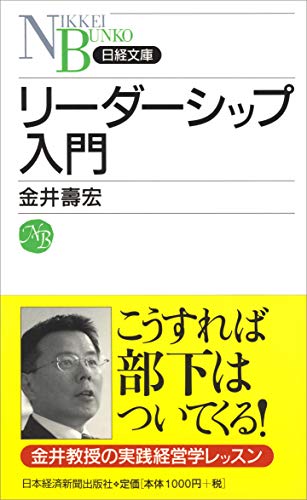- 志を立てる(仕事の意義と意味を掴む)
- 好きになる(興味が熱意と工夫を生む)
- 自らを知る(自分の力、相手の力、自然の理を知る)
- 衆知を集める(多くの人の知恵を集める)
- 訴える(繰り返し訴える)
- まかせる(徹底してまかせる)
- 要望追求する(成功するまでやらせる)
- 叱る、ほめる(寛厳自在、信賞必罰)
- 責任を自覚する(原因、責任は常に内にある)
- 部下に学ぶ(指導しつつも教わり学ぶ)
- 愛嬌
- カン、体験実践を重んじる(理外の理、直観力を養う)
- たくまずして人の心をつかむ(テクニックではなく心情に訴える)
- とらわれない(日々新た)
解説
このリストを引用した『リーダーシップ入門』では、リーダーシップを身につけるために「リーダーシップについての持論」を持つことの意義を以下のように強調しています。
内省を通じて、あるいは質問と議論を通じて、持論は経験から形成されていく。持論をもつから、内省も質問も議論も研ぎ澄まされたものになる。
このリストは持論のサンプルであり、そのまま皆さんの「持論」にはなりえません。持論リストのまとめ方は第2部に解説しましたので、ぜひオリジナルの「リーダーシップ○か条」を作り、育てていってください。
結果として言葉になった○か条は、一見すると平凡な言葉の羅列かもしれません。しかし、なぜこの○か条なのか。どのような意味が、知恵が、込められているのか。問われればすらすらと語れるはずです。そのようにして作った持論こそが、未知の困難にぶつかったときの自分の判断基準になっていくのだと思います。
引用元
金井 寿宏著『リーダーシップ入門』日本経済新聞社 2005年
p190「図表4-13 指導者の心得」より。最後の三つは補足扱いとなっていました