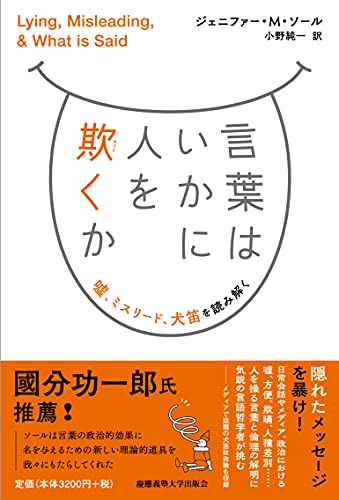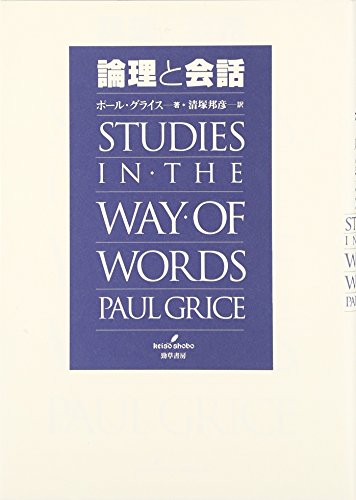まえがき
『グライスによれば、会話の参加者が「会話の格率」――量、質、関係、様態――に従うことで「会話の含意」が成り立つ。』
リスト
- 量の格率: (1) 会話に必要とされるだけの情報を全て与えること、(2) 必要以上の情報を与えないこと
- 質の格率: 真である情報を与えること、すなわち (1) 真でないと知っていることを言わないこと、(2) 十分な根拠のないことを言わないこと
- 関係の格率: 会話の主題に関係することを言うこと
- 様態の格率: 明瞭でなければならない、すなわち (1) 把握できない表現を避けること、(2) 多義性(曖昧さ)を避けること、(3) 簡潔である(不要な冗長さを避ける)こと、(4) 順序立っていること
あとがき
まえがきを含めて、ジェニファー・M・ソール 『言葉はいかに人を欺くか:嘘、ミスリード、犬笛を読み解く』 (慶應義塾大学出版会、2021年)より。小野純一氏の「訳者解題」からの編集・引用です。
リストは「会話の公理(ポール・グライス)」と同じです。ただ、別建てで引用しておきたく思いました。というのは、グライスは『「原理」と「格率」を示した』とあって、その「原理」を引用したかったから。
彼の理論によれば、その前提には「協調の原理」と「会話の格率」がある。協調の原理とは、自分が参加する会話の中で合意される目的や方向性に従うことである。少なくともこれが守られていると想定されるときに聞き手が意味を推論し、また話し手も聞き手にその能力があると仮定している場合に、会話の含意が成り立つ。
本文の参考文献に挙げられていたグライスの著書が訳出されていました。別途目を通すべくメモしておきます。
タイトル: 言葉はいかに人を欺くか:嘘、ミスリード、犬笛を読み解く
著者: ジェニファー・M・ソール(著)、Jennifer Mather Saul(著)、小野 純一(翻訳)
出版社: 慶應義塾大学出版会
出版日: 2021-04-20