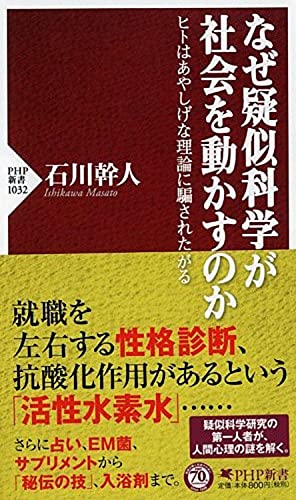まえがき
『科学が満たすべき条件を、私は10項目に整理している(略)。(略)「科学である」との主張があったとき、「その科学性を探るために問いただすべき項目」と考えていただきたい。』
リスト
- 理論の論理性:説明が一貫している。合理的な前提に基づく。飛躍がない。
- 理論の体系性:他の科学的知見と整合。矛盾する結果が出ない。
- 理論の普遍性:広く成立する。特殊な状況に限らない。
- データの再現性:複数の研究で確認。第三者が評価。否定的データを無視しない。
- データの客観性:無作為化対照試験で主観を排除。直感や権威に頼らない。
- 理論とデータの妥当性:適切にデータを収集。他の要因で偶然一致しない。
- 理論とデータの予測性:将来のデータを予測できる。予測が検証される。反証を無視しない。
- 社会的公共性:定義・測定方法が明瞭。評価がオープン。無批判に信じない。
- 社会的歴史性:過去に手法の議論や対抗理論との比較がされている。評価が低くても無視しない。
- 社会的応用性:将来にわたって社会的に利用可能。誤解されて利用されない。
あとがき
まえがきを含めて、石川 幹人『なぜ疑似科学が社会を動かすのか』 (PHP研究所、2016年)より。
著者の意図が伝わるよう、まえがきで略した部分を補って再度引用します。
この科学が満たすべき条件を、私は一〇項目に整理しているので、それを取り上げながら、科学の度合いを評定する方法を紹介しよう。ただし、以下の各条件は市民が個人で調べるのは、難しい面がある。あくまで、「科学である」との主張があったとき、「その科学性を探るために問いただすべき項目」と考えていただきたい。
また、リストはかなり圧縮要約したうえで引用しています。たとえば第7項目「理論とデータの予測性:将来のデータを予測できる。予測が検証される。反証を無視しない。」は、本書では次のように書かれています。
●理論とデータの相互作用が満たすべき条件(妥当性・予測性)
(略)
予測性:将来の実験や調査のデータが(確率的にでも)予測可能な理論が立てられているか、そうした予測が検証されているか、逆に反証があるのに無視されていないか、などの観点で評価される。たとえば(以下略)
著者がせっかくていねいに記したものを乱暴に要約したことをお詫びしなければなりません。でもここまでハンディにしておくと、チェックリストとしてのわたしにとっての使い勝手は向上します。