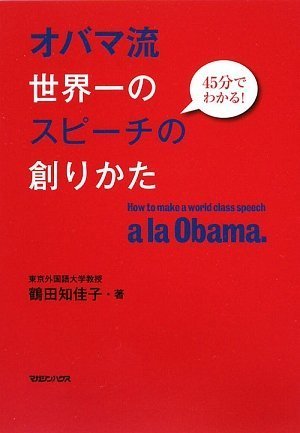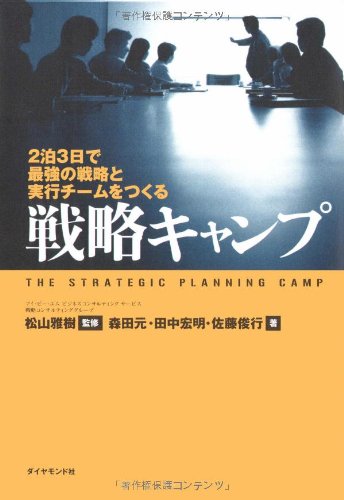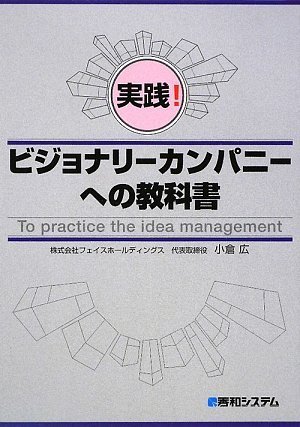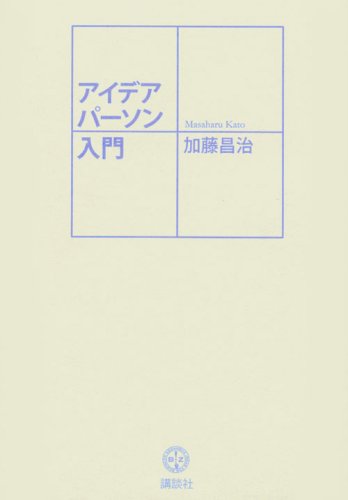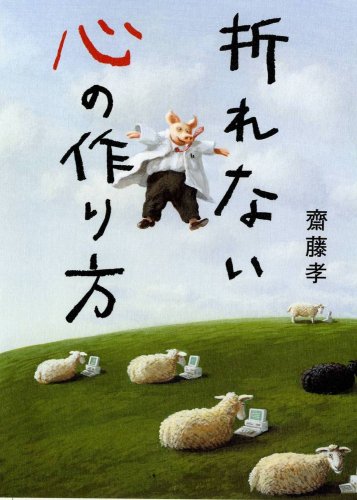まえがき
『インデックスファンドを購入するということは、いわば「市場全体に投資している」ということでもあります。コストを抑えながらじっくりと市場全体の成長を見守りたいという個人投資家にとって、インデックスファンドの利用価値は高いといえるのではないでしょうか。』
リスト
- 【販売手数料】ノーロード(手数料無料)の投信が望ましい
- 【信託報酬】できるだけ低いものがよい。日本株で運用する投信なら年1%未満
- 【信託財産保留額】できれば不要な投信を選びたい
- 【運用実績】設定から5年以上の運用実績が欲しい
- 【運用規模】日本株で運用する投信なら100億円以上が目安。純資産総額が急激に増減している場合は要注意
- 【運用期間】信託期限は「無期限」の投信を選ぼう
あとがき
まえがきを含めて『投信のイロハ ― 初心者向け「インデックス連動型」』(日本経済新聞 夕刊 2009年7月4日)より。記事中の表を編集・引用しました。コスト(最初の3項目)、過去(運用実績)、現在(運用規模)、そして未来(運用期間)と、目配りのあるリストですね。
執筆者はファイナンシャルプランナー 大竹のり子氏。株式会社エフピーウーマン代表としてさまざまにご活躍の方でした。