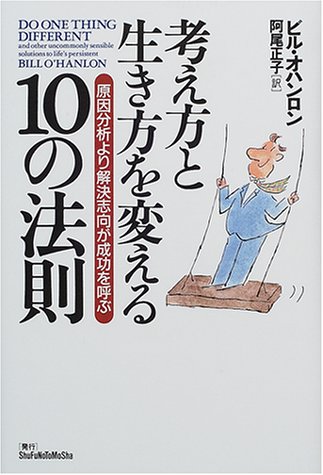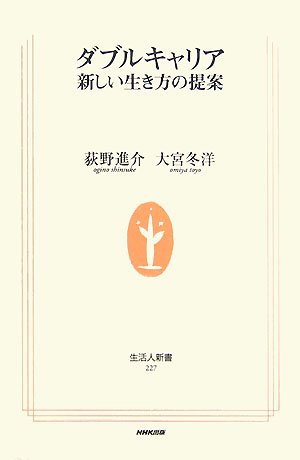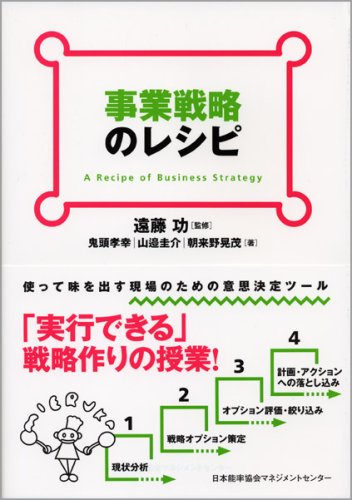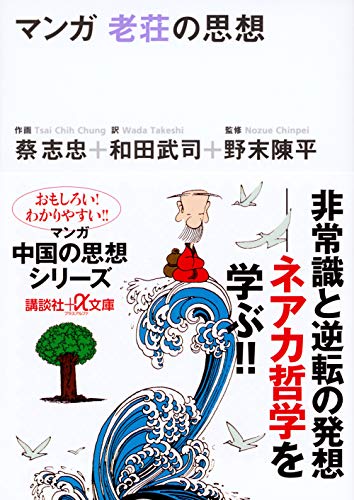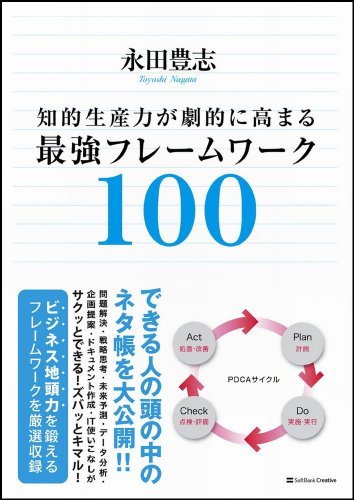まえがき
『なんの効果もなく、あなたの気分をめいらせるだけの質問から、新しい可能性を切りひらき、問題解決と喜びをもたらす質問に頭を切り替えよう。』
リスト
- この困った状況についてわたしはなにを見聞きでき(事実の確認)、その事実からどんな結論(あらすじ、判断、批評)を導きだせるか?
- この問題をなんとか切り抜けなければいけないとしたら、そこから得るものはなに?
- 望ましい結果を得るためにすべきことは?
- 望ましい結果を得るためならやめてもいいと思えることは?
- これはほんとうにわたしが心血をそそぎたいものだろうか? もし違うとしたらどこに目を向けたらいい?
- この問題についていまわたしにできることはある?あるとしたら、まず最初にやるべきことは?もしできることがないなら、現状を変えられないことにどうやって折り合いをつければいい?
- この困った状況のなかでうれしかった瞬間や場面は?
- 以前にこれと同じような状況をうまく切り抜けたときはなにをした?
あとがき
まえがきを含めてビル・オハンロン『考え方と生き方を変える10の法則―原因分析より解決志向が成功を呼ぶ』より。
原因は後で追求するとして、まずはこの困った状況を何とかしたい。そんなときに思い出したい問いかけですね。
- タイトル: 考え方と生き方を変える10の法則―原因分析より解決志向が成功を呼ぶ
- 著者: ビル オハンロン(著)、O’hanlon,Bill(原著)、正子, 阿尾(翻訳)
- 出版社: 主婦の友社
- 出版日: 2000-12-01