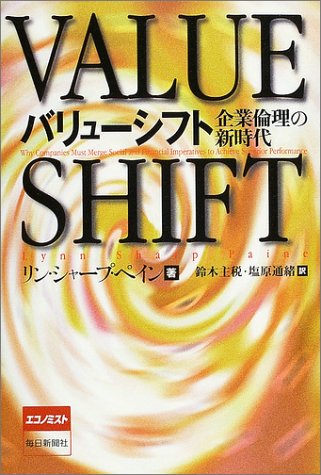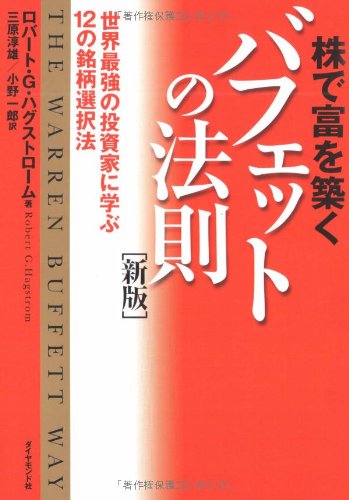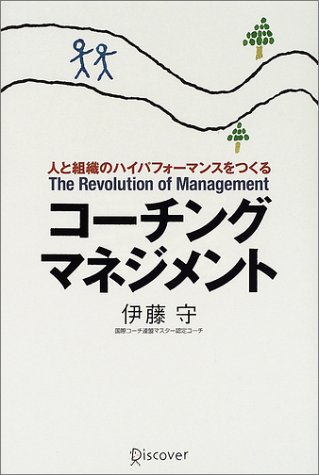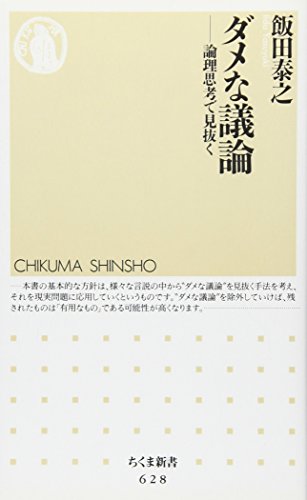まえがき
「日常生活で生じるさまざまな問題や要求に対して、建設的かつ効果的に対処するために必要な能力」として、WHOが定めた10のスキル。
リスト
- 意思決定(Decision making)― 生活に関する決定を建設的に行う力
- 問題解決(Problem solving)― 日常の問題を建設的に処理する力
- 創造的思考(Creative thinking)― 直接経験しないことを考える、アイデアを生み出す力
- 批判的思考(Critical thinking)― 情報や経験を客観的に分析する能力
- 効果的コミュニケーション(Effective communication)― 文化や状況に応じた方法で、言語的または非言語的に自分を表現する能力
- 対人関係スキル(Interpersonal relationship skills)― 好ましい方法で人と接触・関係の構築・関係の維持・関係の解消をすることができる
- 自己認識(Self-awareness)― 自分自身の性格、長所と短所、欲求などを知ること
- 共感性(Empathy)― 自分が知らない状況に置かれている人の生き方であっても、それを心に描くことができる能力
- 情動への対処(Coping with emotions)― 自分や他者の情動を認識し、情動が行動にどのように影響するかを知り、情動に適切に対処する能力
- ストレス・コントロール(Coping with stress)― 生活上のストレッサーを認識し、ストレスの影響を知り、ストレスレベルをコントロールする
あとがき
日本語訳は、「スクールカウンセリング」という文部科学省のページから編集・引用させていただきました。WHOでも元々学校教育の目標の一つとして掲げられたようです(←調査が及んでいません)が、これは一生かけて磨いていくスキルですな。
2009/12/14
これが初出かどうかは不明ですが、WHOのサイト内で探し得た最も古い文献です。”UFE SKILLS EDUCATION FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN SCHOOLS“(PDF)