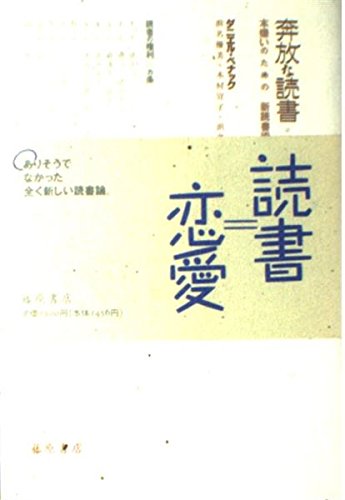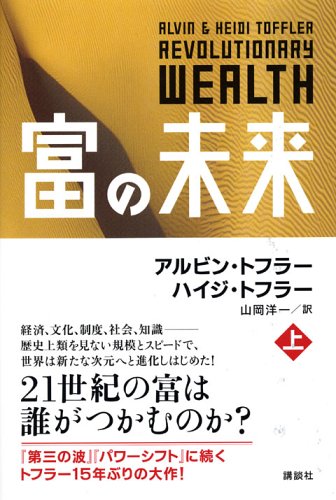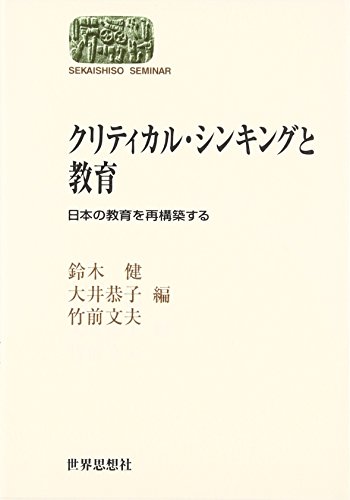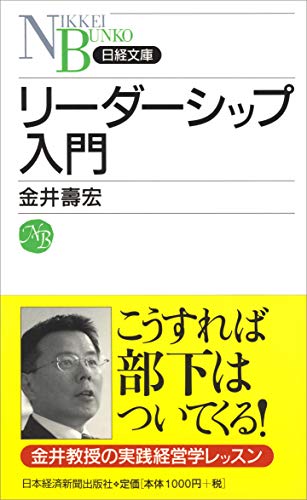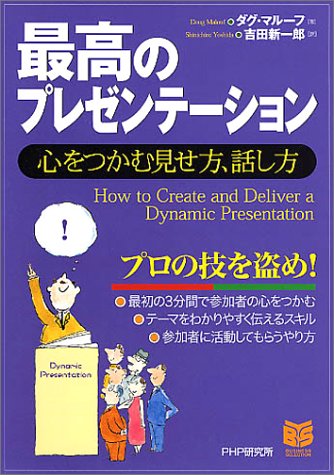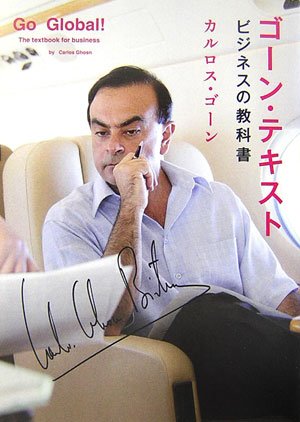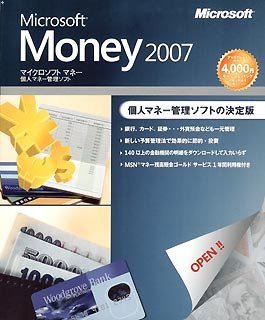まえがき
ひらがな。上の句と下の句で行が分かれています。
リスト
- あきのたの かりほのいほの とまをあらみ
- わがころもでは つゆにぬれつつ
- はるすぎて なつきにけらし しろたへの
- ころもほすてふ あまのかぐやま
- あしびきの やまどりのをの しだりをの
- ながながしよを ひとりかもねむ
- たごのうらに うちいでてみれば しろたへの
- ふじのたかねに ゆきはふりつつ
- おくやまに もみぢふみわけ なくしかの
- こゑきくときぞ あきはかなしき
- かささぎの わたせるはしに おくしもの
- しろきをみれば よぞふけにける
- あまのはら ふりさけみれば かすがなる
- みかさのやまに いでしつきかも
- わがいほは みやこのたつみ しかぞすむ
- よをうぢやまと ひとはいふなり
- はなのいろは うつりにけりな いたづらに
- わがみよにふる ながめせしまに
- これやこの ゆくもかへるも わかれては
- しるもしらぬも あふさかのせき
- わたのはら やそしまかけて こぎいでぬと
- ひとにはつげよ あまのつりぶね
- あまつかぜ くものかよひぢ ふきとぢよ
- をとめのすがた しばしとどめむ
- つくばねの みねよりおつる みなのがは
- こひぞつもりて ふちとなりぬる
- みちのくの しのぶもぢずり たれゆゑに
- みだれそめにし われならなくに
- きみがため はるののにいでて わかなつむ
- わがころもでに ゆきはふりつつ
- たちわかれ いなばのやまの みねにおふる
- まつとしきかば いまかへりこむ
- ちはやぶる かみよもきかず たつたがは
- からくれなゐに みづくくるとは
- すみのえの きしによるなみ よるさへや
- ゆめのかよひぢ ひとめよくらむ
- なにはがた みじかきあしの ふしのまも
- あはでこのよを すぐしてよとや
- わびぬれば いまはたおなじ なにはなる
- みをつくしても あはむとぞおもふ
- いまこむと いひしばかりに ながつきの
- ありあけのつきを まちいでつるかな
- ふくからに あきのくさきの しをるれば
- むべやまかぜを あらしといふらむ
- つきみれば ちぢにものこそ かなしけれ
- わがみひとつの あきにはあらねど
- このたびは ぬさもとりあへず たむけやま
- もみぢのにしき かみのまにまに
- なにしおはば あふさかやまの さねかづら
- ひとにしられで くるよしもがな
- をぐらやま みねのもみぢば こころあらば
- いまひとたびの みゆきまたなむ
- みかのはら わきてながるる いづみがは
- いつみきとてか こひしかるらむ
- やまざとは ふゆぞさびしさ まさりける
- ひとめもくさも かれぬとおもへば
- こころあてに をらばやをらむ はつしもの
- おきまどはせる しらぎくのはな
- ありあけの つれなくみえし わかれより
- あかつきばかり うきものはなし
- あさぼらけ ありあけのつきと みるまでに
- よしののさとに ふれるしらゆき
- やまがはに かぜのかけたる しがらみは
- ながれもあへぬ もみぢなりけり
- ひさかたの ひかりのどけき はるのひに
- しづごころなく はなのちるらむ
- たれをかも しるひとにせむ たかさごの
- まつもむかしの ともならなくに
- ひとはいさ こころもしらず ふるさとは
- はなぞむかしの かににほひける
- なつのよは まだよひながら あけぬるを
- くものいづこに つきやどるらむ
- しらつゆに かぜのふきしく あきののは
- つらぬきとめぬ たまぞちりける
- わすらるる みをばおもはず ちかひてし
- ひとのいのちの をしくもあるかな
- あさぢふの をののしのはら しのぶれど
- あまりてなどか ひとのこひしき
- しのぶれど いろにいでにけり わがこひは
- ものやおもふと ひとのとふまで
- こひすてふ わがなはまだき たちにけり
- ひとしれずこそ おもひそめしか
- ちぎりきな かたみにそでを しぼりつつ
- すゑのまつやま なみこさじとは
- あひみての のちのこころに くらぶれば
- むかしはものを おもはざりけり
- あふことの たえてしなくは なかなかに
- ひとをもみをも うらみざらまし
- あはれとも いふべきひとは おもほえで
- みのいたづらに なりぬべきかな
- ゆらのとを わたるふなびと かぢをたえ
- ゆくへもしらぬ こひのみちかな
- やへむぐら しげれるやどの さびしきに
- ひとこそみえね あきはきにけり
- かぜをいたみ いはうつなみの おのれのみ
- くだけてものを おもふころかな
- みかきもり ゑじのたくひの よるはもえ
- ひるはきえつつ ものをこそおもへ
- きみがため をしからざりし いのちさへ
- ながくもがなと おもひけるかな
- かくとだに えやはいぶきの さしもぐさ
- さしもしらじな もゆるおもひを
- あけぬれば くるるものとは しりながら
- なほうらめしき あさぼらけかな
- なげきつつ ひとりぬるよの あくるまは
- いかにひさしき ものとかはしる
- わすれじの ゆくすゑまでは かたければ
- けふをかぎりの いのちともがな
- たきのおとは たえてひさしく なりぬれど
- なこそながれて なほきこえけれ
- あらざらむ このよのほかの おもひでに
- いまひとたびの あふこともがな
- めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに
- くもがくれにし よはのつきかな
- ありまやま ゐなのささはら かぜふけば
- いでそよひとを わすれやはする
- やすらはで ねなましものを さよふけて
- かたぶくまでの つきをみしかな
- おほえやま いくののみちの とほければ
- まだふみもみず あまのはしだて
- いにしへの ならのみやこの やへざくら
- けふここのへに にほひぬるかな
- よをこめて とりのそらねは はかるとも
- よにあふさかの せきはゆるさじ
- いまはただ おもひたえなむ とばかりを
- ひとづてならで いふよしもがな
- あさぼらけ うぢのかはぎり たえだえに
- あらはれわたる せぜのあじろぎ
- うらみわび ほさぬそでだに あるものを
- こひにくちなむ なこそをしけれ
- もろともに あはれとおもへ やまざくら
- はなよりほかに しるひともなし
- はるのよの ゆめばかりなる たまくらに
- かひなくたたむ なこそをしけれ
- こころにも あらでうきよに ながらへば
- こひしかるべき よはのつきかな
- あらしふく みむろのやまの もみぢばは
- たつたのかはの にしきなりけり
- さびしさに やどをたちいでて ながむれば
- いづこもおなじ あきのゆふぐれ
- ゆふされば かどたのいなば おとづれて
- あしのまろやに あきかぜぞふく
- おとにきく たかしのはまの あだなみは
- かけじやそでの ぬれもこそすれ
- たかさごの をのへのさくら さきにけり
- とやまのかすみ たたずもあらなむ
- うかりける ひとをはつせの やまおろし
- はげしかれとは いのらぬものを
- ちぎりおきし させもがつゆを いのちにて
- あはれことしの あきもいぬめり
- わたのはら こぎいでてみれば ひさかたの
- くもゐにまがふ おきつしらなみ
- せをはやみ いはにせかるる たきがはの
- われてもすゑに あはむとぞおもふ
- あはぢしま かよふちどりの なくこゑに
- いくよねざめぬ すまのせきもり
- あきかぜに たなびくくもの たえまより
- もれいづるつきの かげのさやけさ
- ながからむ こころもしらず くろかみの
- みだれてけさは ものをこそおもへ
- ほととぎす なきつるかたを ながむれば
- ただありあけの つきぞのこれる
- おもひわび さてもいのちは あるものを
- うきにたへぬは なみだなりけり
- よのなかよ みちこそなけれ おもひいる
- やまのおくにも しかぞなくなる
- ながらへば またこのごろや しのばれむ
- うしとみしよぞ いまはこひしき
- よもすがら ものおもふころは あけやらで
- ねやのひまさへ つれなかりけり
- なげけとて つきやはものを おもはする
- かこちがほなる わがなみだかな
- むらさめの つゆもまだひぬ まきのはに
- きりたちのぼる あきのゆふぐれ
- なにはえの あしのかりねの ひとよゆゑ
- みをつくしてや こひわたるべき
- たまのをよ たえなばたえね ながらへば
- しのぶることの よわりもぞする
- みせばやな をじまのあまの そでだにも
- ぬれにぞぬれし いろはかはらず
- きりぎりす なくやしもよの さむしろに
- ころもかたしき ひとりかもねむ
- わがそでは しほひにみえぬ おきのいしの
- ひとこそしらね かわくまもなし
- よのなかは つねにもがもな なぎさこぐ
- あまのをぶねの つなでかなしも
- みよしのの やまのあきかぜ さよふけて
- ふるさとさむく ころもうつなり
- おほけなく うきよのたみに おほふかな
- わがたつそまに すみぞめのそで
- はなさそふ あらしのにはの ゆきならで
- ふりゆくものは わがみなりけり
- こぬひとを まつほのうらの ゆふなぎに
- やくやもしほの みもこがれつつ
- かぜそよぐ ならのをがはの ゆふぐれは
- みそぎぞなつの しるしなりける
- ひともをし ひともうらめし あぢきなく
- よをおもふゆゑに ものおもふみは
- ももしきや ふるきのきばの しのぶにも
- なほあまりある むかしなりけり