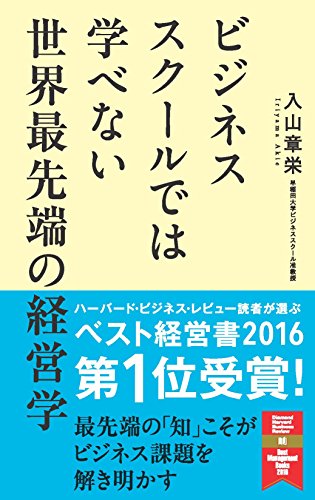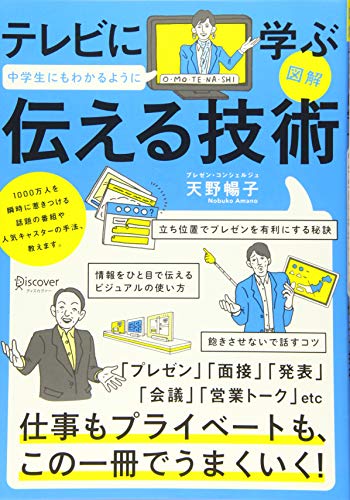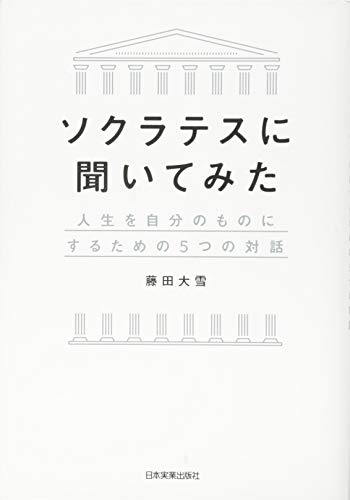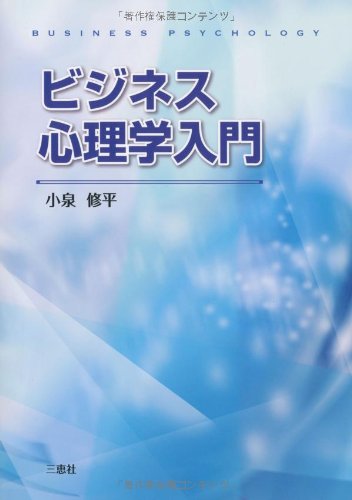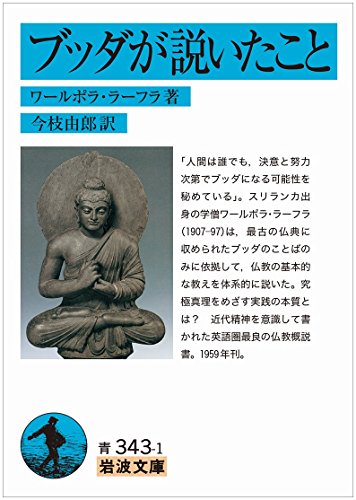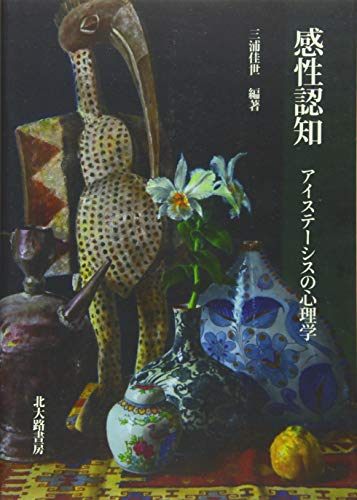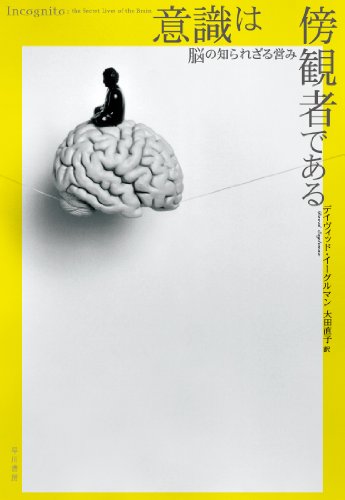まえがき
『トランザクティブ型リーダーは「アメとムチ」を重視しますが、トランスフォーメーショナル型リーダーが重視するのは「啓蒙」です。』
リスト
- 組織のミッションを明確に掲げ、部下の組織に対するロイヤルティーを高める (II)
- 事業の将来性や魅力を前向きに表現し、部下のモチベーションを高める (IM)
- 常に新しい視点を持ち込み、部下のやる気を刺激する (IS)
- 部下一人ひとりと個別に向き合いその成長を重視する (IC)
あとがき
まえがきを含めて、入山 章栄『ビジネススクールでは学べない 世界最先端の経営学』(日経BP社、2015年)より。リスト項目の後にあるアルファベットは、”Transformational leadership” (Wikipedia) からの引用です。この4要素は頭がIで揃えられていて、リストフリーク的には見逃せなかったので。ちなみに Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, Individualized Consideration の略。ただしこの4要素を提案した Bass の論文(参考文献1)ではそうなっておらず、II はずばり Charisma でした。
- タイトル: ビジネススクールでは学べない 世界最先端の経営学
- 著者: 入山 章栄(著)
- 出版社: 日経BP
- 出版日: 2015-11-20
この本からの他のリスト
参考文献
(1) Bass, Bernard M. “From transactional to transformational leadership: learning to share the vision.” Organizational Dynamics 18.3 (1990): 19-32.
(2) 東俊之. “変革型リーダーシップ論の問題点: 新たな組織変革行動論へ向けて.” 京都マネジメント・レビュー 8 (2005): 125-144.