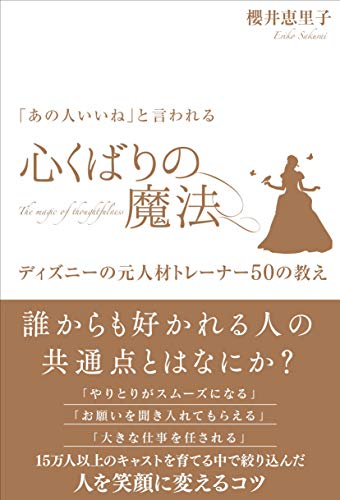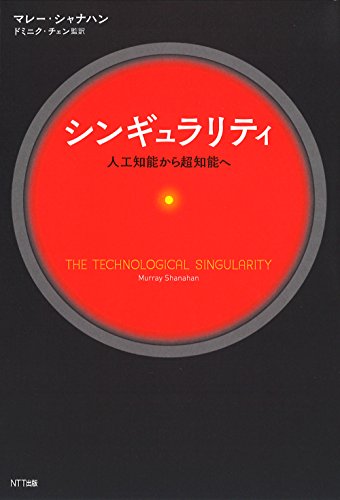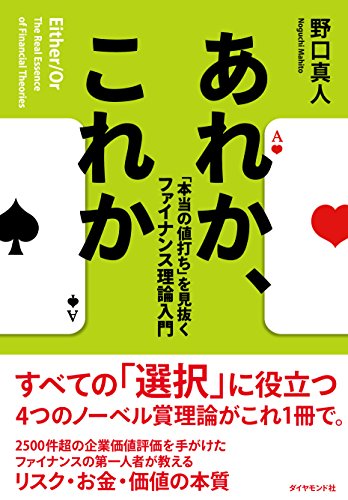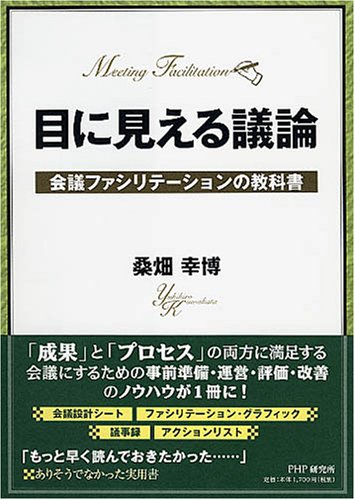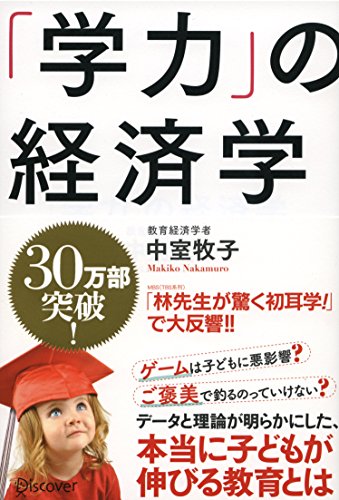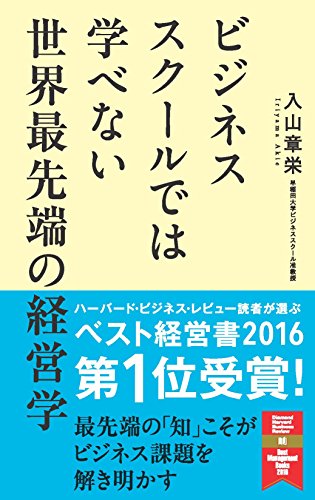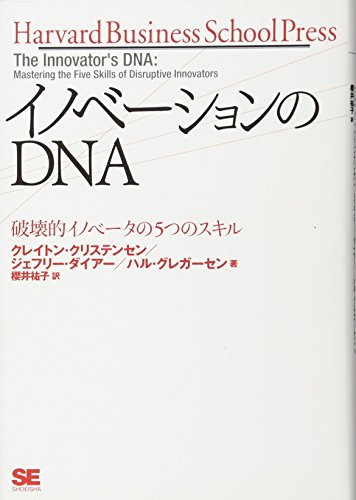まえがき
『ディズニーには、「人財」の成長モデルというものがあります。』
リスト
- 【Make up(一人前のキャストとして舞台に立つ準備をする)】 上司や先輩のサポートを得ながら標準的なオペレーションができる。
- 【Action!(一人前のキャストとして演技を始める)】 独力で標準的なオペレーションができる。
- 【Growing up(キャストとして成長し後輩達を優しく見守る)】 独力で標準的なオペレーションができ、スキル面や精神面で後輩のサポートができる。
- 【Instruct(自ら演じるだけでなく新しいキャストを指導する)】 他者の手本となり得るオペレーションができる。後輩に指導ができる。
- 【Captain(自ら演じながらロケーション全体を統率する)】 ロケーション(職場)全体の視点でオペレーションができる。
あとがき
まえがきは、櫻井 恵里子『「一緒に働きたい」と思われる 心くばりの魔法 〜ディズニーの元人材トレーナー50の教え』(サンクチュアリ出版、2016年)から、リストは「グレードアップ制度」(東京ディズニーリゾート キャスティングセンター)からの引用です。
- タイトル: 「一緒に働きたい」と思われる 心くばりの魔法 〜ディズニーの元人材トレーナー50の教え〜
- 著者: 櫻井 恵里子(著)
- 出版社: サンクチュアリ出版
- 出版日: 2016-04-25