まえがき
『ちなみに、アメリカで出版されている『博士号のとり方』という本で書かれている審査基準は、以下の項目です。』
リスト
- 研究課題
- 研究課題にあわせた研究分野の評価
- 研究の手法
- 研究による貢献
- 合理的な思考能力
- クリエイティブな思考能力
- 執筆力
- データ収集力
- データ解析力
- データの表示力
- 研究対象、クライアントなどの倫理的な扱い
- 剽窃や盗用の拒否
- データの捏造や改ざんの拒否
あとがき
まえがきを含めて、小熊 英二『基礎からわかる 論文の書き方』 (講談社、2022年)より。リストは本文からの編集・引用です。
このリストの直前にまえがきで引用した文章があり、参考文献として『博士号のとり方』[1]が添えられていました。本書での参考文献は第6版でしたが、リンクは本投稿の作成時点での最新版である第7版に張っておきます。
項目から内容の想像がだいたいつきますが、最初の「研究課題」は参考文献を読んでみないとわかりません。本書でいう「主題」と同じ意味合いだとすると、研究課題は論文が答えるべき問いです。設定した研究課題は明確で興味深いか、といったことが基準になるでしょうか。
思考能力を合理的なものとクリエイティブなものに分けているのも興味深いです。ひらめきとか意外な連想があるかどうかが審査基準に含まれているのでしょうか。博士号を取る予定はありませんが目を通してみたくなりました。
参考文献
[1] E・M・フィリップス、D・S・ピュー『博士号のとり方[第6版]―学生と指導教員のための実践ハンドブック―』 (名古屋大学出版会、2018年)
タイトル: 博士号のとり方[第7版]―学生と指導教員のための実践ハンドブック―
著者: E・M・フィリップス(著)、C・G・ジョンソン(著)、角谷 快彦(翻訳)
出版社: 名古屋大学出版会
出版日: 2025-05-27
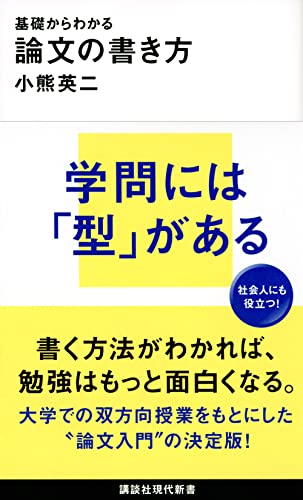
![『博士号のとり方[第7版]―学生と指導教員のための実践ハンドブック―』の書影](https://listfreak.com/archit/media/cache/4815811946.jpg)