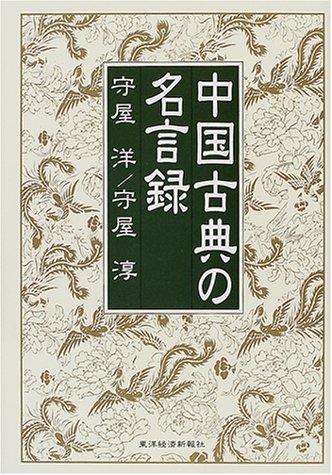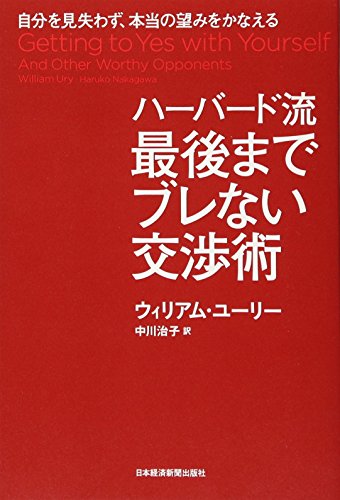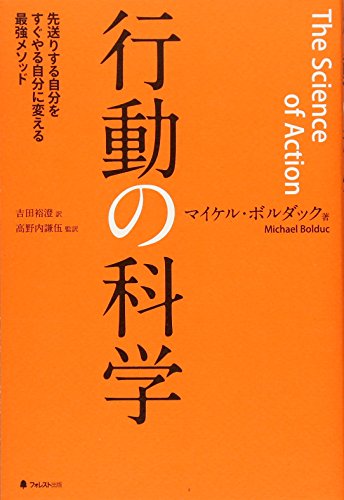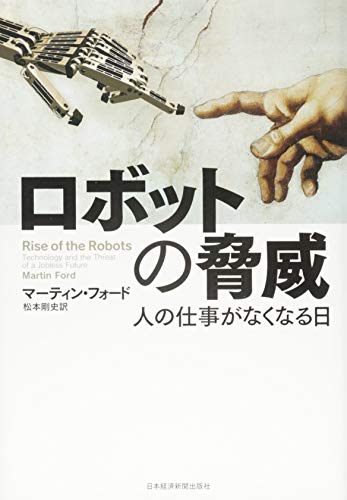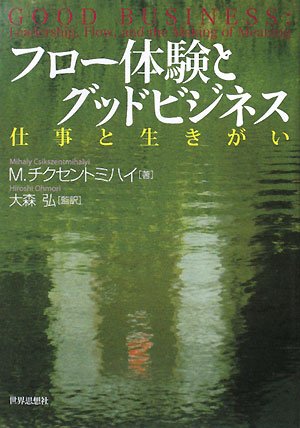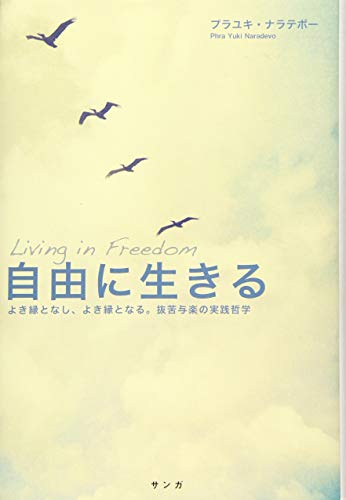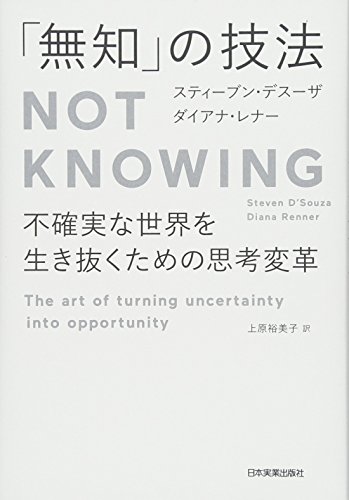まえがき
『孔子曰わく、
リスト
恭 なれば則ち侮 られず(謙虚であれば、人からバカにされることはない)。寛 なれば則ち衆 を得(寛容であれば、まわりに人が集まってくる)。信 なれば則ち人任 ず(誠実であれば、人々の信頼を得ることができる)。敏 なれば則ち功 あり(機敏であれば、仕事を成功させることができる)。恵 なれば則ち以って人を使うに足る(恩恵を施せば、人は喜んでついてくる)。
あとがき
守屋 洋、守屋 淳『中国古典の名言録』(東洋経済新報社、2001年)から編集のうえ引用。リストは『論語』陽貨篇からの採録。
子張が「仁」について孔子に教えを請うたときの答え。仁の五者という言い回しがあるわけではありませんが、タイトルをつけねばならないので命名してみました。