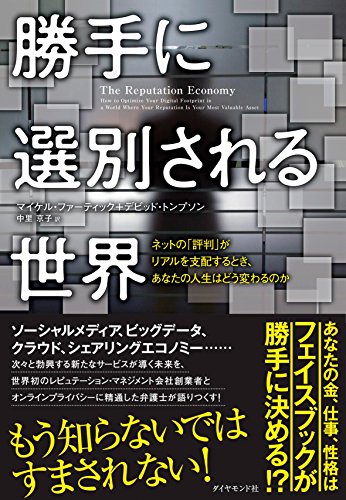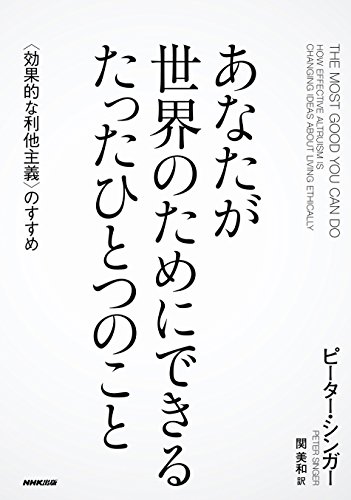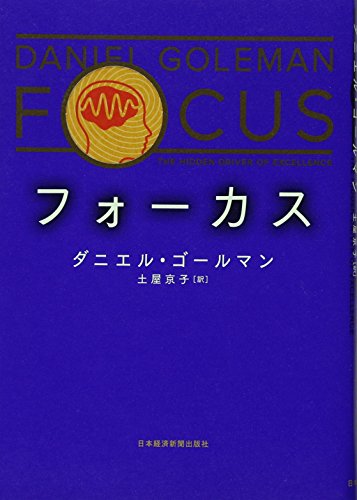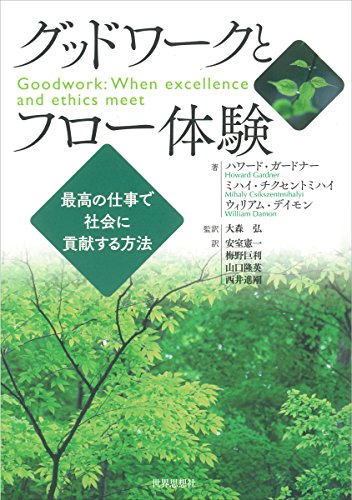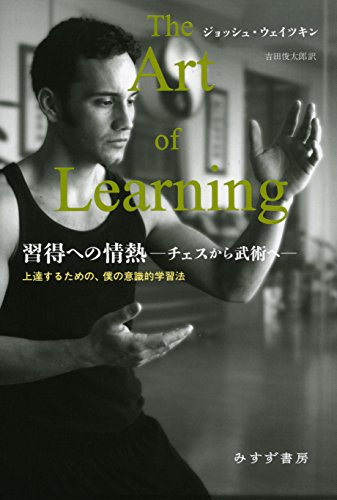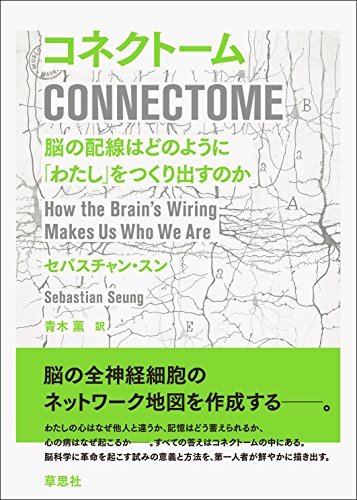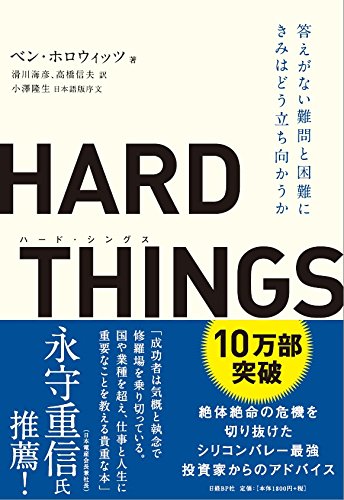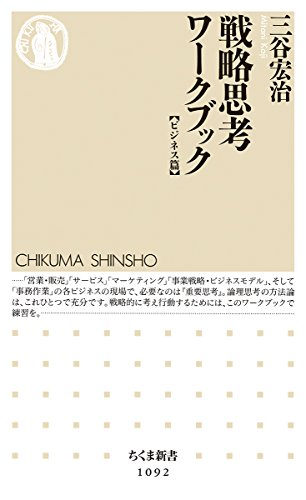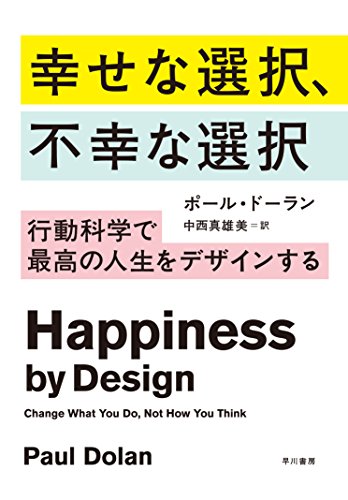まえがき
『「レピュテーション経済」は、評判が瞬時に分析・保管され、特別待遇や利益を手にするパスポートとして使われるような世界だ。』
リスト
- すべてが保管される (Stored)
- すべてが点数化される (Scored)
- すべてが機械化される (Potent)
- すべてがランクづけされる (Discoverable):
- すべてが定量化される (Disruptive)
- すべてがリアルタイム化される (Instant)
- すべてが互換性を持つ (Portable)
- すべてが脱文脈化される (Inaccurate)
- すべてが先手必勝になる (Proactive)
あとがき
まえがきを含めて、マイケル・ファーティック、デビッド・トンプソン 『勝手に選別される世界――ネットの「評判」がリアルを支配するとき、あなたの人生はどう変わるのか』より。リストは原書と訳書の目次から引用しました [1][2]。 内容が想像しづらいものもありますが、さいわい訳書の目次[1]が充実しているので、そちらでだいたい見当が付くかと。
- タイトル: 勝手に選別される世界――ネットの「評判」がリアルを支配するとき、あなたの人生はどう変わるのか
- 著者: マイケル・ファーティック(著)、デビッド・トンプソン(著)、中里 京子(翻訳)
- 出版社: ダイヤモンド社
- 出版日: 2015-12-11
[1] 日本語の目次はダイヤモンド社の書籍紹介ページより引用
[2] 英語の目次は紀伊國屋書店の書籍紹介ページより引用