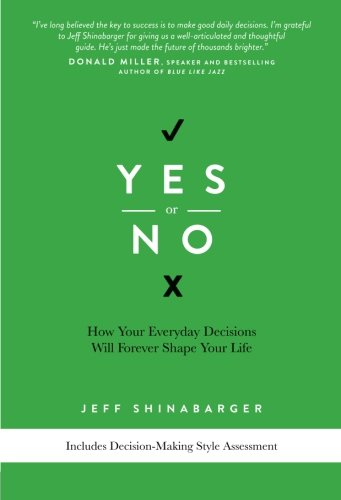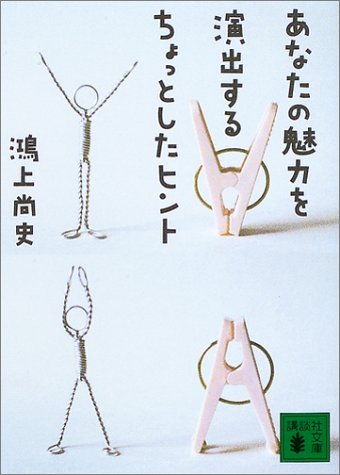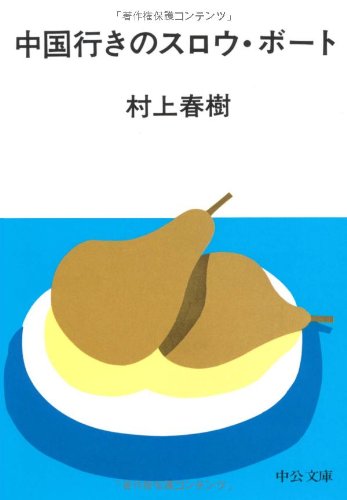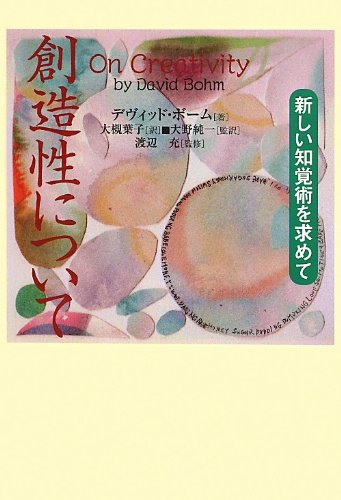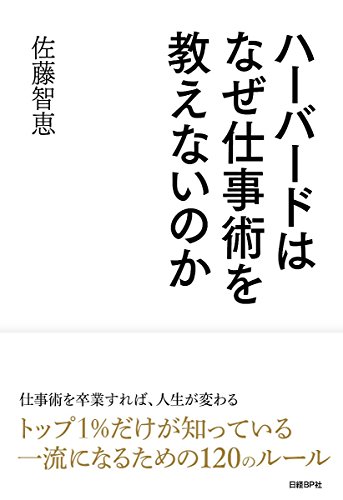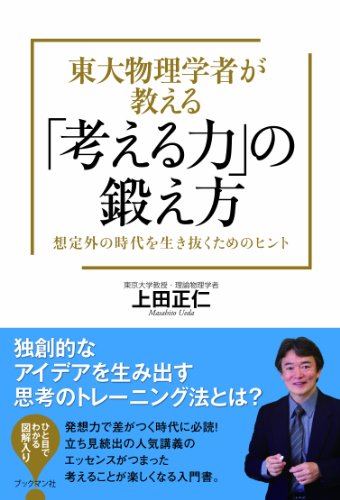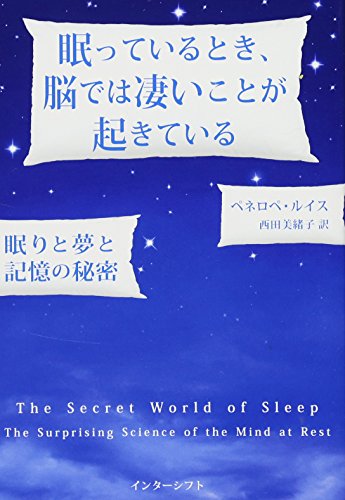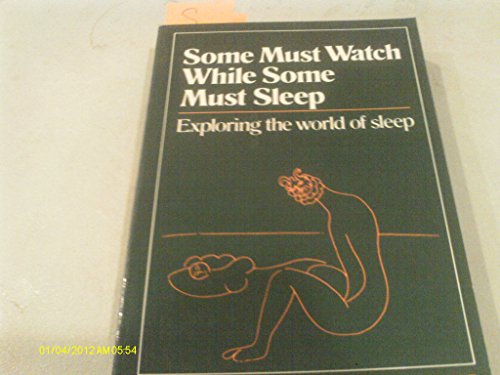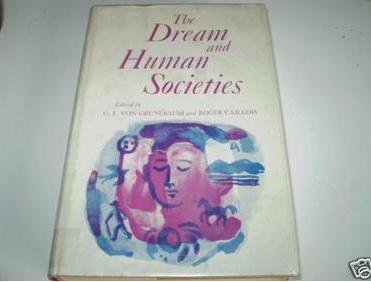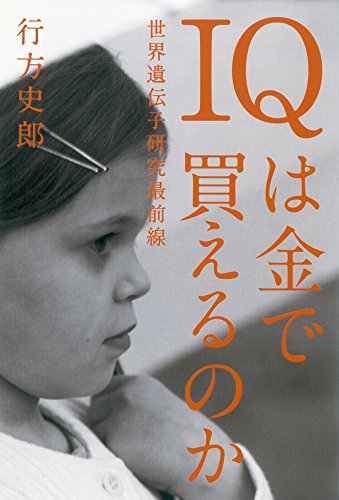まえがき
『どのように意思決定しているのかを理解すると、より自分の考え方を知ることができます。意思決定のスタイルは、あなたの長所と短所を教えてくれます。』
リスト
- 「衆知を集める」派:多くの意見を聞いてコンセンサスを得て決める (Collective reasoning)
- 「データ駆動」派:時間をかけてリサーチし、データに基づいて決める (Data driven)
- 「直感で反射」派:その場の感覚で決める (Gut reaction)
- 「リストアプローチ」派:体系的にメリット・デメリットを考慮し、先を見通したうえで決める (List approach)
- 「スピリチュアルに導かれる」派:神やスピリチュアルなものの声に従って決める (Spiritually guided)
- 「物語に生きる」派:のちに誰かに語る物語によって決める (Story living)
- 「受動的非決定」派:自分で決めずにすむならどんな決定にも従う (Passive undecided)
あとがき
“The 7 Styles of Decision Making“(Entrepreneur)より意訳。まえがきは「自分の意思決定のスタイルを知ろう」(ライフハッカー[日本版])からの引用です。
いずれも、Jeff Shinabarger “Yes or No: How Your Everyday Decisions Will Forever Shape Your Life”を紹介する記事。
独特な分類で面白い。本も読みたくなりましたが、出版後1年半経って未訳ということは、訳書で読むのは無理かな。
- タイトル: Yes or No: How Your Everyday Decisions Will Forever Shape Your Life
- 著者: Shinabarger, Jeff(著)
- 出版社: David C Cook
- 出版日: 2014-09-01