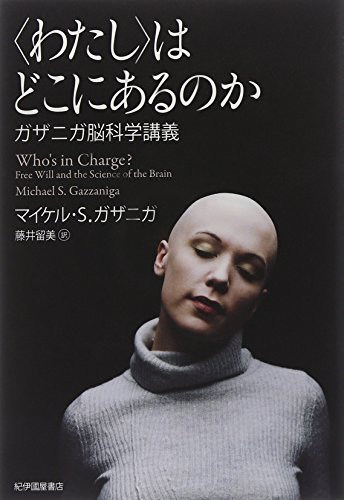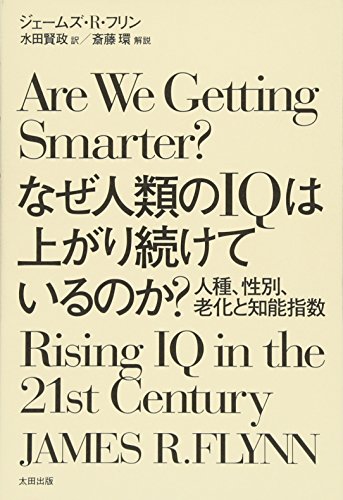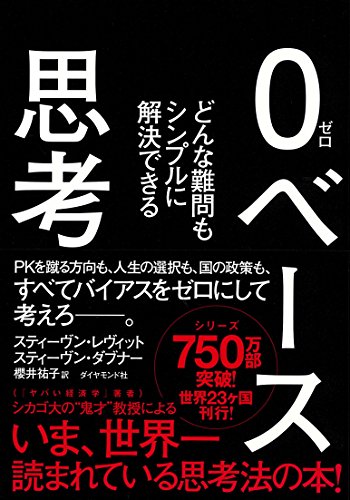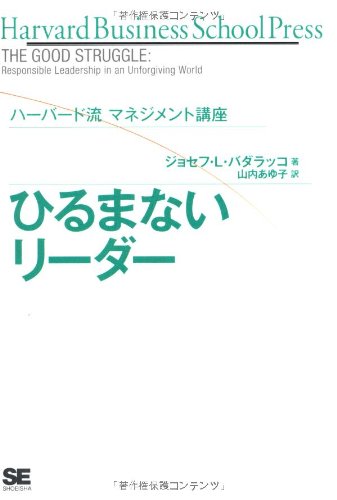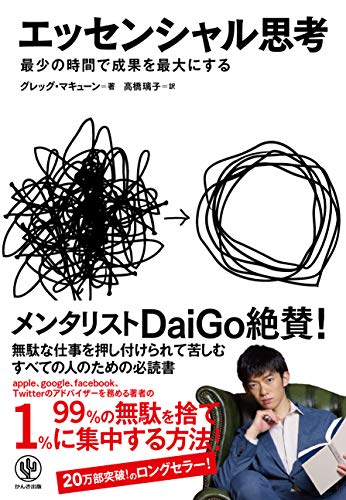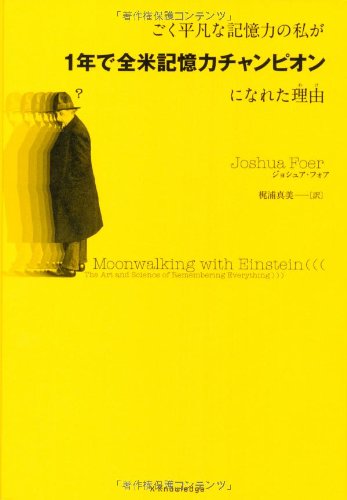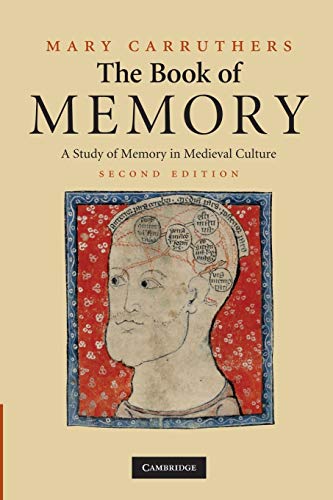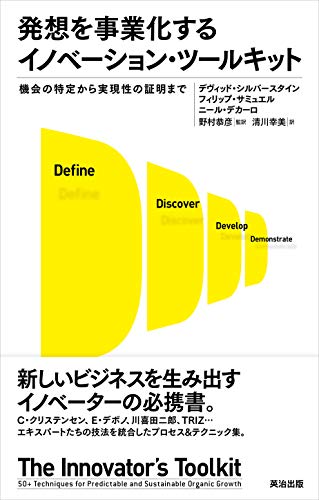まえがき
『アメリカ合衆国の刑法及びコモン・ローは、イギリスの法律家エドワード・コークの唱えた「犯意の原則」――精神も有罪でない限り、行為は有罪では無い――が根底にある』。「犯意」を重い順に並べると。
リスト
- 【目的をもって (purposely)】 その行為あるいはそれが引き起こす結果を目的として行動した
- 【知りながら (knowingly)】 その行為の性質が善か悪か・合法か違法かを自覚していた
- 【無謀に (recklessly)】 正当化できない重大なリスクを意識的に無視した
- 【過失により (negligently)】 意識すべきだった重大なリスクや既知のリスクをつくりだした
あとがき
まえがきの引用文はマイケル・S. ガザニガ『〈わたし〉はどこにあるのか: ガザニガ脳科学講義』(紀伊國屋書店、2014年)より。リスト項目の解説部分も、本書の本文から編集して作成しました。リスト項目の見出し部分は「犯罪構成要素」(ja.wikipedia)を参考にしました。そのほか(参考)に記したエントリを参考にしています。
ちなみに、行為者の精神状態にかかわらず罪は罪とする立場は【厳格責任 (strict liability)】と呼ばれ、現在の米国の模範刑法法典(参考2)では第5項目の位置に置かれています。
- タイトル: 〈わたし〉はどこにあるのか: ガザニガ脳科学講義
- 著者: マイケル・S. ガザニガ(著)、Gazzaniga,Michael S.(原著)、留美, 藤井(翻訳)
- 出版社: 紀伊國屋書店
- 出版日: 2014-08-28
この本からの他のリスト
参考文献
1. Mens rea (en.wikipedia)
2. Model Penal Code (en.wikipedia)