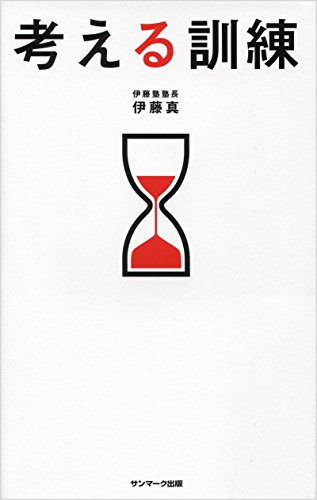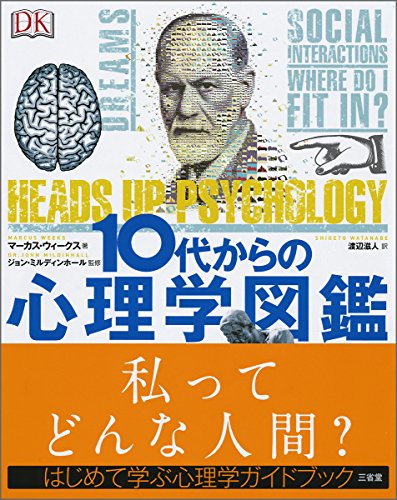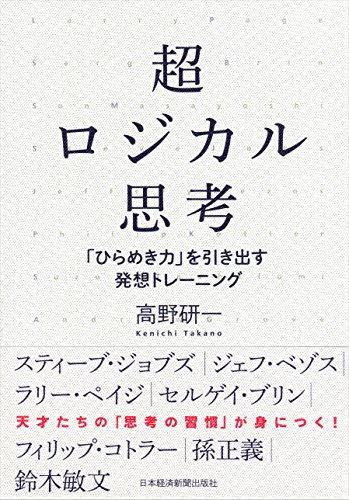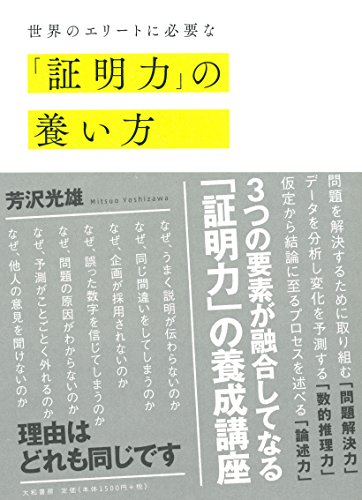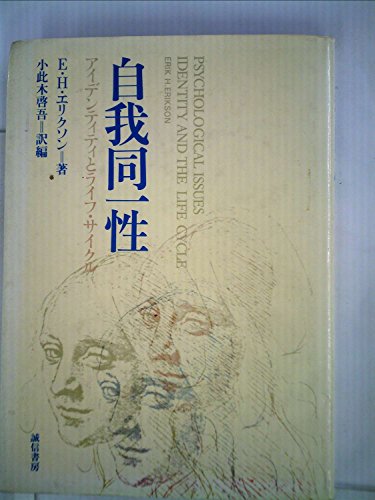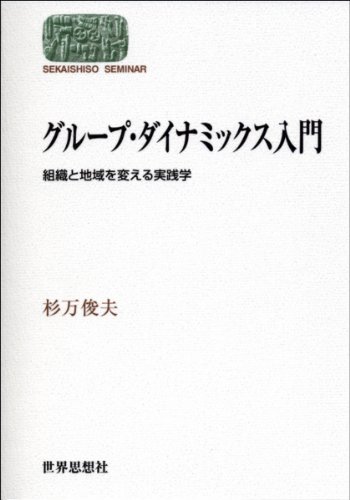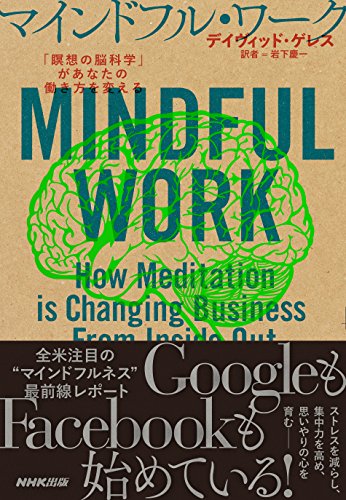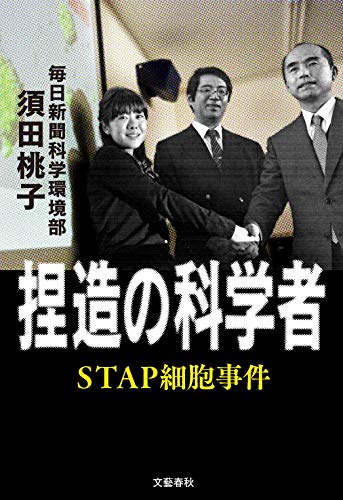まえがき
『ロバート・スターンバーグはさまざまなタイプの愛を調べ、その関係を成り立たせるのは親密さと情熱と責任(コミットメント)という3つの基本要素だと説明しました。』
リスト
- 【親密さ】 愛着、近しさ、つながり、結束の感情。
- 【情熱】 執着的心酔と性的誘因の両方につながる衝動。
- 【決意】 短期的には誰かとともにいようという決断。長期的にはその相手とともに立てた計画。
あとがき
まえがきはマーカス・ウィークス『10代からの心理学図鑑』(三省堂、2015年)より。リストは “Triangular theory of love“(Wikipedia)を翻訳しました。limerence など定訳がないものを含めて、意訳・造語訳を含みます。
原文も、やがて変わる可能性があるので引用しておきます。
* Intimacy – Which encompasses feelings of attachment, closeness, connectedness, and bondedness.
* Passion – Which encompasses drives connected to both limerence and sexual attraction.
* Commitment – Which encompasses, in the short term, the decision to remain with another, and in the long term, plans made with that other.
上記のWikipedia記事では、この3要素がすべて欠けている場合からすべて揃っている場合までの8通りについて、名称と内容が定義されています。
- タイトル: 10代からの心理学図鑑
- 著者: マーカス・ウィークス(著)、ジョン・ミルディンホール(監修)、渡辺 滋人(翻訳)
- 出版社: 三省堂
- 出版日: 2015-08-27
この本からの他のリスト