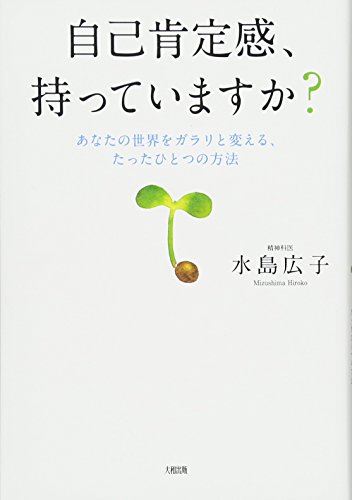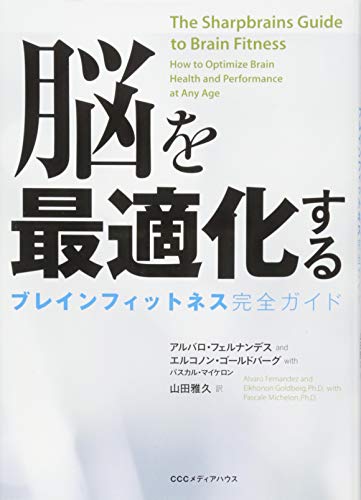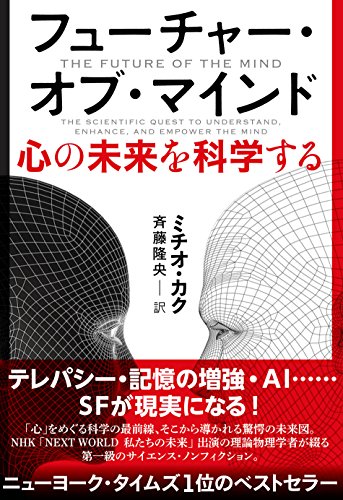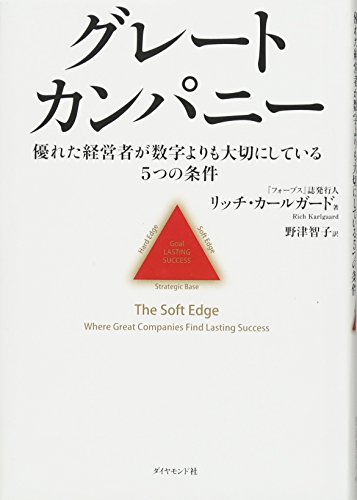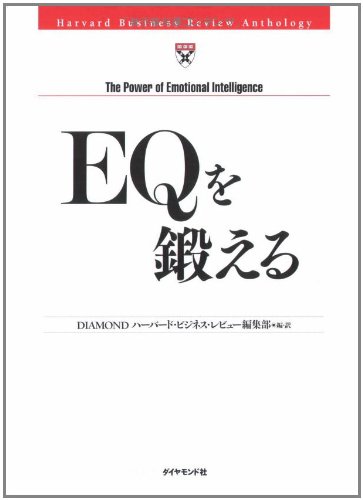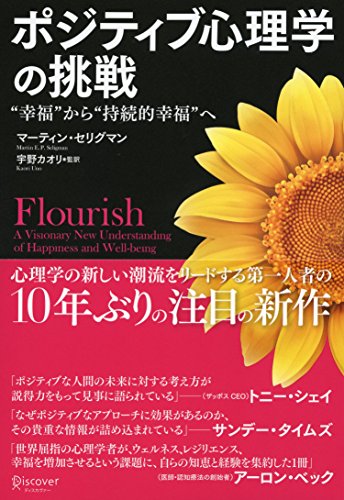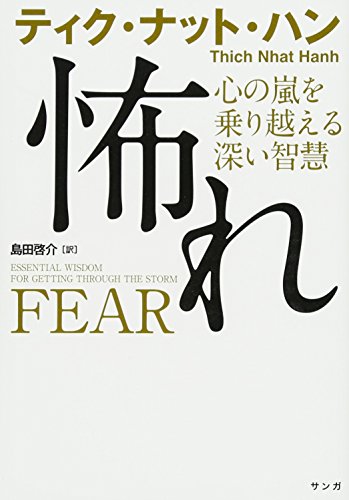まえがき
『行動変容のための科学があります。この分野における第一人者であるプロチャスカは、行動変容には段階があると提唱しています。』
リスト
- 前熟考期:変化について考え始める前段階
- 熟考期:変化しなければと深く考える段階
- 実行期:変わるために実際になにかを試みる段階
- 維持期:起こした変化を最低6か月間保つ段階
- 確立期:変化によって生まれた新しい行動が身につく段階
あとがき
まえがきを含めて、アルバロ・フェルナンデス、エルコノン・ゴールドバーグ、パスカル・マイケロン 『脳を最適化する ブレインフィットネス完全ガイド』(CCCメディアハウス、2015年)より。
調べてみると、これ (Stages of Change) はTranstheoretical model (Wikipedia) という行動変容モデルの構成要素の一つ。別に定義されている、10ステップからなる行動変容のプロセス (Processes of Change) をたどることで、このステージを一段ずつ上っていくようなモデルです。
プロチャスカが共著者として名を連ねている総説からの引用とリストを対比させてみます。(1)
- Precontemplation : No intention to take action within the next 6 months
- Contemplation : Intends to take action within the next 6 months
- Preparation : Intends to take action within the next 30 days and has taken some behavioral steps in this direction
- Action : Changed overt behavior for less than 6 months
- Maintenance : Changed overt behavior for more than 6 months
- Termination : No temptation to relapse and 100% confidence
もともとは6か月、30日といった期間が明示されています。定量性には欠けますが、リストのほうが各段階の意味はわかりやすい。
確立期とはうまい訳ですね。ただし、先に引用した Wikipedia では 「逆戻り&再開」期みたいな言葉が使われています。この理論自体はまだ確立期には至っていないのかも。
- タイトル: 脳を最適化する ブレインフィットネス完全ガイド
- 著者: アルバロ・フェルナンデス(著)、エルコノン・ゴールドバーグ(著)、パスカル・マイケロン(著)、山田雅久(翻訳)
- 出版社: CCCメディアハウス
- 出版日: 2015-10-22
参考文献
(1) Prochaska, James O., Colleen A. Redding, and Kerry E. Evers. “THE TRANSTHEORETICAL MODEL AND STAGES OF CHANGE.” In Glanz, Karen, Barbara K. Rimer, and Kasisomayajula Viswanath, eds. Health behavior and health education: theory, research, and practice. John Wiley & Sons, 2008. Chapter 5.