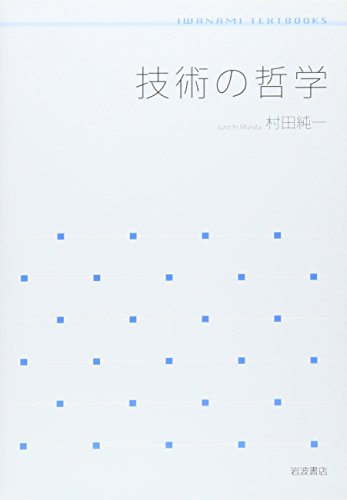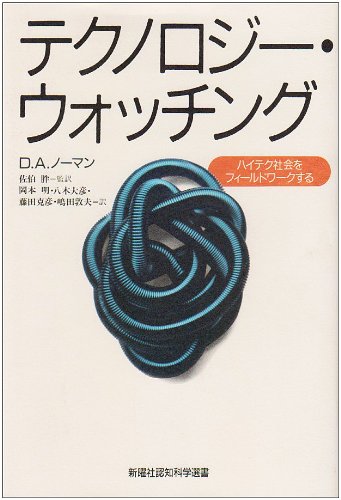まえがき
「ノーマンは使いやすい人工物を設計するために、以下のような設計の原則をあげている」
リスト
- アフォーダンス(affordance) ― 引いて開けるドアには、引きやすい取っ手をつける
- 対応づけ(mapping) ― どのスイッチを付ければどの照明が点くか、分かるようにする
- 可視性/フィードバック(visibility/feedback) ― 電話機は、ボタンを押したことを示すために音が出る
- 分散的認知(distributed cognition) ― 複数の人間が操作エラーをチェックできるようにする
- 制約(constraint) ― 誤った使い方ができないようにする
あとがき
『技術の哲学』より。ダッシュ(―)より右側は、本文の内容を汲んで、付け加えています。
分散的認知という項目がやや浮いているように感じます。実際、この設計原理が必要とされる例としては、飛行機のコックピットや化学プラントや原子力発電所が挙げられています。複数の人間が操作に関わるような道具のデザインを評価するとき以外は気にしなくてよいかもしれません。
ただし「複数の人間が」でなく「複数の箇所で」操作エラーをチェックできるようになっているかは、重要な場合があるかも。一連の操作のどこかで間違った場合、後続の操作のどこかでそれに気づけるようになっているか、とか。
まえがきのノーマンとは、認知心理学者のドナルド・A. ノーマン。『技術の哲学』では、このリストの参考文献としてノーマンの2冊の本を挙げています。
タイトル: 誰のためのデザイン?―認知科学者のデザイン原論 (新曜社認知科学選書)
著者: ノーマン,ドナルド・A.(著)、ノーマン,D.A.(著)、久雄, 野島(翻訳)
出版社: 新曜社
出版日: 1990-02-01
タイトル: テクノロジー・ウォッチング―ハイテク社会をフィールドワークする (新曜社認知科学選書)
著者: D.A. ノーマン(著)、岡本 明(翻訳)、藤田 克彦(翻訳)、佐伯 胖(翻訳)、八木 大彦(翻訳)、嶋田 敦夫(翻訳)
出版社: 新曜社
出版日: 1993-10-08