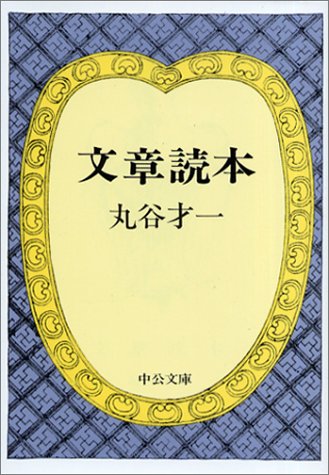まえがき
文章に色を添えるレトリックの数々。
リスト
- 隠喩(メタファー):AはBである
「人生は歩いてゐる影だ。哀れな役者だ」(『マクベス』) - 直喩(シミリー):AはBのやうだ
「仰せの通り、あれ〔雲〕はまさしく駱駝のやうでございます(『ハムレット』) - 擬人法(プロソポピーア):人間でないものを人間になぞらえる
「時間め、おれの恐ろしい功に先手を打ったな」(『マクベス』) - 迂言法(ペリフラシス):遠まわしに表現する
「桜草の花の小径を浮かれ歩く」(「快楽に耽る」の意)(『ハムレット』) - 代称(ケニング):迂言法の一種。何度も出てくるものや人を言い換える
「夜の蝋燭」(『ロミオとジュリエット』) - 頭韻(アリタレイション):語の最初の文字の発音を揃える
「きれいはきたない、きたないはきれい」(『マクベス』) - 畳語法(エピジュークシス):同音語を続けて強調する
「消えろ、消えろ、短い蝋燭!」(『マクベス』) - 首句反復(アナフォーラ):文首ないし句首に同一語句を繰り返す
「なぜ火の雨が降るのか、なぜ亡霊がうろつくのか」(『ジュリアス・シーザー』) - 結句反復(エピフォーラ):文尾に同じ語句を繰り返す
「ぼくが誰に贈ったのかあの指環を、誰のため贈ったのかあの指環を」(『ヴェニスの商人』) - 前辞反復(アナディプロシス):前の文中の最後の語ないし最も重要な語を次の文で繰り返す
「愚図でのろまの野呂助。野呂助のお供は…」(『リチャード三世』) - パリソン:同じ構造の節や句を続けざまに用いる
- イソコロン:同じ長さの節の連続
- 対句(アンティセシス):同じ構造の2つの句を続けて用いる
- 連辞省略(アシンデトン):節や句を接続詞ぬきでつなぐ
- 羅列:読んで字のごとく
- 誇張法(ハイパーボリ):大げさに言う
「白髪三千丈」(『秋浦歌』) - 緩叙法(マイオウシス):控えめに言う
- 曲言法(ライトウティーズ):反対語を否定して強い肯定を表す
- 修辞的疑問(レトリカルクエスチョン):いわゆる反語
- 換喩(メトニミー):事物を、その属性や密接な関係のあるもので言い換える
「白髪」で老年を指す - 撞着語法(オクシモロン):矛盾し対立する語を結びつける
「有難迷惑」 - 声喩、擬声音、擬態音(オトマノピーア):声・動作などを音声で表現する
あとがき
丸谷才一『文章読本』より。一行目のコロンの右側の説明は、本文からの引用・要約です。また本に出ているレトリックの完全な引用ではありません。