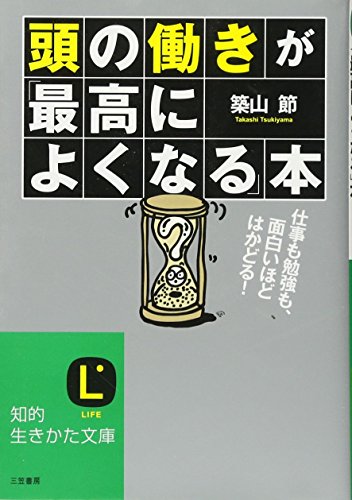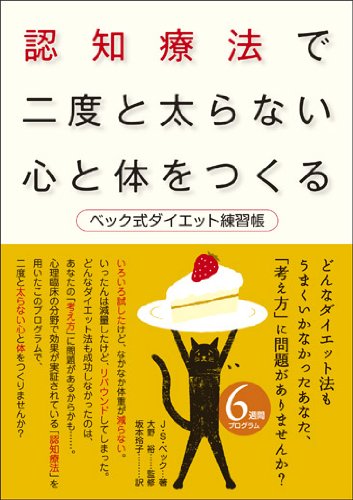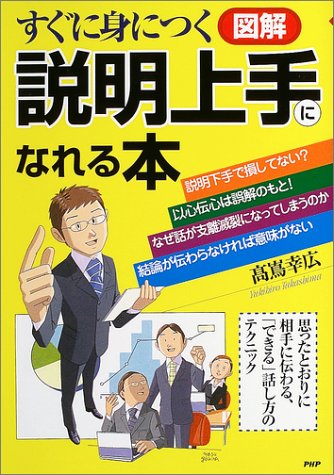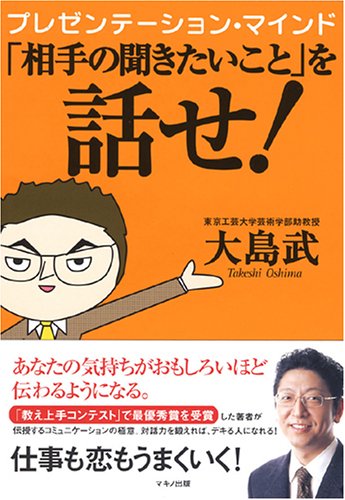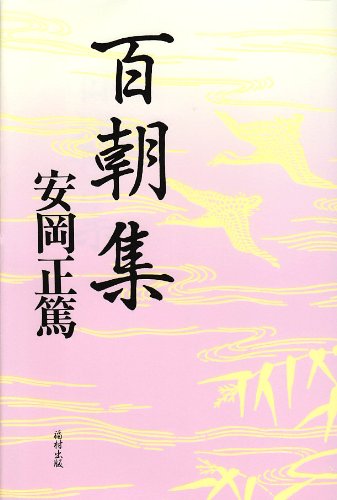まえがき
『「7つの健康習慣」は米国のブレスロー教授が生活習慣と身体的健康度との関係を調査した結果から広く知られるようになりました。』
リスト
- 喫煙をしない
- 定期的に運動をする
- 飲酒は適量を守るか、しない
- 1日7-8時間の睡眠を
- 適正体重を維持する
- 朝食を食べる
- 間食をしない
あとがき
まえがきを含めて「ブレスローの7つの健康習慣を実践してみませんか?」(e-ヘルスネット)より。厚生労働省のサイトです。
中学校のテストに出たという話を聞いて、検索してみました。『上記の7つの健康習慣の実践の有無によって、その後の寿命に影響することが分かっている』とのこと。
ふーむ。「影響する」という表現が微妙ですね。健康習慣の実践と寿命の間に因果関係があることを証明するのはなかなか大変そうに思えます。時間のあるときにソースを読んでみたい。
あと、飲酒は「適量」、体重は「適正」なのに、睡眠だけ「7-8時間」とビシッと指定があるのがちょっと不思議。適正な睡眠時間は7-8時間なのでしたっけ。