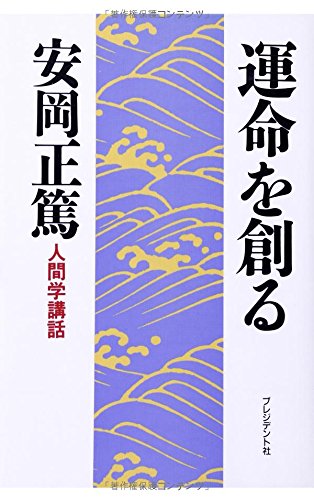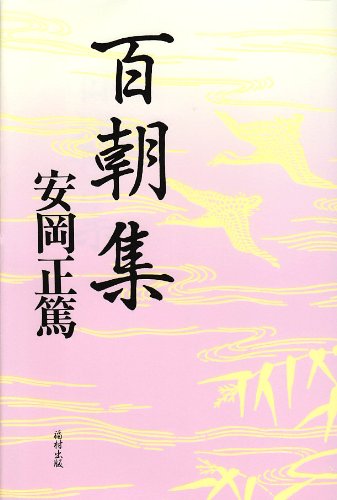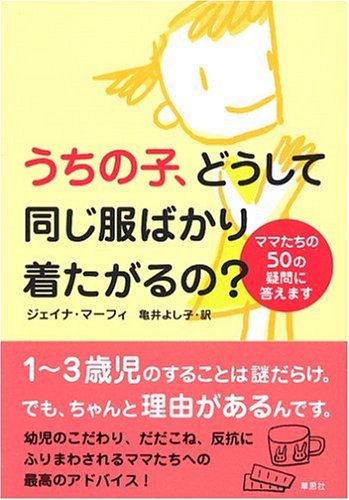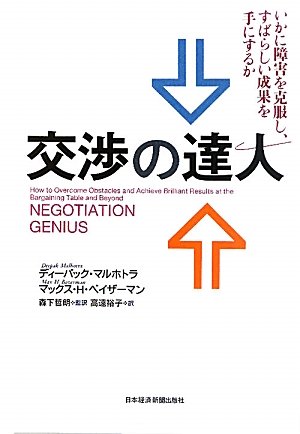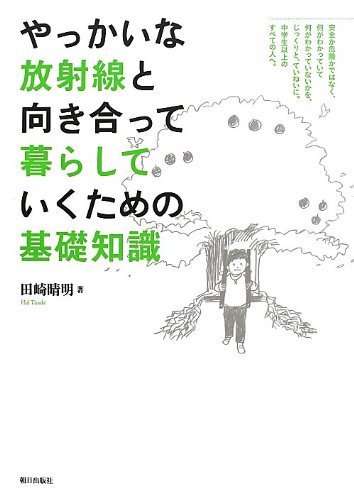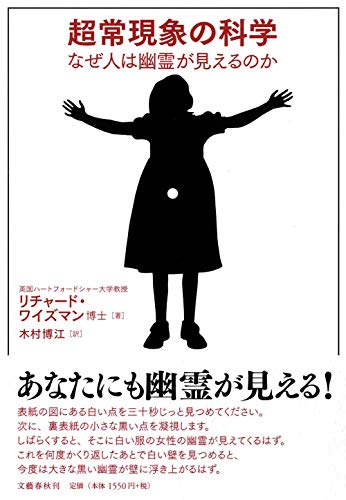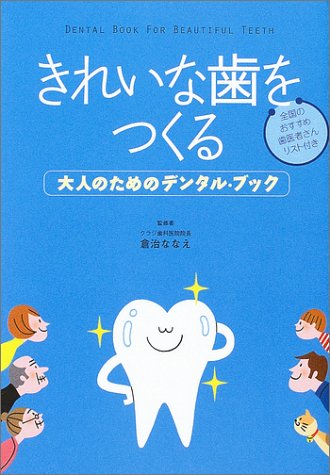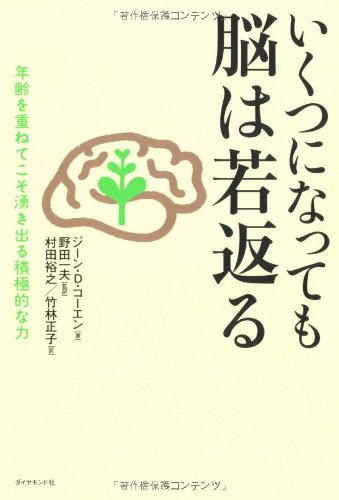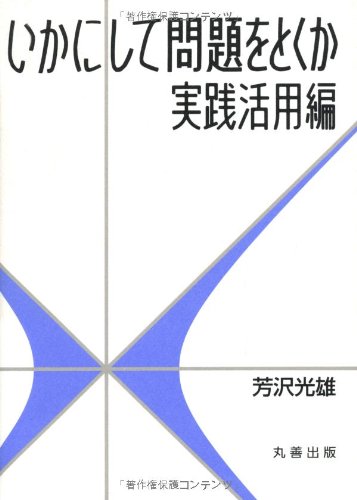まえがき
『私はこの「六然」を知って以来、少しでもそうした境地に心身を置きたいものと考えて、それとなく忘れぬように心がけてまいりましたが、実に良い言葉です。まことに平明でしかも我々の日常生活に即して活きています。』
リスト
- 自処超然 … 自ら処すること超(ちょう)然。自分自身に関してはとらわれないように。
- 処人藹然 … 人に処すること藹(あい)然。人に接するには穏やか・和やかに。
- 有事斬然 … 有事には斬(ざん)然。事があるときは愚図愚図しないで活き活きと。
- 無事澄然 … 無事には澄(ちょう)然。事なきときは水のように澄んだ気で。
- 得意澹然 … 得意には澹(たん)然。澹は淡と同じ。得意のときはあっさりと。
- 失意泰然 … 失意には泰(たい)然。失意のときは泰然自若。
あとがき
まえがきを含めて『運命を創る』より。六然は「りくぜん」と読みます。六然訓とも。「…」以降の解説は本文からの編集・引用です。処人藹然の解説だけ、すこし自分の言葉で書き換えました。2項目ずつ3つのペアになっていて覚えやすいですね。
もともとは明の時代を生きた崔銑(さいせん)という人の言葉とのこと。
- タイトル: 人間学講話第1集 運命を創る (安岡正篤人間学講話)
- 著者: 正篤, 安岡(著)
- 出版社: プレジデント社
- 出版日: 1985-12-10