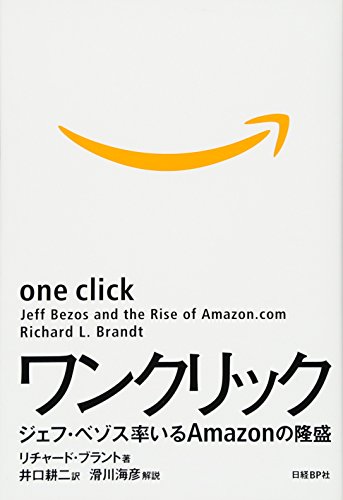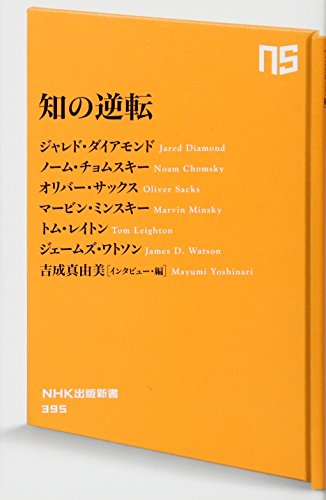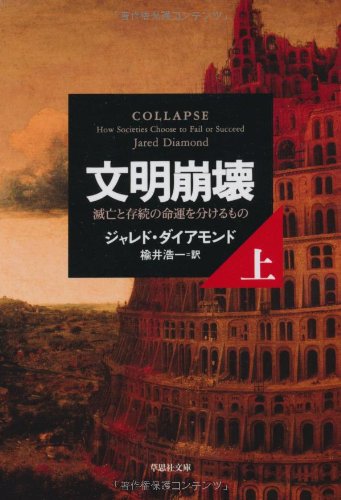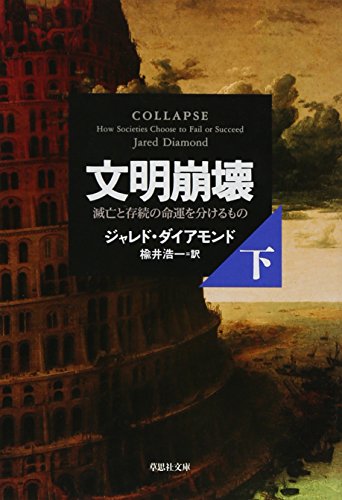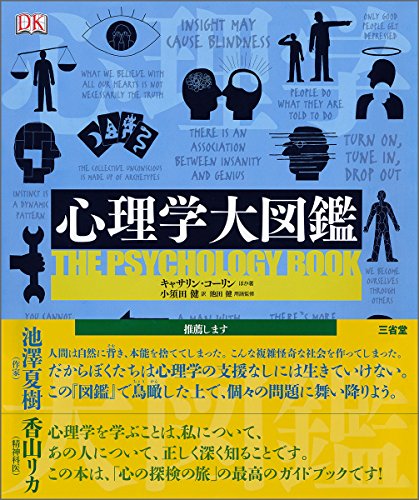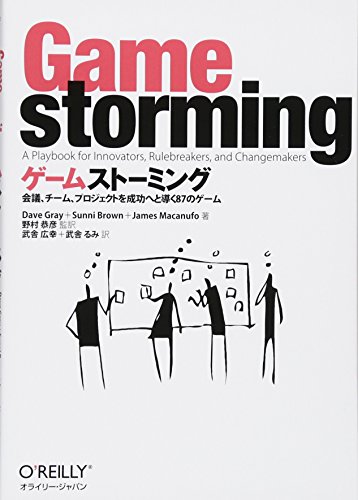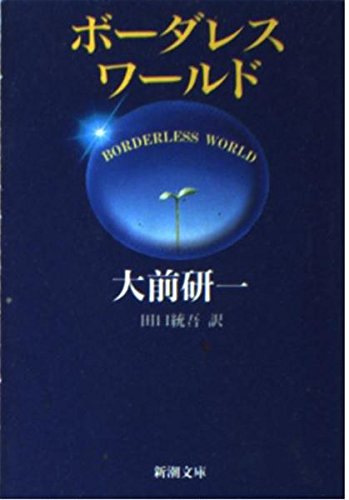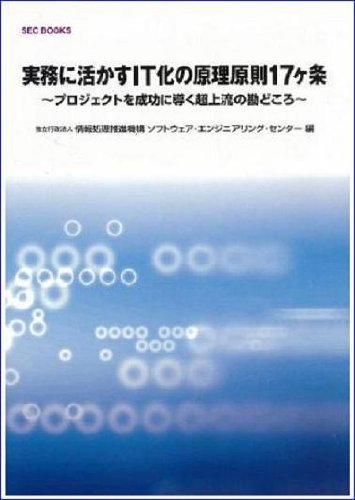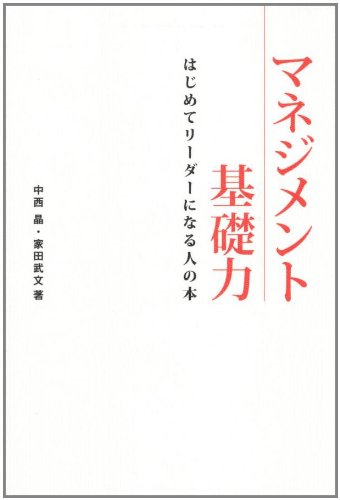まえがき
『これら4つの哲学はいずれも、とても明快なルールだ。ベゾスの経営哲学について驚くようなことがあるとすれば、それは、世の中の経営者でこの哲学を実践できる人がほとんどいないらしいという点である。』
リスト
- 徹底的な顧客第一主義
- きちんとしたものができるまで、発明、再発明をねばり強く続ける
- 長期的に考える
- 「毎日が初日」
あとがき
まえがきを含めて『ワンクリック―ジェフ・ベゾス率いるAmazonの隆盛』より。最終章の本文をリスト化のうえ引用しました。
いいなと感じたのは「毎日が初日」という言葉。日本語には初心という素晴らしい言葉がありますが、同じような意味で使っているのかな。”jeff bezos management philosophy”などで検索してみたのですが、この4か条が経営哲学だという情報源は見当たらず。
- タイトル: ワンクリック ジェフ・ベゾス率いるAMAZONの隆盛
- 著者: リチャード・ブラント(著)、滑川海彦 (解説)(その他)、井口 耕二(翻訳)
- 出版社: 日経BP
- 出版日: 2012-10-18