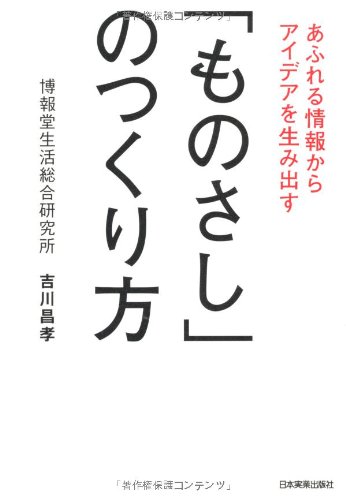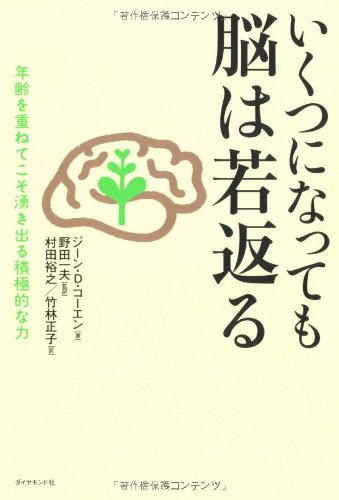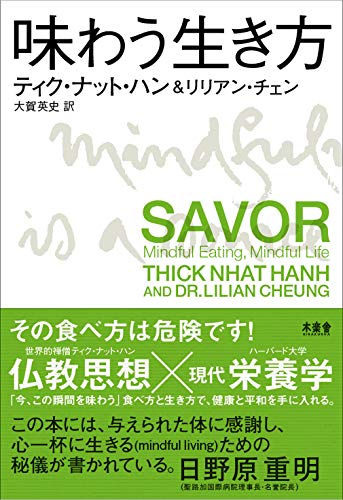まえがき
『これら三つの思考力は、積み重ねた人生経験、感情面での発達、そして年齢の積み重ねで脳に生じる肯定的変化がオモテに現われたものであり、「成熟した思考力」なのです。』
リスト
- 相対主義的思考 ― “唯一絶対”を追わない
- 弁証法的思考 ― 相反矛盾を“止揚”する
- 体系的思考 ― “関係・過程”に意義がある
あとがき
まえがきを含めて、村田 裕之『40歳から活きる!「オトナの脳力」』(月刊ビジネスデータ 2009年5月号、日本実業出版社)より。
この3つは「ポストフォーマル思考」の特徴として次のように紹介されていました。
『ポストフォーマル思考は、私たちが成長し、学習し、経験を重ねるなかで認知発達した結果、身につく「論理的思考」ではない認知力で、次の三つの思考法で特徴づけられます。』
ポストフォーマルということはフォーマル思考があるわけです。記事にはこう書かれています。
『現代心理学の分野に「フォーマル思考(formal thought)」という言葉があります。フォーマル思考とは、問題を解決しようとするときに純粋に論理を突きつめる思考法で、最近よく耳にする「論理的思考」とほぼ同じ意味です。』
現代心理学の分野に「フォーマル思考」があるのかどうか調べてみました。フォーマル思考あるいはformal thoughtではほとんど情報が取れなかったのですが、やがてこのformalは、ジャン・ピアジェの思考発達段階説(Piaget’s theory of cognitive development – Wikipedia)における形式的操作期(Formal operational stage – Wikipedia)のformalを指していることが分かりました。形式的操作期は12歳以降に到達する思考発達の最終段階です。ポストフォーマル思考はこの次の段階ということですね。
リストの3か条の引用元も調べたかったのですが見つからず。やや似た文章はありました。
…it is possible to identify in the diverse descriptions of postformal thought (cf. Kramer, 1983, 1989) some features which would be specific to this level: (1) the recognition and understanding of the relativistic, non-absolutist, nature of knowledge; (2) the acceptance of contradiction to the extent that it is part of reality; and (3) the integration of contradiction into comprehensive systems, i.e., into a dialectical whole (Kramer, 1989).
— Helena Marchand. (2001). Some Reflections On PostFormal Thought. [The Genetic Epistemologist, Vol29(3)
その後、記事の著者が訳した『いくつになっても脳は若返る』を読んだところ、これら3つの思考が「発達性知能」として詳しく紹介されていました。しかし本の中ではリストのような端的な言葉ではまとまっていなかったので、このままこちらを採用します。
- タイトル: いくつになっても脳は若返る
- 著者: ジーン・コーエン(著)、野田 一夫(監修)、村田 裕之(翻訳)、竹林 正子(翻訳)
- 出版社: ダイヤモンド社
- 出版日: 2006-10-20
この本からの他のリスト