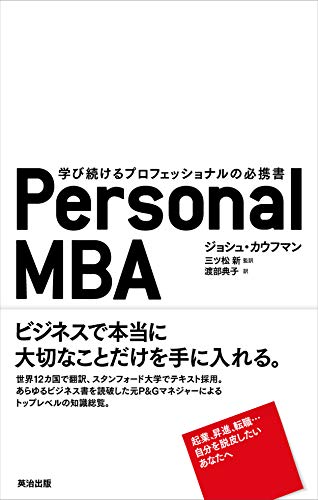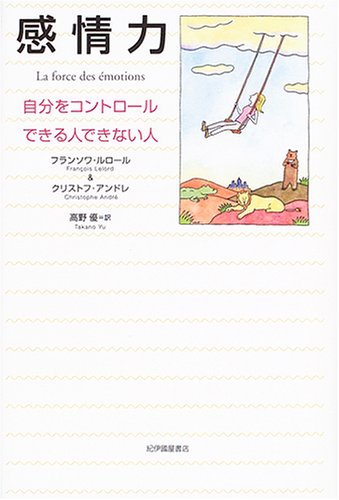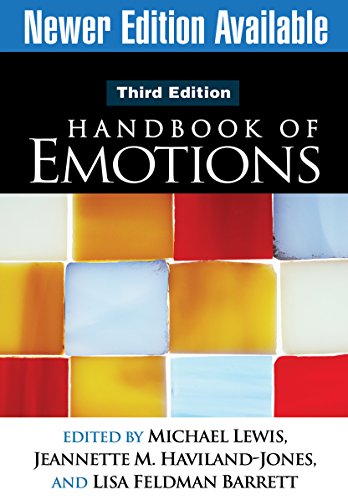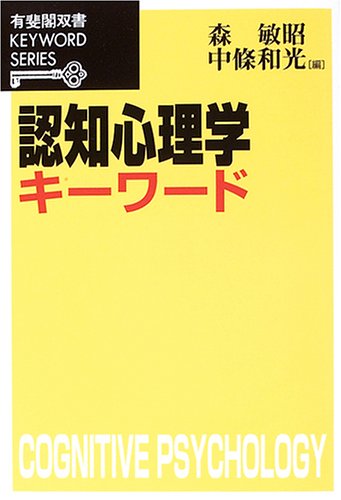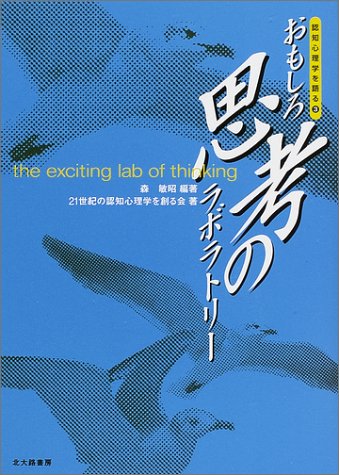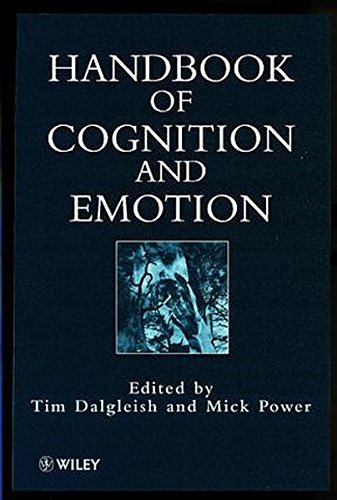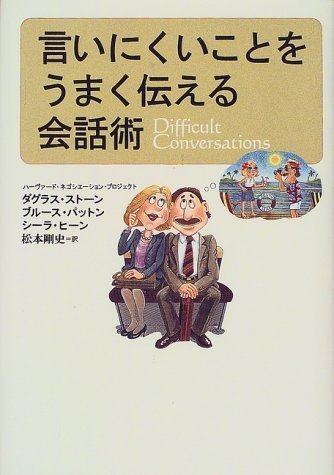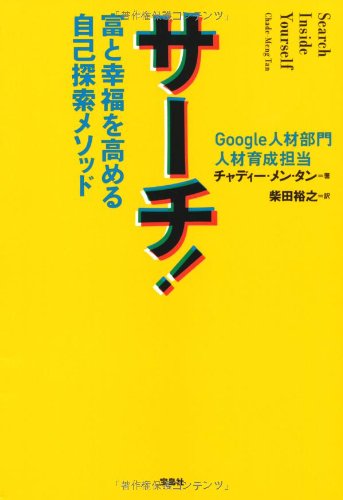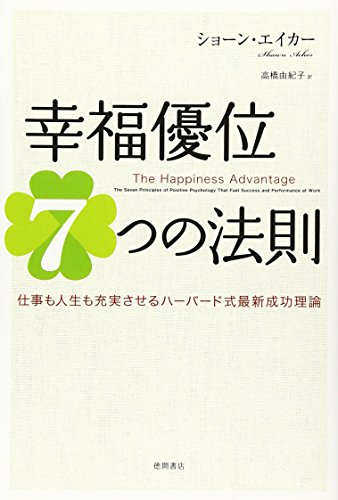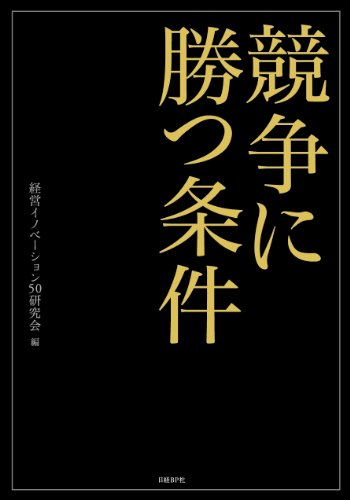まえがき
『本書は、できるだけ迅速かつ効率的に、理にかなったビジネス慣行の基礎を教えることを意図している。学ぶ内容をおおまかに挙げてみよう。』
リスト
- 【価値創造】 人々が必要としたり、欲しがったりするものを見つけ、それを創り出す。
- 【マーケティング】 自分が創出したものに注意を喚起し、需要を高める。
- 【販売】 潜在顧客を、実際にお金を払ってくれる顧客へと変える。
- 【価値提供】 約束したものを顧客に提供し、確実に顧客を満足させる。
- 【ファイナンス】 ビジネスを続け、努力が報いられるだけのお金を生み出す。
- 【人々の心を理解する】 人々がどう感じ・考え・行動するかを理解し、事業に生かす。
- 【自分と上手につきあう】 効果的かつ効率的に働く。
- 【他の人々とうまく協業する】 顧客、従業員、請負業者などと効果的に協業する。
- 【システムを理解する】 ビジネスをシステムとして理解する。
- 【システムを分析する】 システムを要素に分解・測定し、構造的にとらえる。
- 【システムを改善する】 システムを最適化し、不確実性と変化に対処していく。
あとがき
まえがきを含めて『Personal MBA――学び続けるプロフェッショナルの必携書』より。【】の部分は本書の目次(第2章から第12章まで)です。1~5は著者が「ビジネスの五つの構成要素」と呼ぶもので、本文から引用しています。6以降は、本書からママ引用できるミニ定義がなかったので、できるだけ短い要約を添えました。
項目数が多いせいもあり、パッと見ると分かりづらいですが、著者は、リスト(つまり本書の章立て)をさらに3つにくくっています。これで意図がよく分かるかと。
・ビジネスの仕組み(1~5)
・人々の働き方(6~8)
・システムの仕組み(9~11)
- タイトル: Personal MBA――学び続けるプロフェッショナルの必携書
- 著者: ジョシュ カウフマン(著)、三ツ松 新(監修)、三ツ松 新(監修)、渡部 典子(翻訳)
- 出版社: 英治出版
- 出版日: 2012-08-10