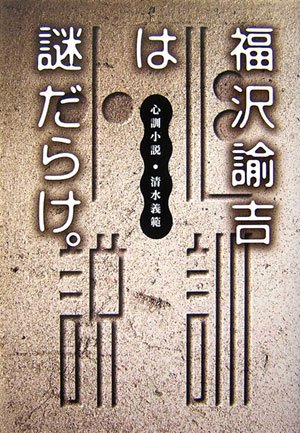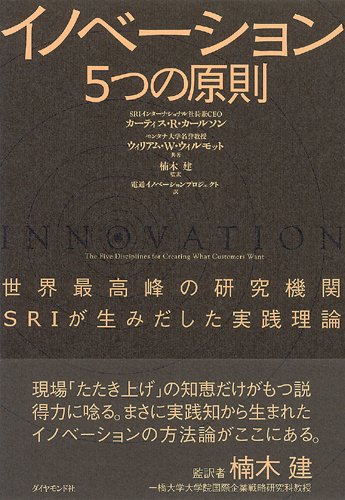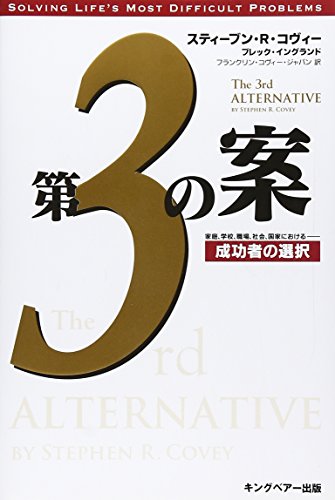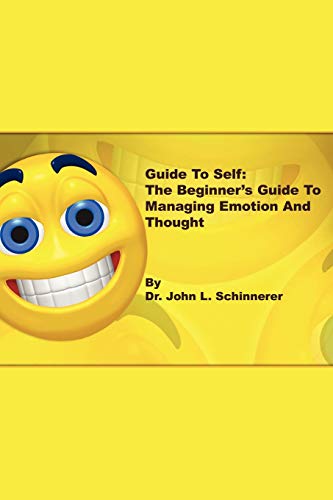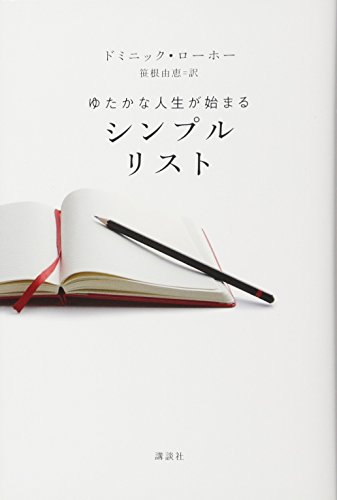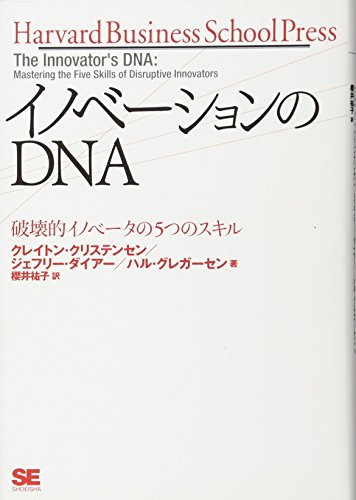まえがき
日常五訓とも。
リスト
- はいという素直な心
- すみませんという反省の心
- おかげさまという謙虚な心
- 私がしますという奉仕の心
- ありがとうという感謝の心
あとがき
日常の五心 – Wikisource より。そのWikisourceは『福沢諭吉は謎だらけ。心訓小説』を引用元として挙げています。
カッコなど一部の記号を外したうえで引用しています。
何かの雑誌で、柔道家の小川直也(Wikipedia)氏のインタビューを読んだところ、氏の道場に「日常五心」が掲げられているとありました。
検索してみると、武道系の道場でこれを唱えているところが多いようですね。
五つでは多いとすると、後半の三つだけでいいかな。