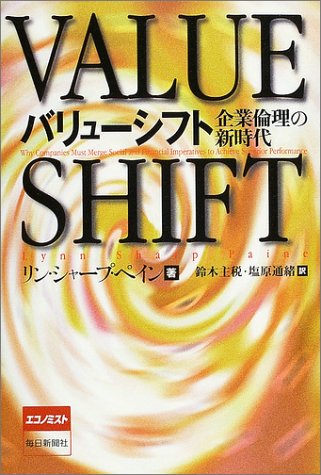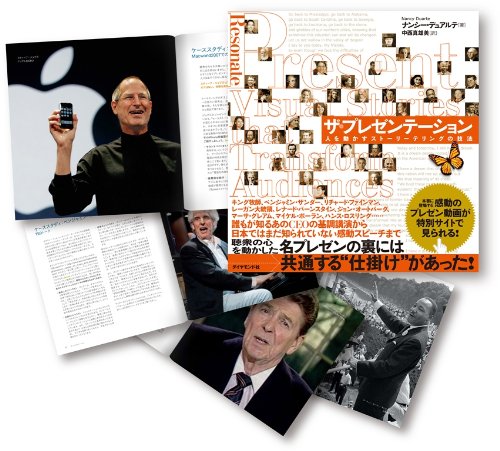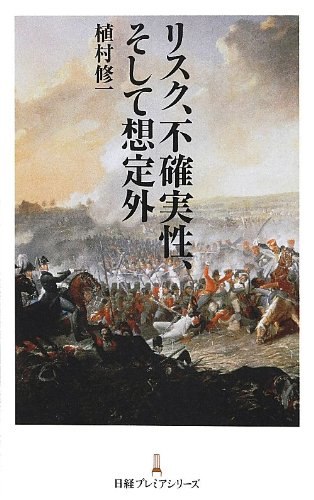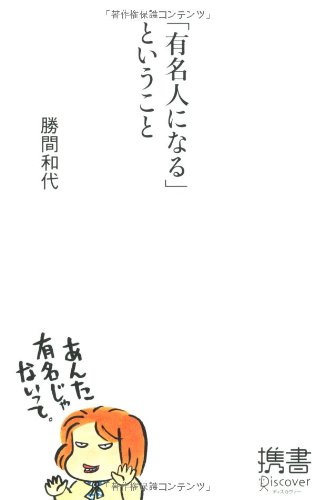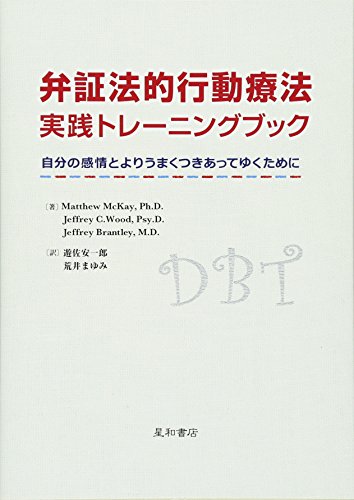まえがき
倫理的であるとは「何について」「どうする」ことなのか。
「正義/人間性」についての「基本的な/完全をめざした」行動のリスト。
リスト
- ●正義についての倫理的な行動(基本 ― 完全)
- ・間違ったことをしない ― 正しいことをする
- ・契約を全うする ― 約束を守る
- ・盗みをしない ― 公正でいる
- ・詐欺行為をしない ― 正直でいる
- ・法の文言にしたがう ― 法の精神にしたがう
- ●人間性についての倫理的な行動(基本 ― 完全)
- ・自己を維持する ― 自己を成長させる
- ・他人を傷つけない ― 積極的に他人を助ける
- ・人間の権利を尊重する ― 人間の尊厳を奨励する
- ・社会にとって有害なことをしない ― 社会の改善に貢献する
- ・思いやりを持つ ― 勇気を持つ
あとがき
『バリューシフト―企業倫理の新時代』より編集・引用。
- タイトル: バリューシフト―企業倫理の新時代
- 著者: リン・シャープ ペイン(著)、Paine,Lynn Sharp(原著)、主税, 鈴木(翻訳)、通緒, 塩原(翻訳)
- 出版社: 毎日新聞社
- 出版日: 2004-04-01
この本からの他のリスト
参考文献
倫理の広さと深さ – 起-動線