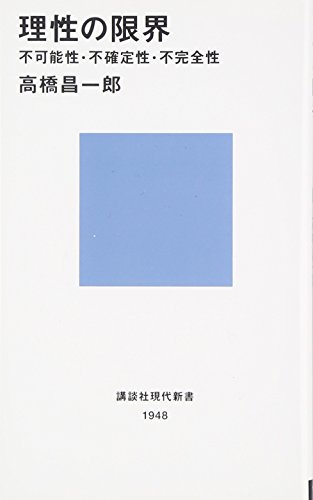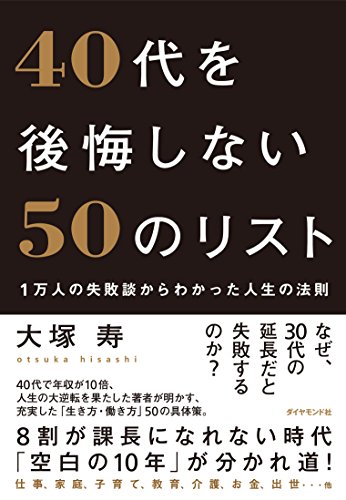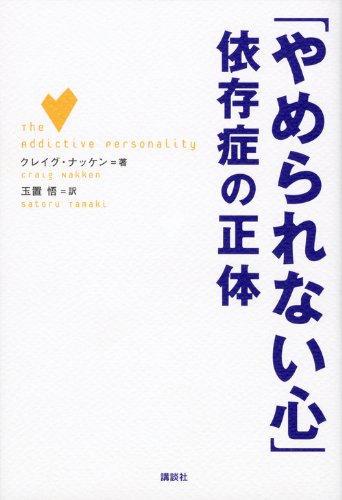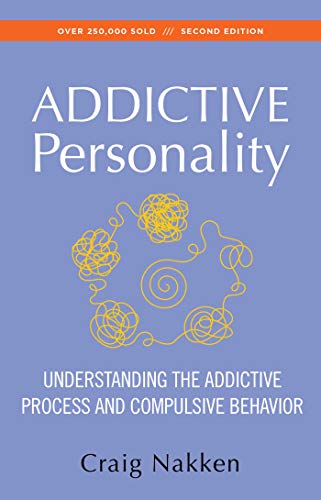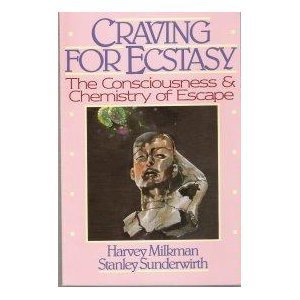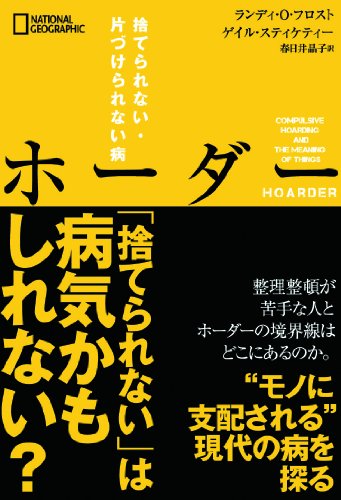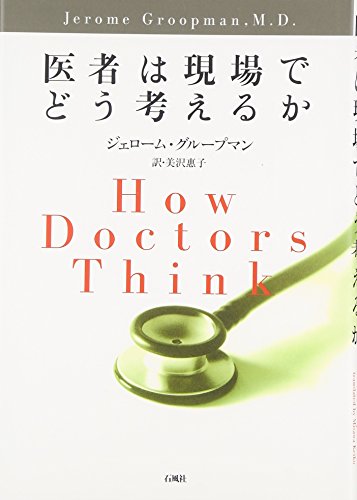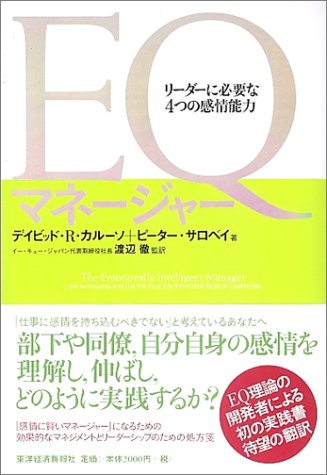まえがき
『定年退職した人のほとんどの後悔が、四〇代にあるというのも顕著でした。』
リスト
- 「自分にとって大切なこと」を優先できなかった
- わかっていても結局「守り」に入ってしまった
- 「二元論」で考えなければよかった
- 「仕事」と「家庭」のバランスが取れなかった
- 未来の成功より「今日一日」を大切にすればよかった
- 負けない「絶対的な自信」が欲しかった
- 誰にも負けない「強み」がつくれなかった
- 「スピード決断」ができなかった
- 社内外で「本当に頼りになる人脈」を築いておけばよかった
- 「自分の特性」をもっと意識しておけばよかった
- 会社が自分に「何を求めているのか」をもっと意識すればよかった
- 仕事に追われて「すべきこと」ばかりやっていた
- 「どこまで目指すか」を考えるべきだった
- 自分が「何を成し遂げたか」がわからなくなった
- 「他人を動かすスキル」が身につかなかった
- 負けない「交渉力」が欲しかった
- 「伝える力」が足りなかった
- 「意思決定」が苦手だった
- 「スピード」をもっと重視するべきだった
- 「対人音痴」が直らなかった
- もっと「時間の使い方」を工夫すればよかった
- 「週末時間」を有効に使えなかった
- もっと「家族との時間」に気を遣えばよかった
- 「相手に合わせて」飲みに行かなければよかった
- 「付き合いのいい人」である必要などなかった
- 「優先順位」を間違ってしまった
- 忙しいなりに「細かい時間」の使い方を工夫すればよかった
- 「やりたいこと」にチャレンジできなかった
- 利害を超えた「人付き合い」を軽視してしまった
- 頼まれたときに「上司として」応えられなかった
- 「年下との人間関係」を大切にすべきだった
- 「コミュニケーション下手」を克服したかった
- 「話し方」で損をした
- 「言葉」ではなかなか伝わらなかった
- 「会社以外の居場所」を見つけておくべきだった
- 自分自身を「振り返る時間」を持つべきだった
- もっと「仕事に役立つ本」を読めばよかった
- 時間がなくてなかなか「本」が読めなかった
- 「読書の効用」をもっと活かせばよかった
- 「教養」を深めておけばよかった
- 年相応の「お金の使い方」を考えればよかった
- 「介護」について準備しておけばよかった
- 「自分の世界が広がる趣味」を始めておけばよかった
- 「親業」にもっと積極的に取り組めばよかった
- 「上司の能力」を積算しておくべきだった
- 「会社の価値観」を見極めるべきだった
- やはり「出世」したかった
- 人事を「感情的に判断」すべきではなかった
- サラリー以外の「生活の糧」を持つべきだった
- もっと「地域社会」と付き合えばよかった
あとがき
まえがきを含めて『40代を後悔しない50のリスト 1万人の失敗談からわかった人生の法則』より。リスト項目は出版社(ダイヤモンド社)の書籍紹介ページからの引用です。ただし、なぜか7番が欠落していたので、それは書籍の目次から引用しました。
もちろん本書では、後悔をリストアップするだけではなく、それぞれについての処方箋がセットになっています。その一行要約も書籍紹介ページからチェックできます。
著者は『私はその一万人以上の方から、「後悔しない生き方」の具体的な方法を学びました。』と述べています。具体的には営業の仕事を通じてお会いした方々に話を聞きまくったそうです。
本文の序章から、ヒアリングの対象は「日本人」で、かつ「企業人」であることがうかがえます(その情報はタイトルに盛り込みました)。時代的に、また経営者・経営幹部が多かったことが強調されてもいるので、大部分は「男性」と考えてよいでしょう。
世代的にはどんな人たちか。1962年生まれの著者が28歳のとき(1990年)からヒアリングを開始したとすると、その年に60歳(当時の大手企業の退職年齢)だった人は1930年生まれです。このあたりが最高齢の層。最も若い人は、本書が書かれた2010年(出版が2011年1月なので)に50歳の人ですから、1960年生まれ。ざっくり言って昭和ひと桁~昭和35年生まれ、あるいは「団塊の世代プラスマイナス15歳くらい」でしょうか。
団塊の世代が突出して数が多いこと、その世代はもとより企業人が多いであろうことを踏まえ、上記を思い切って要約すると、このリストは「団塊世代の男性が40代を振り返って後悔していること50」という感じなのかな。
……にしても(上記の仮定が合っているとすると)20年で1万人から学んだってすごい。1万[人]を20[年]×200[年/日](←仕事を通じてということなので)で割ると、2.5[人/日]!しかもオーバー50歳限定ですからね。話半分(失礼)にしてもすごい。