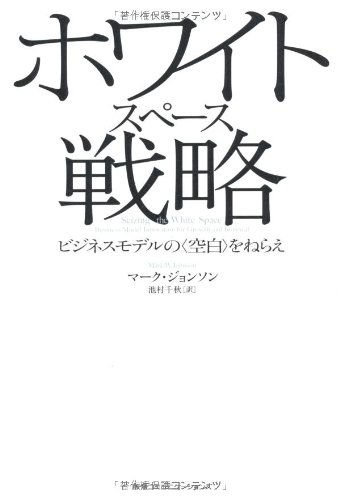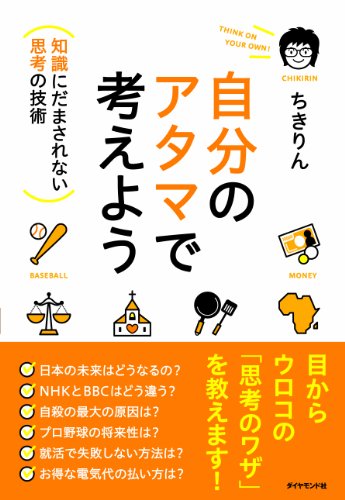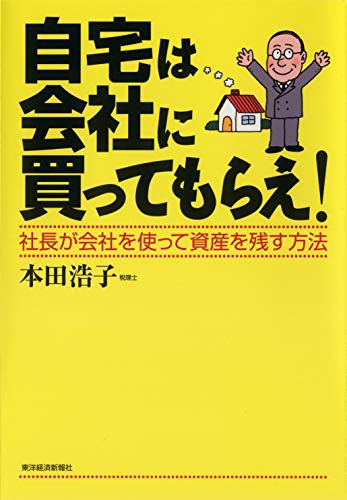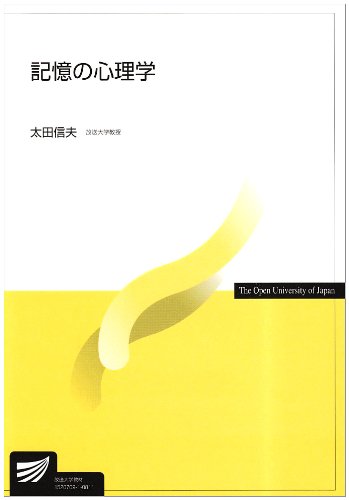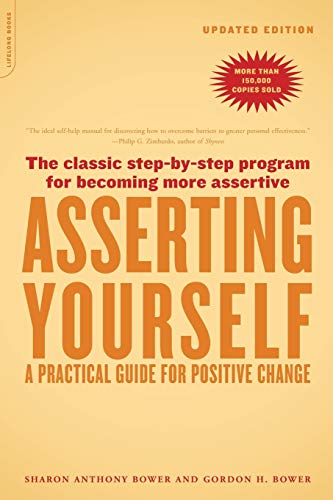まえがき
市場の成熟に従い、顧客の判断基準はどう推移するか。
リスト
- 【機能性】 初期の市場では、商品やサービスには機能性が求められる〈商品のイノベーション〉
- 【信頼性】 機能性が満たされると、品質と信頼性が求められる〈業務プロセスのイノベーション〉
- 【利便性】 機能性と信頼性が満たされると、利便性とカスタマイズ性が求められる〈ビジネスモデル・イノベーション〉
- 【価格】 機能性・信頼性・利便性が満たされると、市場はコモディティ化し、競争は価格面に絞られる〈ビジネスモデル・イノベーション〉
あとがき
『ホワイトスペース戦略 ビジネスモデルの<空白>をねらえ』より。項目名の次の説明文は、引用者側で作文しました。〈○○イノベーション〉の部分は、それぞれのステージでの競争に勝つために求められるイノベーションの種類です。
これはとても分かりやすく、かつ頷けるリストではないでしょうか。
『競争の基準が利便性や価格に移ると、顧客が解決したいジョブは根本から変わる。それにともなって、企業が打ち出すべき顧客価値提案の中身も当然変わる。企業が既存のビジネスモデルの限界にぶち当たる場合が最も多いのは、この段階だ。』
- タイトル: ホワイトスペース戦略 ビジネスモデルの<空白>をねらえ
- 著者: マーク・ジョンソン(著)、Mark W. Johnson(著)、池村千秋(翻訳)
- 出版社: CCCメディアハウス
- 出版日: 2011-03-29