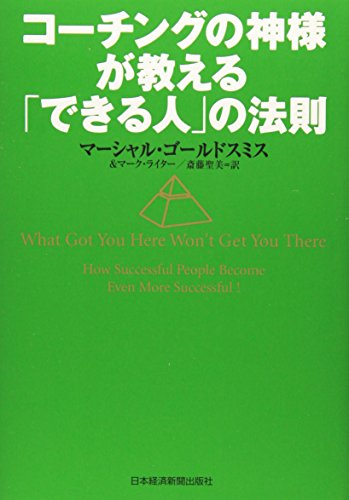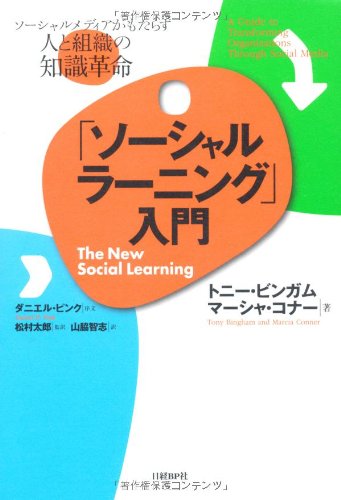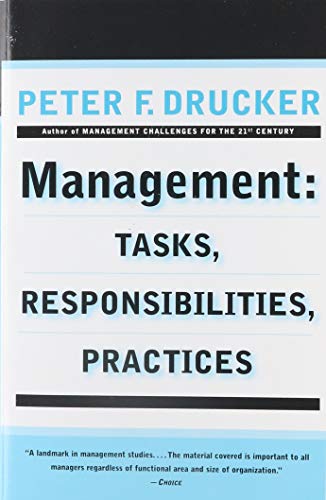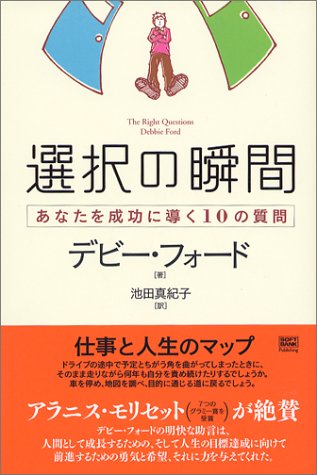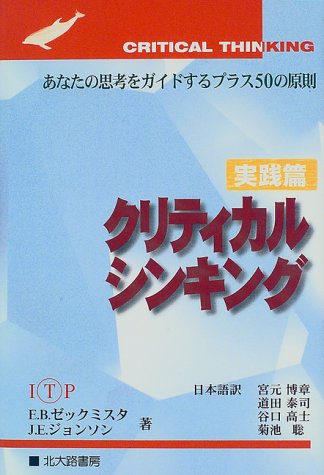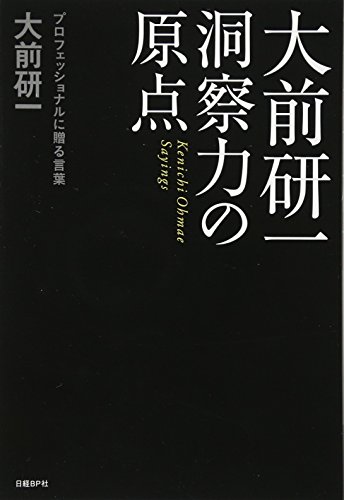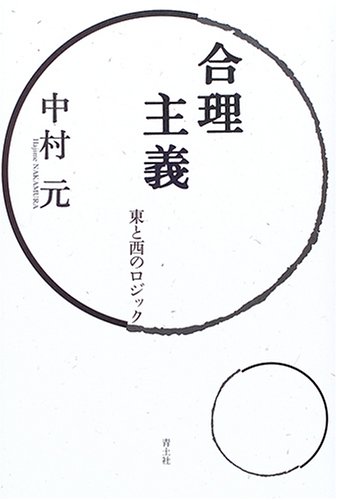まえがき
『(このリストは)対人関係の行動、とくにリーダーシップの行動にかかわる問題点だ。不必要に職場を著しく不愉快な場所にしてしまう、日々の許しがたい、いやな行動だ。それは一人でいるときには起こらない。一人の人が他の人に対して何かをするときに出てくる「悪い癖」だ。』
リスト
- 極度の負けず嫌い。何を犠牲にしても、どんな状況でも、まったく重要でない場合でも、勝ちたいと思う気持ち。
- 何かひとこと価値をつけ加えようとする。どんなことにでもちょっと口出ししたいという強い欲望。
- 善し悪しの判断をくだす。他人を評価して、自分の基準を他人に押しつけようとする気持ち。
- 人を傷つける破壊的コメントをする。不要な皮肉や痛烈なコメントをする。そうすれば自分が切れ者で機知のある人に見えると思う。
- 「いや」「しかし」「でも」で文章を始める。これらの否定的・限定的な言葉を使いすぎる。ひそかに「私が正しいんだ。あなたは間違っている」と言っているようなものだ。
- 自分がいかに賢いかを話す。他人が考える以上に私は賢いんだと見せたい欲望。
- 腹を立てているときに話す。感情的な興奮を経営ツールとして利用する。
- 否定、もしくは「うまくいくわけないよ。その理由はね」と言う。頼まれもしないのに否定的な考え方を他人に吹きこもうとする。
- 情報を教えない。優位な立場を保つために、情報を他人と共有しようとしない。
- きちんと他人を認めない。賞賛し褒賞を与えることができない。
- 他人の手柄を横どりする。成功に対する自分の貢献度を過大評価するいちばんいやな手口。
- 言い訳をする。不愉快な行動を、変えることのできない生まれつきのものとして片づけ、他人がしかたないと思うようにさせる。
- 過去にしがみつく。自分の責任を過去の出来事や人のせいにする。自分以外の人すべてのせいにすることの一例。
- えこひいきする。誰かを不公平に扱っていることに気づかない。
- すまなかったという気持ちを表わさない。自分の行動に責任をとらない。間違いを認めない。自分の行動が他人にどう影響したかを認めることができない。
- 人の話を聞かない。職場の人に対して敬意を払わない、もっとも受動攻撃的な形。
- 感謝の気持ちを表わさない。非常に基本的な悪いマナー。
- 八つ当たりする。たんに手助けしようとする罪のない人を攻撃したいという誤った欲望。
- 責任回避する。自分以外の人みんなを責める。
- 「私はこうなんだ」と言いすぎる。自分の欠点をまるで長所のようにほめそやす。それが自分なんだと主張する。
あとがき
まえがきを含めて『コーチングの神様が教える「できる人」の法則』より引用。3年ほど前に読んだときにはこのリストを載せなかったのですが、再読して、やはり載せたいなと感じました。
著者の長年の経験から引き出された悪癖の数々。その多くは、1の「勝ちたい」という気持ちから来ていると洞察しています。
- タイトル: コーチングの神様が教える「できる人」の法則
- 著者: ゴールドスミス,マーシャル(著)、ライター,マーク(著)、Goldsmith,Marshall(原著)、Reiter,Mark(原著)、聖美, 斎藤(翻訳)
- 出版社: 日本経済新聞出版
- 出版日: 2007-10-01