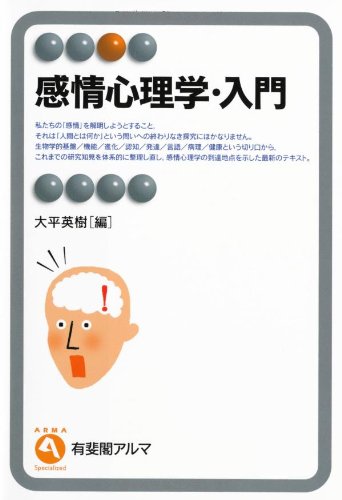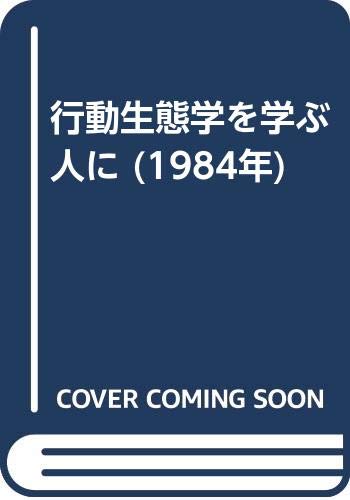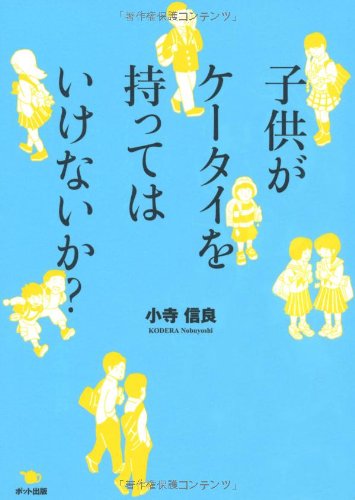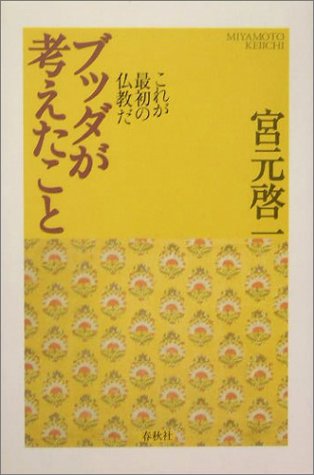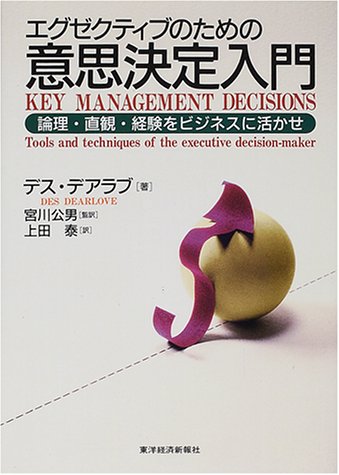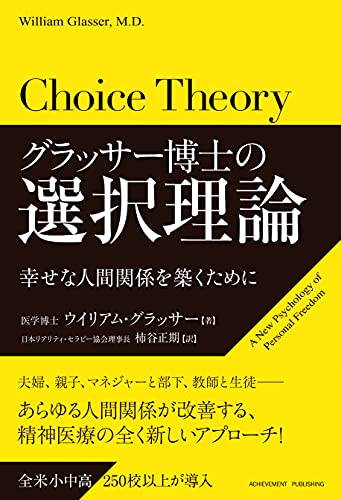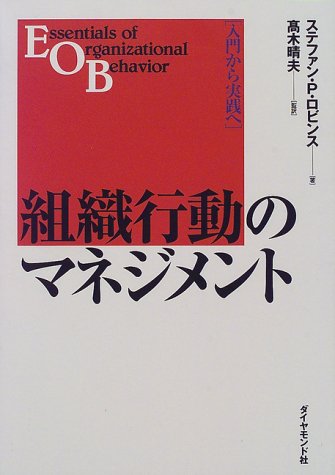まえがき
『ダーウィン(Darwin、1859)の提唱した進化論(略)の骨格は、変異、遺伝、競争、選択、そして結果としての適応にまとめられる(略)。』
リスト
- 【変異】 同種に属する動物においても、個体間には形質(形態や生理反応や行動など)にさまざまな違いがある。
- 【遺伝】 変異の一部はDNAを通じて子孫へと伝えられる。
- 【競争】 繁殖に必要なさまざまな資源(生育に必要な空間、環境中の食料、配偶のパートナーなど)には限りがあるため、実際に子孫を残せる個体は限られる。
- 【選択(淘汰)】そこで、最終的に子孫を多く残せる個体と残せない個体が生じる。
- 【適応】 この事態が続けば、繁殖できる確率が高い形質を発現させる遺伝子が個体群内に広まっていく。このプロセスが結果として、生物を特定の環境に適した形質に変化させていく。
あとがき
まえがきを含めて『感情心理学・入門』より。ダーウィンの進化論がキーワードとともにコンパクトにまとめられていて分かりやすかった。とはいえ引用元では1ページ近い文章になっているので、リスト化するために本文を大幅に刈り込んだうえで整形・引用しています。大意を損ねないよう要約したつもりではありますが、分かりづらいところがあったら引用者の責任ですので、まずは本書にあたってくださいね。
もっとも、この本自体は感情心理学の本。引用部分の参考文献として『行動生態学を学ぶ人に』が挙げられていましたので、こちらも併せて紹介しておきます。
- タイトル: 感情心理学・入門 (有斐閣アルマ)
- 著者: 大平 英樹(編集)
- 出版社: 有斐閣
- 出版日: 2010-12-18
この本からの他のリスト
- タイトル: 行動生態学を学ぶ人に (1984年)
- 著者: 城田 安幸(著)、N.B.デイビス(著)、J. R. クレブス(著)
- 出版社:
- 出版日: 1970-01-01