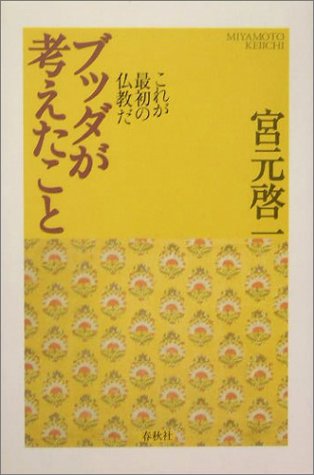まえがき
『仏教の認識論では知覚が決定的に重視されるが、知覚という認識を構成する基盤、要素を、それぞれ十二処(六入と六境)、十八界(六入と六境と六識)として立てる。』
リスト
- 【六入(感官) ―― 六境(対象) ―― 六識(知覚)】
- 眼〈げん〉(視覚器官) ―― 色〈しき〉(色かたち) ―― 眼識(視覚)
- 耳〈に〉(聴覚器官) ―― 声〈しょう〉(音声) ―― 耳識(聴覚)
- 鼻〈び〉(嗅覚器官) ―― 香〈こう〉 ―― 鼻識(嗅覚)
- 舌〈ぜつ〉(味覚器官) ―― 味〈み〉 ―― 舌識(味覚)
- 身〈しん〉(触覚器官) ―― 触〈そく〉(冷熱など) ―― 身識(触覚)
- 意〈い〉(思考器官) ―― 法(思考の対象) ―― 意識(内覚)
あとがき
まえがきを含めて『ブッダが考えたこと―これが最初の仏教だ』より。一部の読みがなやフォーマットなどには多少編集を施したうえで引用しています。
仏教の概念には後世の付け足しがたくさんありますが、十八界はブッダ自身の発想であるとされています。したがって、ネットを含めてさまざまな資料に載っています。
この本を引用元として選んだ理由は、リストが比較的コンパクトにまとまっていたことと、意識の知覚作用に「内覚」という、おそらくは造語をあてているのが面白いなと思ったから。