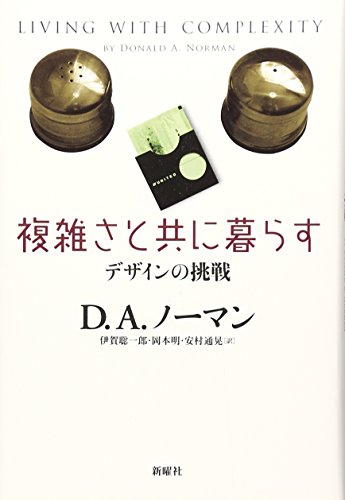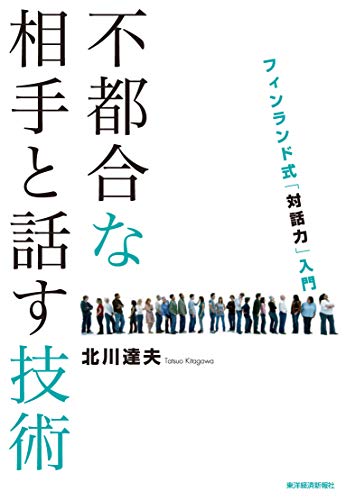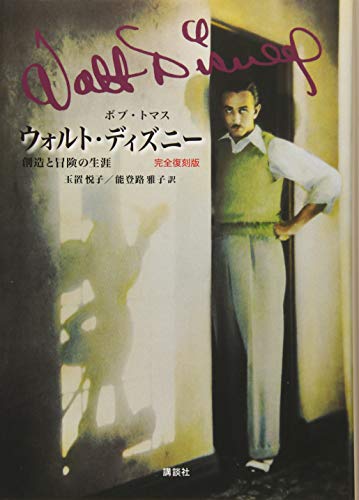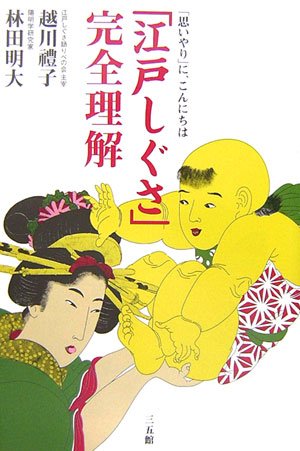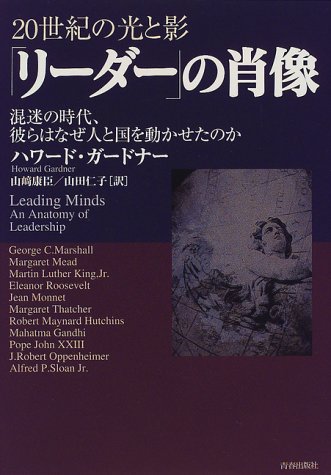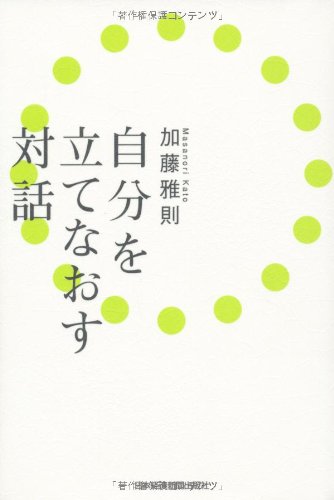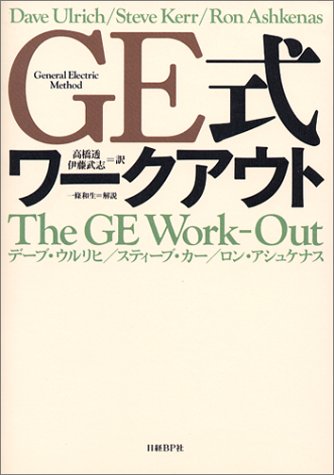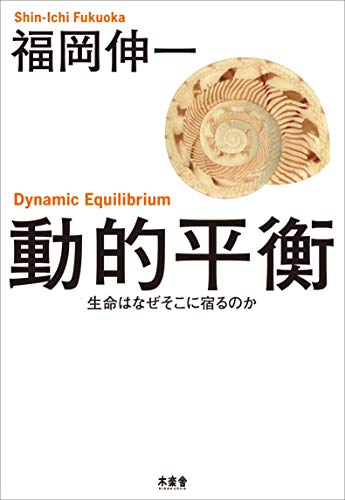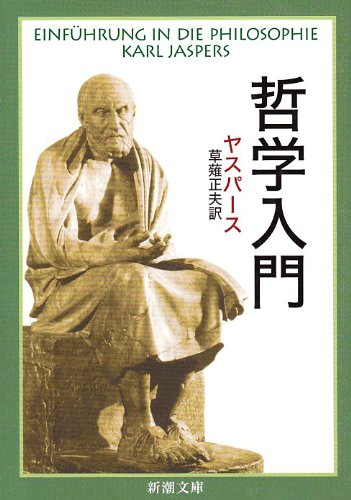まえがき
イベントへの参加者が、後日経験を振り返ったときに「良い経験だった」と思い出してくれるようにするために、デザイナーが守るべき原則とは。
リスト
- 終わりをうまく扱うこと
- 家に持ち帰る記念品を与えること
- 始まりと終わりを強調すること
- 避けられない不愉快な場面を中ごろに埋め込むこと
あとがき
『複雑さと共に暮らす―デザインの挑戦』第7章「待つことのデザイン」より。文章をリスト化して引用しました。
たとえば遊園地で遊ぶというイベントには、不愉快な経験(待ち時間)と愉快な経験(アトラクション)が混在しています。『人間の記憶の研究では、イベントの想起は経験の能動的な再構築であり、多くの歪みが起こることが示されている』そうですので、イベントの設計者からすると、客がトータルの経験を後でよい思い出として想起してくれることが重要なわけです。遊園地だけでなく、研修やプレゼンテーションなど「経験」を設計・提供する立場の人にとっては有用なリストではないでしょうか。
リスト項目は、単一の研究結果の紹介ではありません。著者は南カリフォルニア大学マーシャルビジネススクールのリチャード・チェイスとスリラム・ダスの研究結果を挙げ、加えて『イベントの記憶に関する多くの研究結果は、次のようなデザイン原則を強化するものである』としてこれらの項目を列挙しています。
- タイトル: 複雑さと共に暮らす―デザインの挑戦
- 著者: ドナルド・ノーマン(著)、伊賀聡一郎(翻訳)、岡本明(翻訳)、安村通晃(翻訳)
- 出版社: 新曜社
- 出版日: 2011-07-28