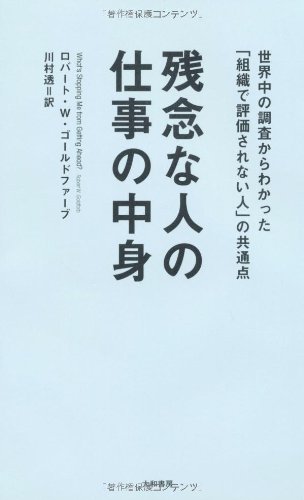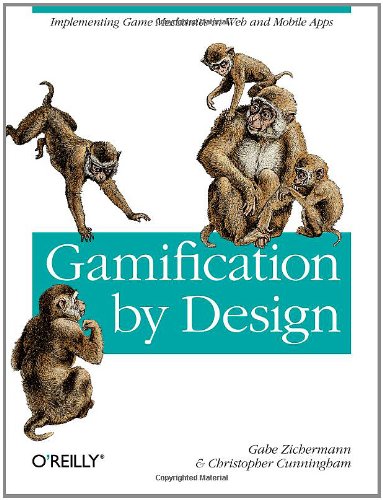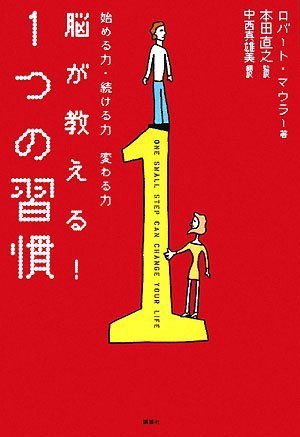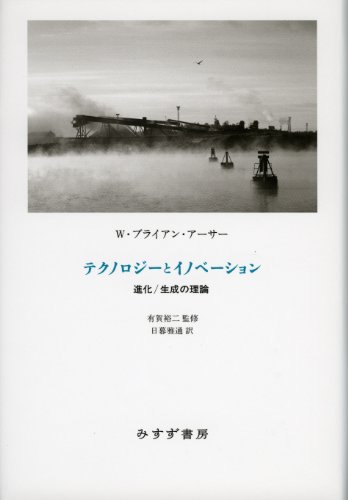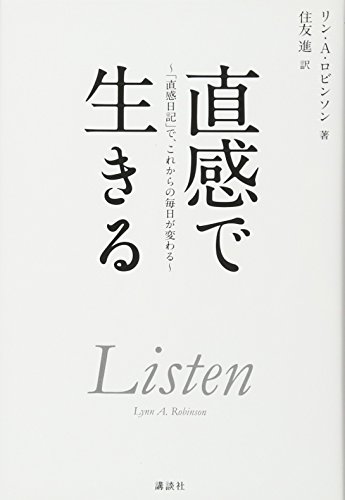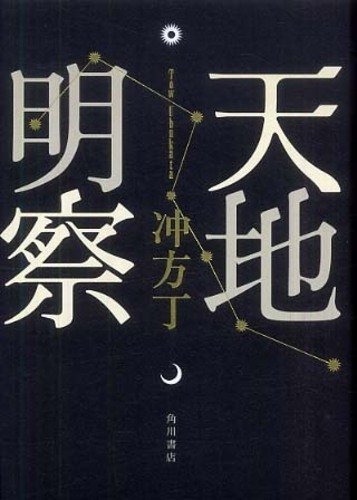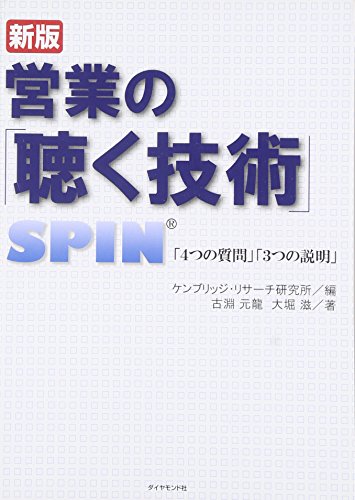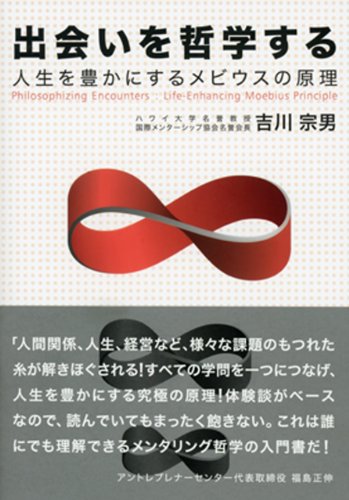まえがき
『世界5大陸、60以上の組織で800人以上のコンサルティング、コーチングを行なってきた著者曰く、民族・業種・業態を問わず、「組織で評価されない人」には「12の共通点」があるという。』
リスト
- 【一貫性の欠如】 ごまかす。人の手柄を横取りする。まわりに不信感を持たせるような振る舞いをする。
- 【役割の無理解】 「上司にとって何が大事か」をよくわかっていない。
- 【ジコチュー】 人と協力して仕事をするのを嫌がる。
- 【傲慢】 高飛車で挑発的。トラブルメーカー。
- 【頑固】 譲歩しない。組織の利益より自分のエゴ。絶対に譲らない。
- 【理論至上主義】 理屈っぽい。直感や第六感をまったく受け入れない。融通の利かない石頭。
- 【偏見】 異性や異なる立場の相手を軽視する。
- 【変化への抵抗】 変化を嫌がる。新しいアイデアも非現実的と切り捨てる。
- 【仲良しクラブ】 かつての同僚の上司になりきれない。いつまでも仲良しクラブのまま。
- 【まかせない】 人に仕事をまかせられない。自分でやった方が簡単と思っている。
- 【問題の誇張】 解決方法よりも問題自体にとらわれすぎ。過度の心配性。
- 【無用なユーモア】 人を傷つける皮肉や無神経なユーモアばかり言う。
あとがき
『残念な人の仕事の中身 ~世界中の調査からわかった「組織で評価されない人」の共通点』より。まえがきはamazon.co.jpの「内容紹介」コーナーからの引用です。
どれも身につまされますが、個人的には最後のポイントだなあ。なかなか直らない癖だと思っていたことが、12大特徴の1つとは。
リストとして鑑賞すると、もう一段階の集約、あるいは並び順への配慮があるとよかったように思います。
- タイトル: 残念な人の仕事の中身 ~世界中の調査からわかった「組織で評価されない人」の共通点
- 著者: ロバート・W・ゴールドファーブ(著)、川村 透(翻訳)
- 出版社: 大和書房
- 出版日: 2011-08-20