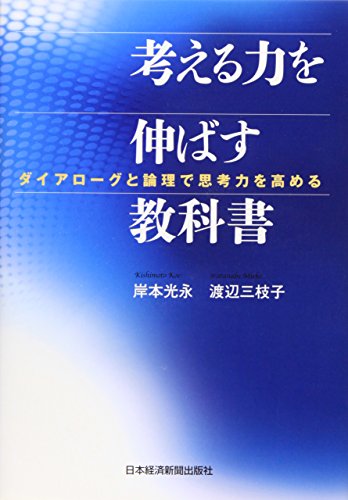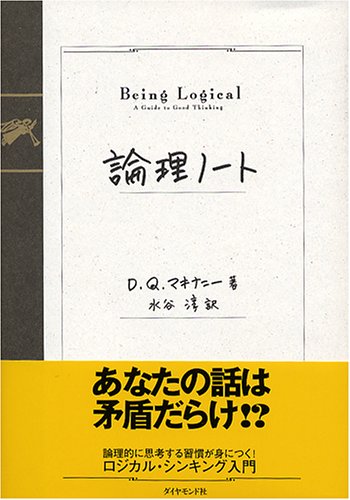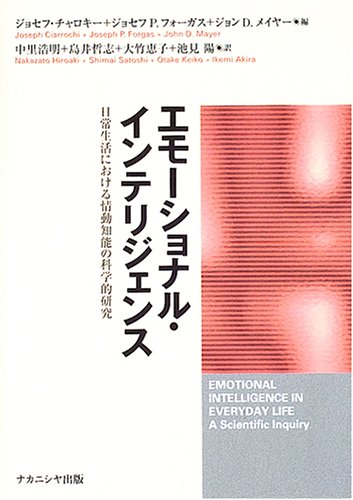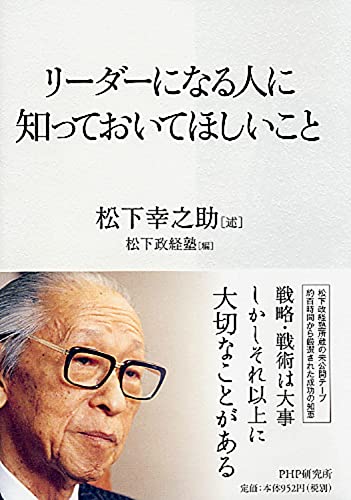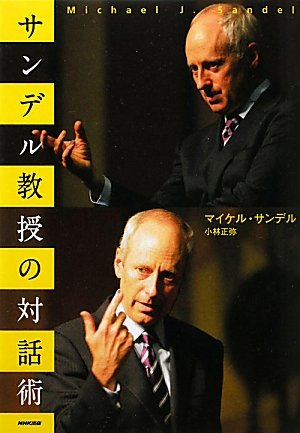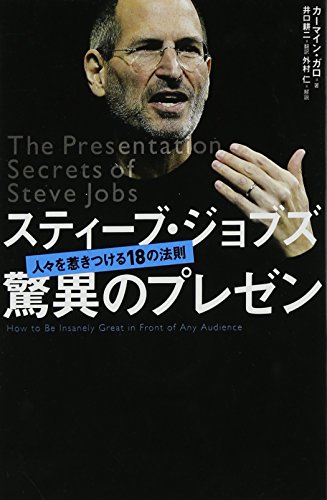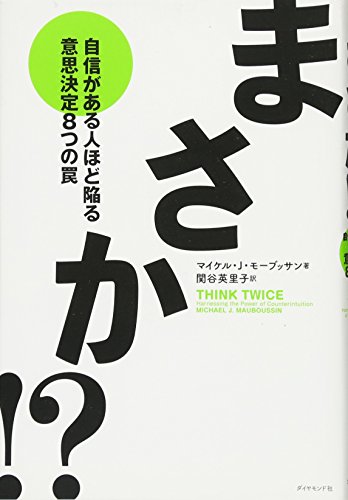まえがき
「睡眠障害は心身の問題を引き起こし、一過性不眠から慢性不眠(疾病)へ移行する可能性がある。慢性不眠は生活の質の著しい低下を招くほか、うつ病のリスクを高め、自殺の原因になることも」
リスト
- 【睡眠時間は人それぞれ、日中の眠気で困らなければ十分】 睡眠の長い人、短い人、季節でも変化、8時間にこだわらない/年をとると必要な睡眠時間は短くなる
- 【刺激物を避け、眠る前には自分なりのリラックス法】 就寝前4時間のカフェイン摂取、就寝前1時間の喫煙は避ける/軽めの読書、音楽、ぬるめの入浴、香り、筋弛緩トレーニング
- 【眠たくなってから床に就く、就寝時刻にこだわり過ぎない】 眠ろうとする意気込みが頭を冴えさせる、寝付きを悪くする
- 【同じ時刻に毎日起床】 早寝早起きではなく、早起きが早寝に通じる/日曜に遅くまで床で過ごすと、月曜の朝が辛くなる
- 【光の利用でよい睡眠】 目が覚めたら日光を取り入れ、体内時計をスイッチオン/夜は明るすぎない照明を
- 【規則正しい3度の食事、規則的な運動習慣】 朝食は心と体の目覚めに重要、夜食はごく軽く/運動習慣は熟睡を促進
- 【昼寝をするなら、15時前の20〜30分】 長い昼寝はかえってぼんやりのもと/夕方以降の昼寝は夜の睡眠に悪影響
- 【眠りが浅いときは、むしろ積極的に遅寝・早起きに】 寝床で長く過ごしすぎると熟眠感が減る
- 【睡眠中の激しいイビキ・呼吸停止や足のピクつき・むずむず感は要注意】 背景に睡眠の病気、専門的な治療が必要
- 【十分眠っても日中の眠気が強いときは専門医に】 長時間眠っても日中の眠気で仕事・学業に支障がある場合は専門医に相談/車の運転に注意
- 【睡眠薬代わりの寝酒は不眠のもと】 睡眠薬代わりの寝酒は、深い睡眠を減らし、夜中に目覚める原因となる
- 【睡眠薬は医師の指示で正しく使えば安全】 一定時刻に服用し就寝/アルコールとの併用をしない
あとがき
まえがきを含めて「【レポート】休日の寝だめは赤信号、遅寝早起きはオススメ! 「もはや国民病」睡眠障害の現状と対応(マイコミジャーナル)」より。Twitter / @yoshikmaで見かけました。
原典は、厚生労働省の精神・神経疾患研究委託費を受けた「睡眠障害の診断・治療ガイドライン作成とその実証的研究班」の平成13年度研究報告書とのこと。この成果の詳細は『睡眠障害の対応と治療ガイドライン』という書籍にまとめられ、ネットからは参照できないようです。
熟眠感(8)なんて言葉があるんですね。個人的には(4)がナルホドでした。睡眠のコントロールは、起床時間のコントロールと見つけたり。
- タイトル: 睡眠障害の対応と治療ガイドライン
- 著者: 睡眠障害の診断・治療ガイドライン研究会(Unknown)、真, 内山(Unknown)
- 出版社: じほう
- 出版日: 2002-07-01
(追記:2014/04/02)
2014年版が出ています。
睡眠12箇条(健康づくりのための睡眠指針 2014)