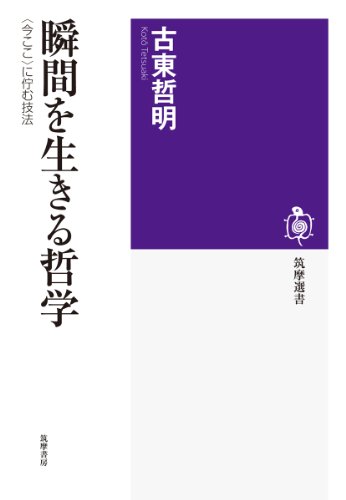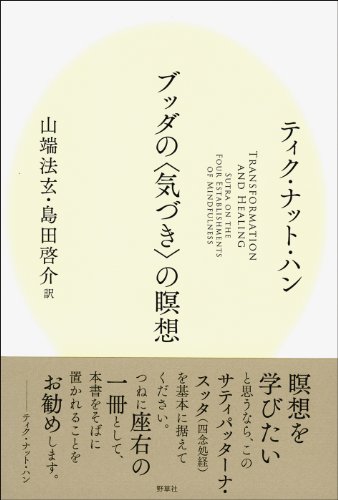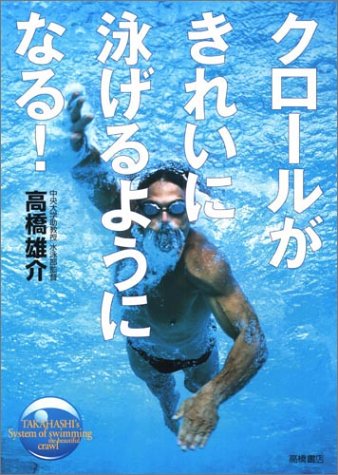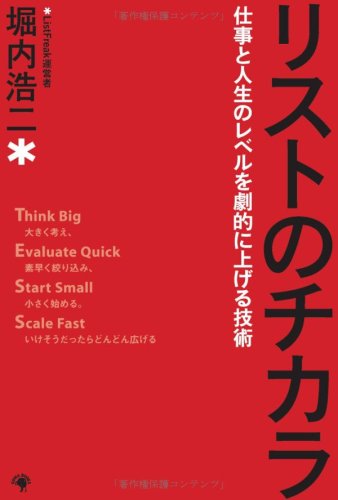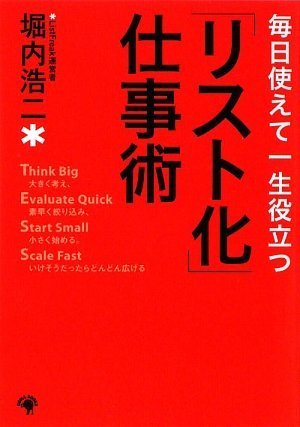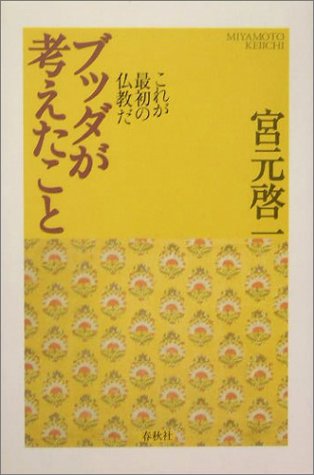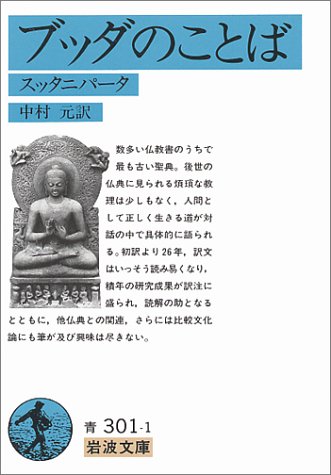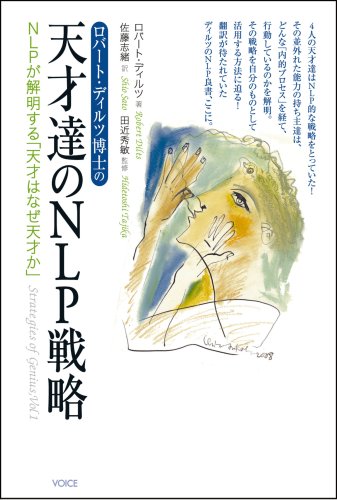まえがき
社会からみた家庭の機能とは。
リスト
- 社会化機能(人間性を形成し文化を内面化し社会適応能力を身につけるよう子供を教育する機能)
- 経済機能(生産・消費の基礎単位機能)
- 私的所有物保持・防護機能
- 性機能(婚外性を禁じ性秩序を維持しながら子を産むことで社会の新成員を補充)
- 福祉・医療機能(病人や老人子供の扶養・援助・治癒機能)
- 情緒安定槻能(外界から一線を画した、安らぎと憩いの場の提供機能)
あとがき
『瞬間を生きる哲学』より。本の主旨とはあまり関係のない会話の中で出てきたのですが、このように整理されたリストを見たことがなかったので反射的にメモ。
著者の専門は哲学なので、ここ何かからの引用と思われますが、引用元は不明。厚生白書とかには似たような情報がありそう。