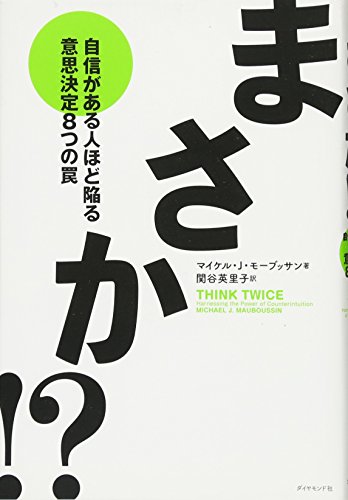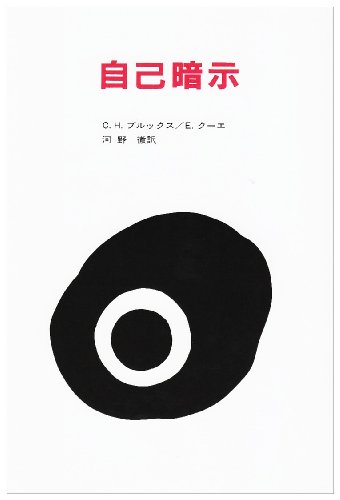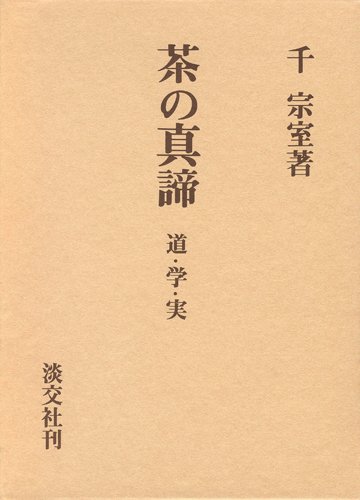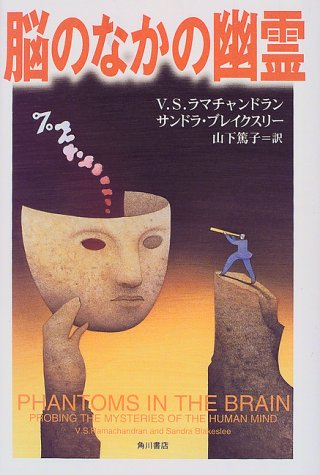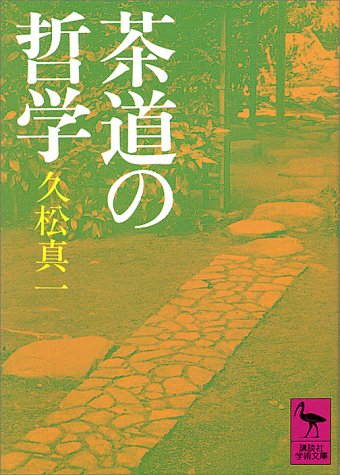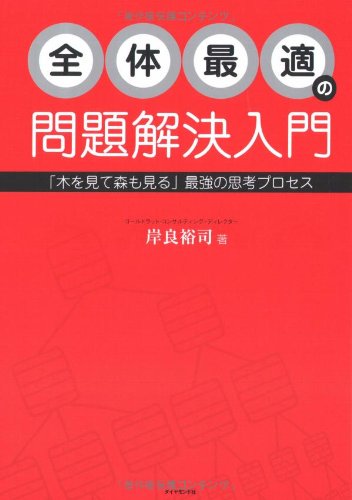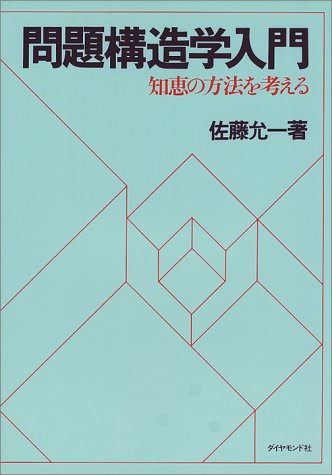まえがき
『本書はまさしく、「思考することをあきらめてはならない」ということを言っている。』
リスト
- 意思決定をする際に、過去のデータなど客観的な指標を使って判断できているか。自分が直面している問題は特別なものだと、浅はかな勘違いをしていないか。楽観的に考え過ぎていないか。
- 視野を広げて、他の選択肢を考えたか。問題を検討するにあたって、自分はアンカーやインセンティブの影響を受けていないか。
- この問題は専門家の意見を聞くべきものか、そうでないものか、わかっているだろうか。専門家の意見を鵜呑みにしていないだろうか。
- 自分の周りの状況を冷静に理解しているだろうか。周りの影響を受けて、決断しようとしていないだろうか。
- 自分が置かれている状況、つまり自分の置かれているシステムの複雑さを考慮に入れているだろうか。複雑な状況を、必要以上に簡略化して考えていないだろうか。個別の部分を見るのではなく、全体最適の視点に立って、問題をとらえられているか。
- 自分は、物事の相互関係と因果関係の区別がついているだろうか。状況に見合った意思決定となっているだろうか。状況に当てはまらない「理論」を無理に当てはめてしまっていないか。
- 物事が大きく変化する可能性を考慮に入れているだろうか。
- 運と実力を混同していないだろうか。ハロー効果の影響を受けていないか。
あとがき
まえがきを含めて『まさか!?―自信がある人ほど陥る意思決定8つの罠』より。リストは「訳者あとがき」からの引用です。
「罠」のタイプを8つに分けて、豊富な事例を交えて解説しています。章ごとにまとめも付いています。ただ本文には、本書全体のまとめになるようなリストはありませんでした。終章では意思決定のチェックリストを作るべしという提案があったので、自分なりのリストを作れということでしょう。
と思ったら、本文に続く「訳者あとがき」で、親切にも訳者(関谷英里子氏)が先回りしてそのようなリストを作ってくれていました。ありがたく引用させていただきます。
- タイトル: まさか!?―自信がある人ほど陥る意思決定8つの罠
- 著者: マイケル・J・モーブッサン(著)、関谷 英里子(翻訳)
- 出版社: ダイヤモンド社
- 出版日: 2010-04-09