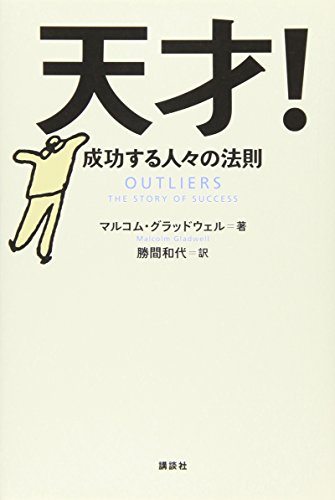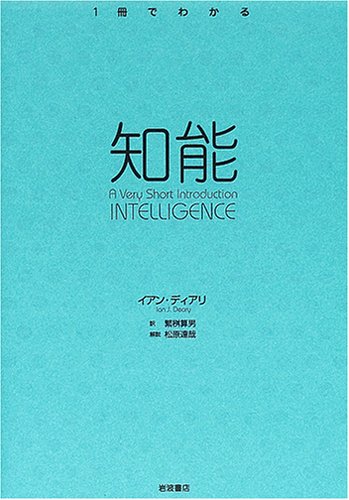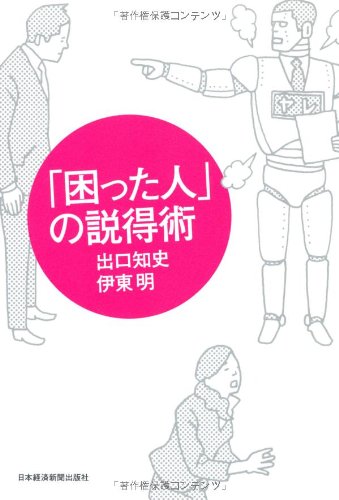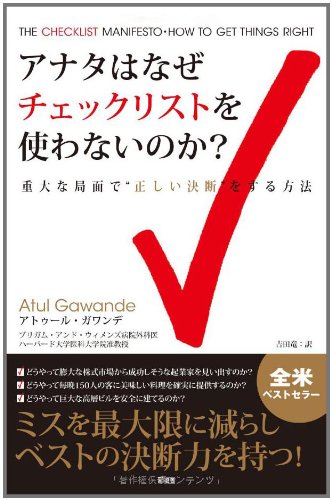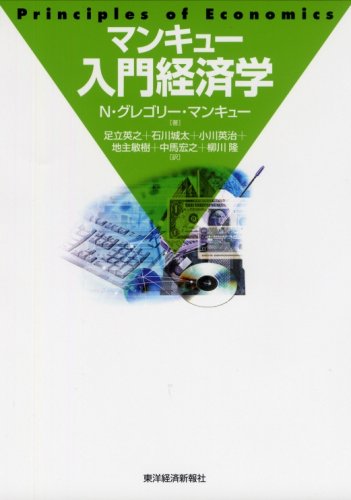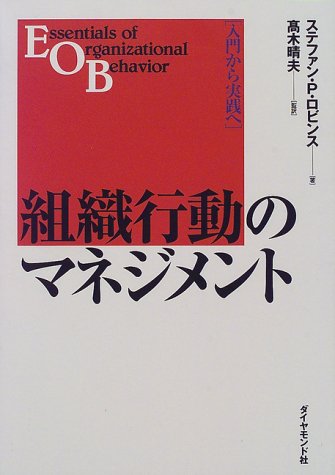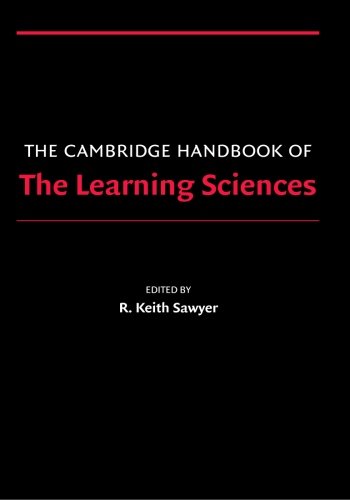まえがき
KIPP(Knowledge Is Power Program)というアメリカのチャータースクールが生徒に求めている、教室内でのふるまいとは。
リスト
- Sit up straight(きちんとした姿勢を保つ)
- Listen(耳を傾ける)
- Ask and answer(質問し、質問に答える)
- Nod your head(うなずく)
- Track the speaker with your eyes(話し手を目で追う)
あとがき
“SLANT in KIPP Schools“(YouTube)の、開始後45秒あたりからの引用です。
授業に参加するときに生徒に取ってほしい行動が、姿勢・耳・口・頭・目のレベルで端的かつ具体的にリストアップされていて、なかなかよくできているなあと感じたので収集しました。ただ、slantとは斜めという意味ですよね。リストの目的と合っていないような気もしますが、他に意味があるのかな。
このリスト(に近いもの)を知ったのは『天才! 成功する人々の法則』という本です。ごく大まかに言えば「学習時間を長くすれば成績が良くなる」という著者の主張を裏付ける事例として、KIPPという『実験的な公立学校』が紹介されていました。
この本では、Sが一つ多い”SSLANT”が紹介されています。参考までにこちらも引用しておきます(訳書では”Nod when spoken to”となっていますが、原書”Outliers”に従ってbeingを追加しています)。
Smile(笑顔を忘れない)
Sit up(きちんとした姿勢を保つ)
Listen(耳を傾ける)
Ask questions(質問する)
Nod when being spoken to(話しかけられたら会釈する)
Track with your eyes(相手を目で追う)
Sit up = きちんとした姿勢を保つ は意味を酌んだ訳に思えたのでそのまま使わせていただいています。一方Nod=会釈では、クラスルームの振る舞いとしては妙なので、これは普通に「うなずく」としました。
(参考)
- タイトル: 天才! 成功する人々の法則
- 著者: マルコム・グラッドウェル(著)、勝間 和代(翻訳)
- 出版社: 講談社
- 出版日: 2009-05-13