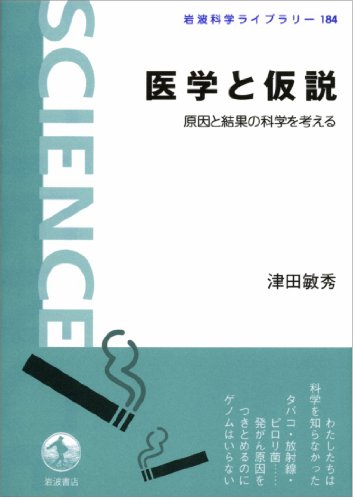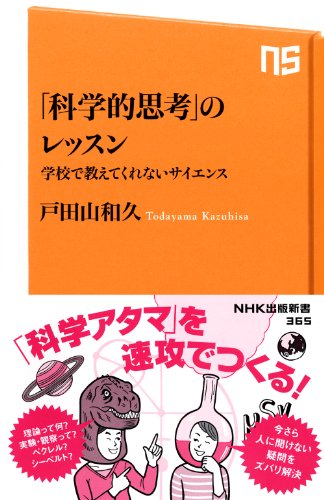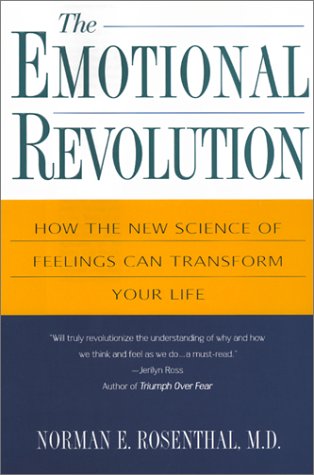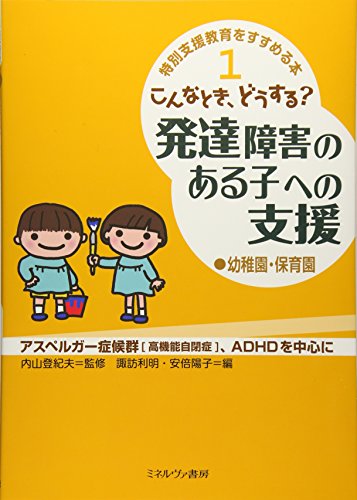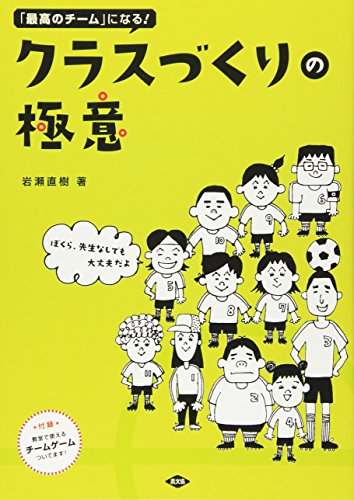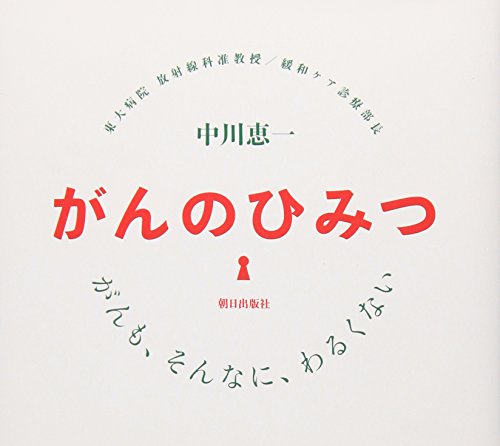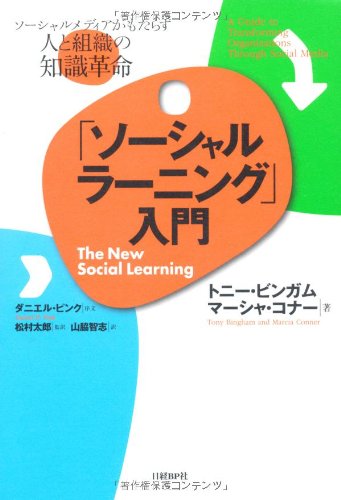まえがき
『長期にわたる関係を無理なく維持するためには、お互いの主な価値観を気持ちよく受け止められなくてはなりません。
以下にあげるのは、長期間のパートナーとして考えている相手と共有できるかもしれない、あるいは共有できないかもしれない価値観です。』
リスト
- 友情 お互いの親密さや興味に応じて、二人の関係に他人を加えること。
- 家庭生活 家族を持ち、家族の一員となること。親になること。
- 宗教 絶対的で人智を超えた力とつながりを持ちたいと思うこと。
- 実利主義 お金を貯め、お金をコントロールすることに中心的な価値を置くこと。
- 唯美主義 特に音楽、文学、絵画に関連した美と好みに重きを置くこと。
- 知性 分析的、合理的な追求に価値を置くこと。
- 社会性 他の人を助けること、社会的な関心を示すこと。
- 官能主義 肉体の快楽を追求すること。
- 快楽主義 楽しいことや楽しい時間に価値を置くこと。
- 経歴主義 経歴をつむことに価値を置くこと。
- 現実主義 理性の追求。実用的なことが重要であり頼りがいがあるという考え方。
- アウトドア志向 戸外での活動に価値を認めること。自然との対話を好むこと。
- スポーツ志向 スポーツに参加することに価値を見出そうとすること。
- 自主性 自立に価値を置き、自分のことについて考えること。何か企てることに価値を置くこと。
- 伝統の専重 伝統に価値を置くこと。現状に従い同調を重んじること。
- 自己実現 個人としての成長と発達に関心を注ぐこと。
あとがき
まえがきを含めて『思いやりの人間関係スキル―一人でできるトレーニング』より。一生に何回も使わないような、そして自分はたぶんもう使わないリストだけれど、誰かの役に立ちそうな気がします。
- タイトル: 思いやりの人間関係スキル :一人でできるトレーニング
- 著者: リチャード ネルソン・ジョーンズ(著)、Nelson Jones,Richard(原著)、充, 相川(翻訳)
- 出版社: 誠信書房
- 出版日: 1993-02-15