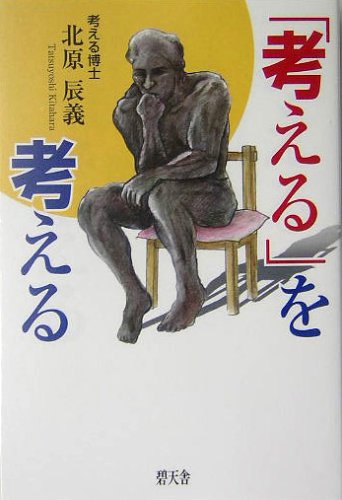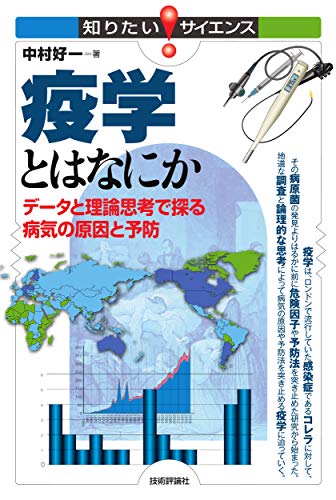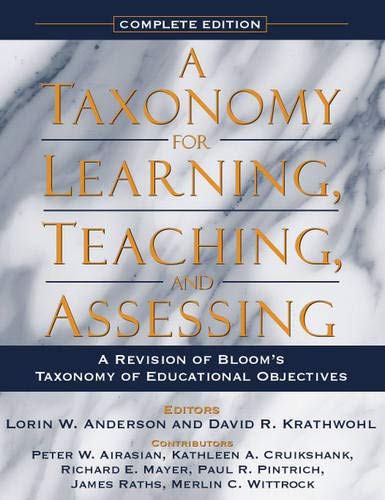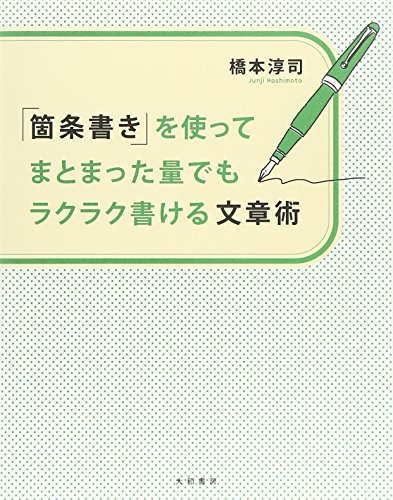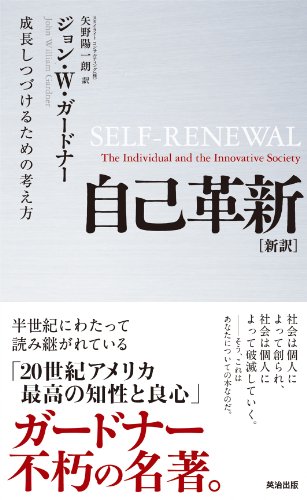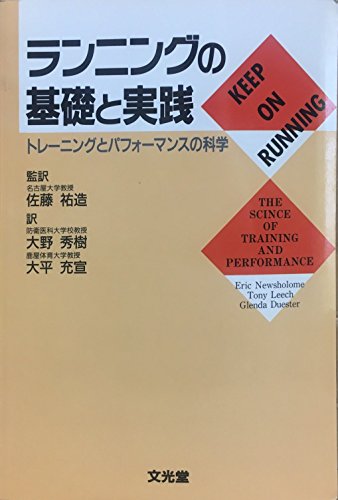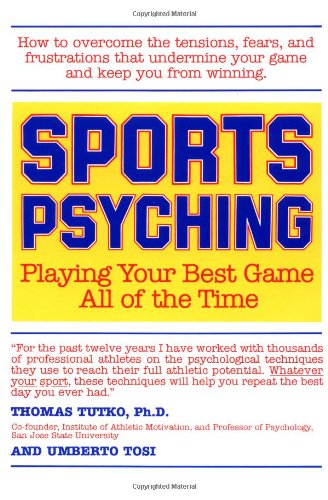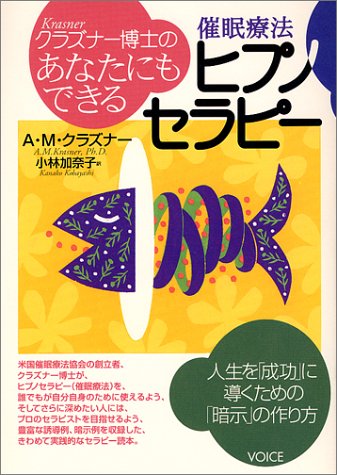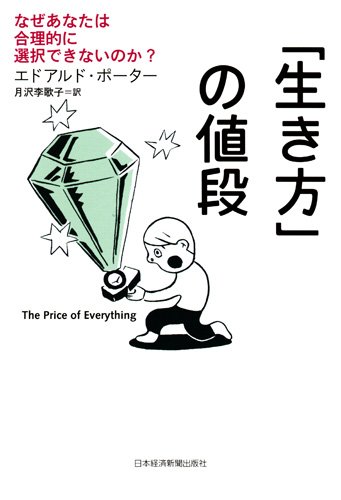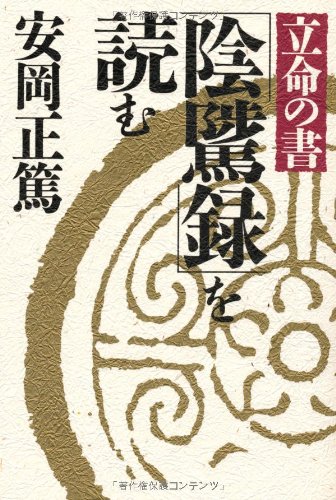まえがき
『1964年、米国公衆衛生総監の諮問委員会(略)は、(略)因果関係の有意性を判定するための基準を示した』。AがBの原因であると判断するためには、何が言えればいいか。
リスト
- 【関連の一貫性】 AとBとの関連には再現性がある
- 【関連の強さ】 AとBとの関連は密接である
- 【関連の特異性】 Aは他の原因候補よりも強くBに関連している
- 【関連の時間関係】 AがBに先行している
- 【関連の整合性】 AがBの原因であることが他の理論や知識と矛盾しない
あとがき
まえがきは『ニッポンの「たばこ政策」への提言』(Tobacco Free * Japan、2004年)より。リスト項目は私訳です。引用元については以下に解説します。
『「考える」を考える』という本で、『米国公衆衛生局諮問委員会では、因果関係五原則を発表しています』という文を見かけてました。その五原則も載っていたのですが、オリジナルの用語を知りたいと思って検索した結果、1964年の”Smoking and Health: Report of the Advisory Committee to the Surgeon General of the United States“(Wikipedia)というレポートが原典であることが分かりました(ただしWikipediaには五原則は載っていません。興味のある方は原典 “Smoking and Health (1964)” をどうぞ)。
その五原則はこんな感じです。これを訳し、短い解説を添えてみたのが上のリスト(解説部分は本文の翻訳ではありません)。
- a. The consistency of the association
- b. The strength of the association
- c. The specificity of the association
- d. The temporal relationship of the association
- e. The coherence of the association
参考までに『「考える」を考える』版も引用します。
- 関連の時間性 原因は結果に先行する。
- 関連の普遍性 その関係や現象がどこでも成り立つ。
- 関連の密接性 原因と結果に相関関係がある。
- 関連の特異性 その原因があれば、ある確率でその問題が発生する。
- 関連の合理性 その関係がこれまでの理論に合致する。
- タイトル: 「考える」を考える
- 著者: 北原 辰義(著)
- 出版社: 碧天舎
- 出版日: 2005-06-01
追加:中村 好一『疫学とはなにか データと理論思考で探る病気の原因と予防』(技術評論社、2021年)を参考に原典のリンクを更新しました。本書でも五原則が紹介されています。
- タイトル: 疫学とはなにか データと理論思考で探る病気の原因と予防
- 著者: 中村 好一(著)
- 出版社: 技術評論社
- 出版日: 2021-04-16