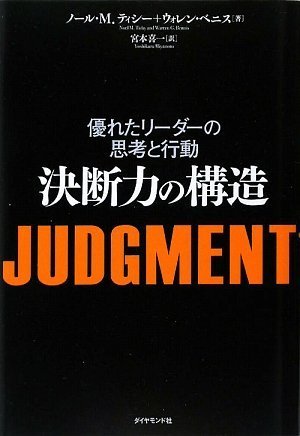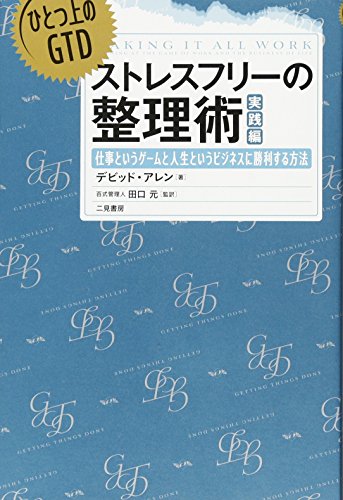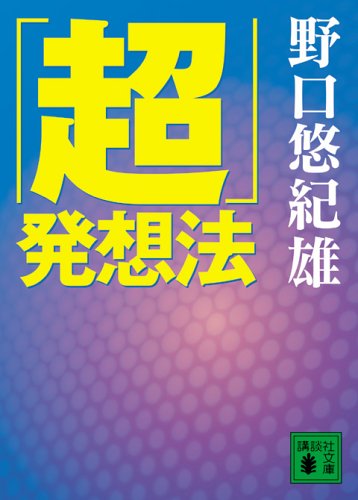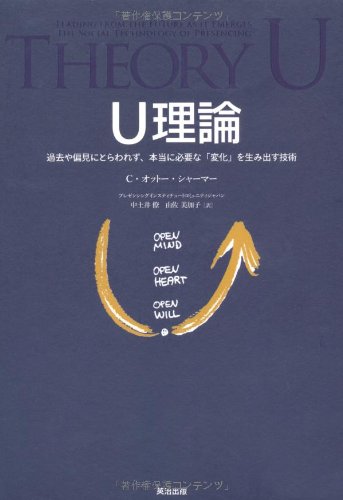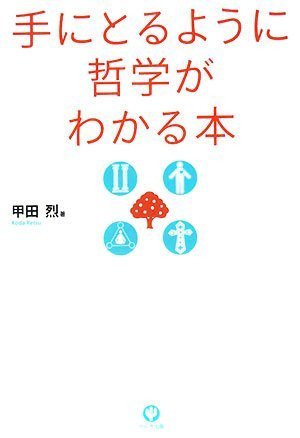まえがき
一九六一年一月九日、アメリカ第三五代大統領としての就任演説を一一日後に控え、ジョン・F・ケネディはマサチューセッツ州議会で上院議員としての最後の演説をした。
「いずれ将来、歴史の最高裁がわれわれひとりひとりに判決をくだす日がやって来る……どんな政治的な立場であっても、成功するか失敗するかは、次の四つの質問に対する答えで決まるだろう。」
リスト
- われわれは本当に勇気のある人間だったか
- われわれは本当に誠実な人間だったか
- われわれは本当に決断力のある人間だったか
- われわれは本当に献身的な人間だったか
あとがき
まえがきを含めて『決断力の構造―優れたリーダーの思考と行動』より。
原文と音声は”Address of President-Elect John F. Kennedy Delivered to a Joint Convention of the General Court of the Commonwealth of Massachusetts“(John F. Kennedy Presidential Library & Museum)にあります。またYouTubeには部分的ながらスピーチの映像がありました。
もうちょっとこなれた日本語訳を見つけたいと思いつつ、忘れないようにメモ。
- タイトル: JUDGMENT 決断力の構造―優れたリーダーの思考と行動
- 著者: ノール・M・ティシー(著)、ウォレン・ベニス(著)、宮本 喜一(翻訳)
- 出版社: ダイヤモンド社
- 出版日: 2009-07-17