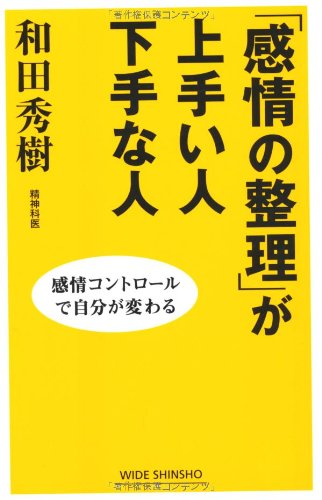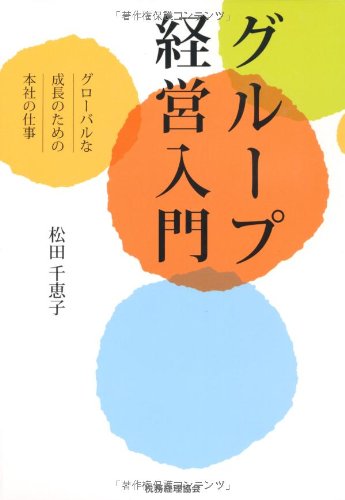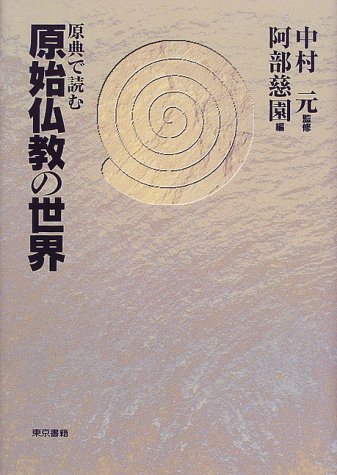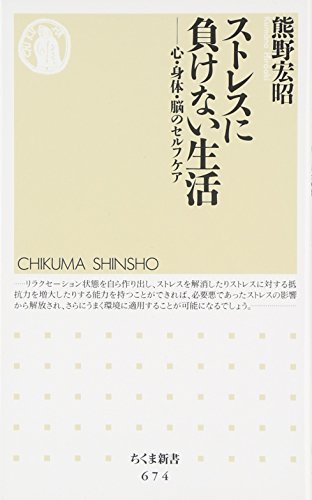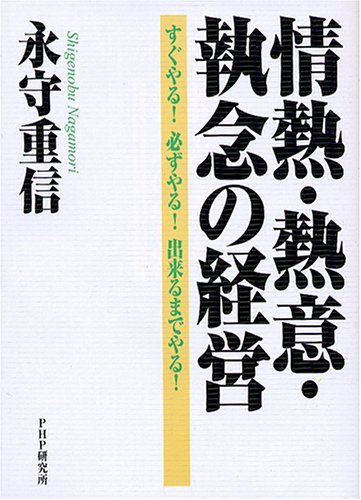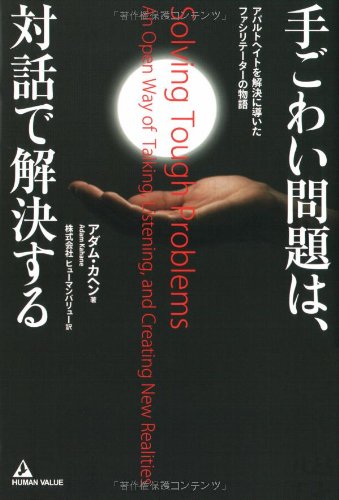まえがき
「この4つの文字の中には、すべてのお茶の心がこめられているといわれています。」
リスト
- 和 … お互いに和やかに楽しむこと
- 敬 … 互いに敬うこと
- 清 … 見た目も心も清潔であること
- 寂 … 不完全なものに美を見いだすこと
あとがき
まえがきは「お茶の心ってなんだろう」(裏千家ホームページ)より。四規(しき)とも呼ばれるそうです。ちなみに 和敬清寂は「わけいせいじゃく」と読みます。
リスト項目は、某中学校の文化祭で見かけた文章を参考にしました。
上記の裏千家のページにももちろん説明をがあるのですが、「寂」が「どんなときにも動じない心」となっています。
文化祭で「寂」の説明を読んで「なるほど、侘(わ)び寂(さ)びの“寂び”か!」と思ってしまったので、文化祭バージョンを採用しました。
他人とともに時を過ごすときの心得として覚えておきたいリストです。