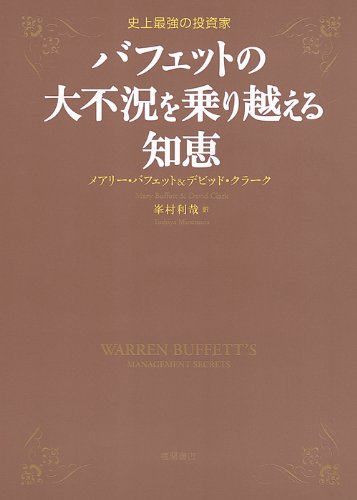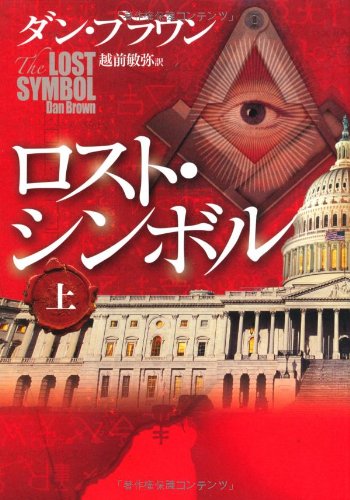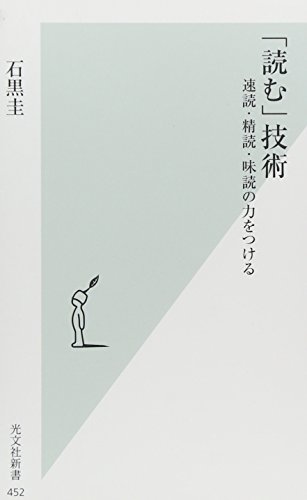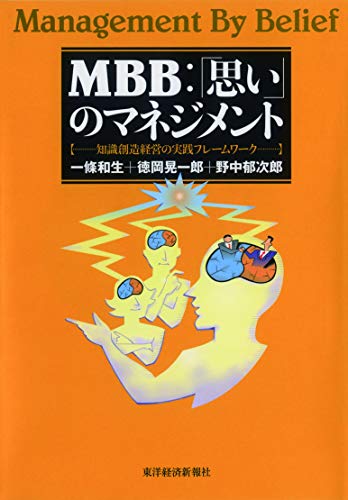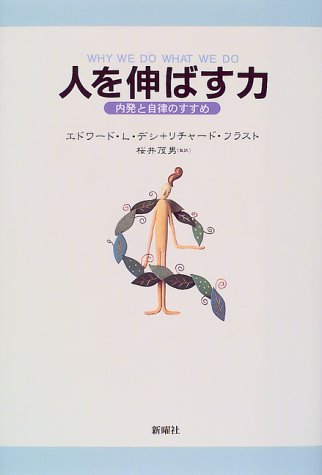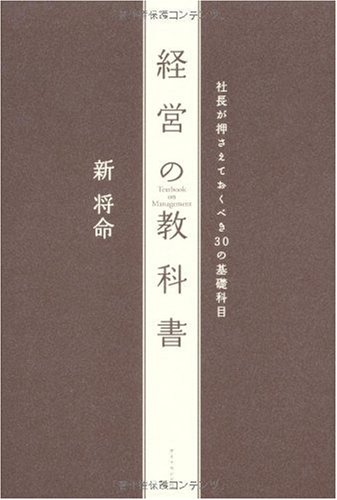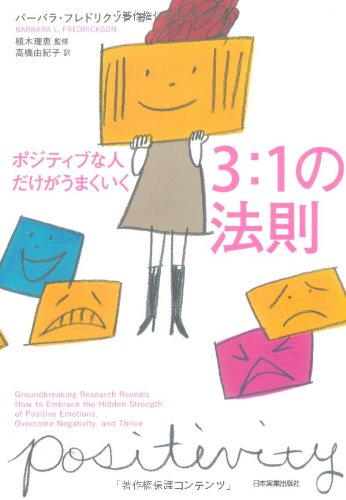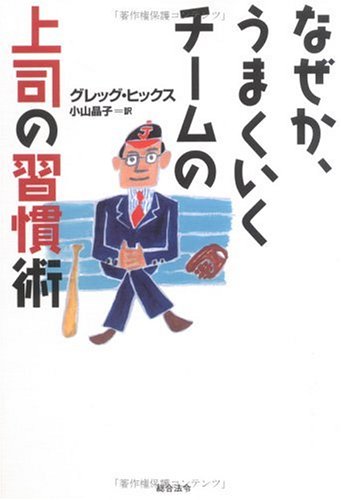まえがき
「経営者の善し悪しはリーダーシツプで決まる。そして、良い経営者は”LEADERSHIP”で表される10の資質を持っていなければならない。」
リスト
- Loyalty(忠実)
- Enthusiasm(熱意)
- Attitude(態度)
- Discipline(規律)
- Example(手本)
- Respect(敬意)
- Scholarliness(学究)
- Honesty(正直)
- Integrity(誠実)
- Pride(矜持)
あとがき
まえがきを含めて『史上最強の投資家 バフェットの大不況を乗り越える知恵』より。長いアクロニムは往々にしてこじつけが目立ちますが、これはいいセンを行っているのでは。
これは、バークシャー・ハサウェイ傘下の企業の創業者が、上司としてのウォーレン・バフェットを評するときに使った言葉。ウォーレン・バフェットはこのすべてを備えているというのです。
- タイトル: 史上最強の投資家 バフェットの大不況を乗り越える知恵
- 著者: メアリー・バフェット(著)、デビッド・クラーク(著)、峯村利哉(翻訳)
- 出版社: 徳間書店
- 出版日: 2010-03-19