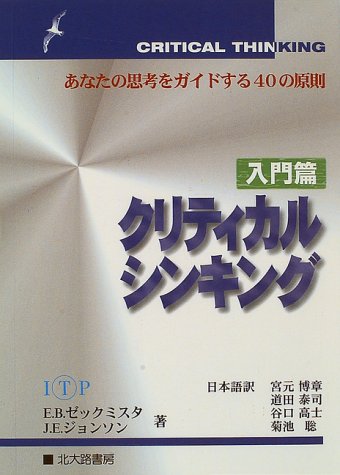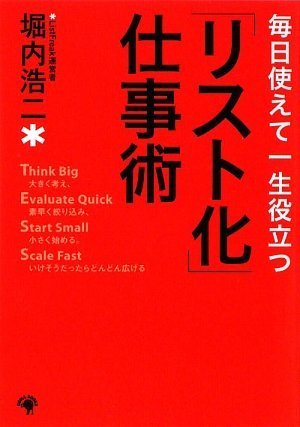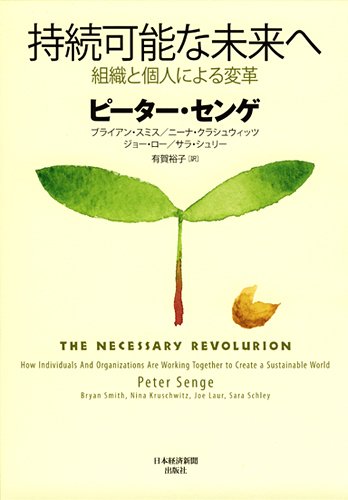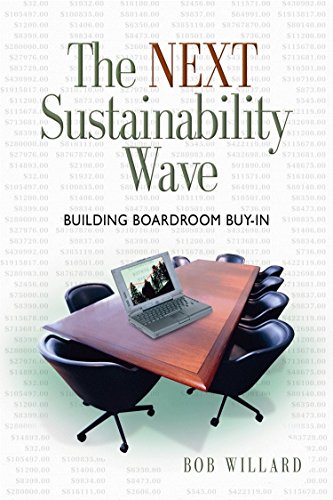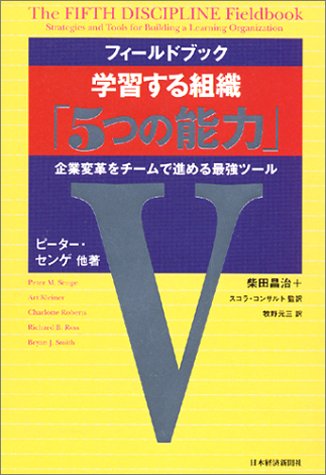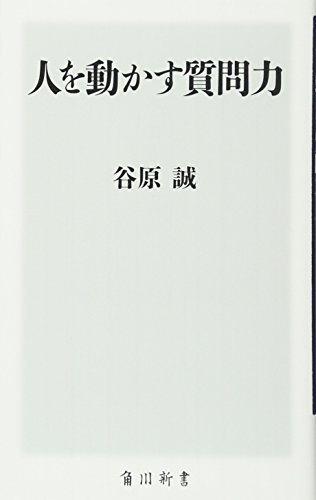まえがき
最近では「ミーティング産業/集客産業」なる言葉もあるとか。
リスト
- Meetings – 企業等の会議
- Incentives – 企業等の行う報奨・研修旅行(インセンティブ旅行)
- Conferences / Conventions – 国際機関・団体、学会等が行う国際会議
- Exhibitions / Events – イベント、展示会・見本市
あとがき
“Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions” (Wikipedia) および 「MICEの開催・誘致の推進」(観光庁)より。まえがきは、Wikipediaにこんな記述があるのを受けて書きました。
“Recently, there has been an industry trend towards using the term “Meetings Industry” to avoid confusion from the acronym.”
こんなacronymがあるとは知らなかった。さらに2010年は”Japan MICE Year”だとか。いつの間に!