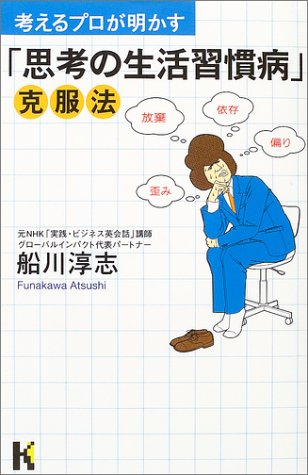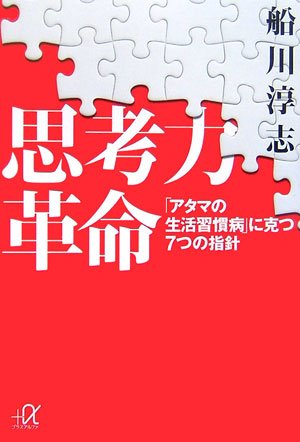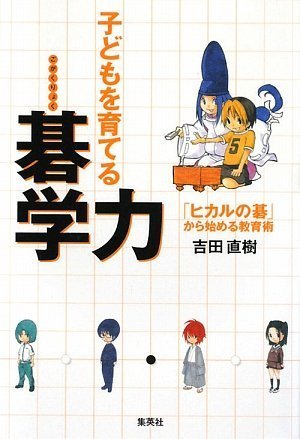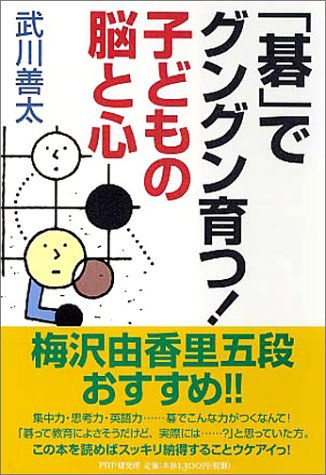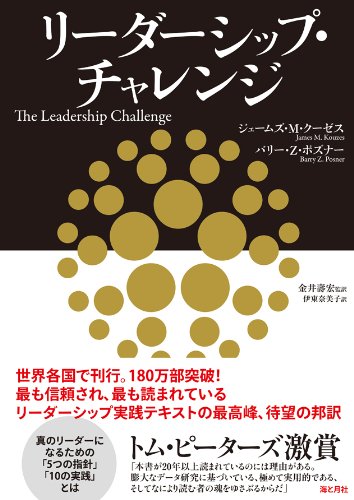まえがき
「おおげさな言い方ではなく、いまや“思考の危機”が日本を覆っているのです」
リスト
- 思考の放棄 ― 「これだけの情報では無理ですよ」などと口にして、自ら考えることを止めてしまう
- 思考の依存 ― 「だって、社長が言ってますよ」と人の頭に頼ってしまう
- 思考の歪み ― 推論の過程にムラや無理がある
- 思考の偏り ― 特定のことについては効果的に推論できるが、ちょっと専門分野がそれると思考力が機能しなくなる
あとがき
まえがきを含めて『考えるプロが明かす「思考の生活習慣病」克服法』より。
あるある!と笑えたり、自分を振り返ると笑えなかったり……なリストです。著者は前2者を「思考停止系」、後2者を「思考不全系」と分類していて、これも納得。
- タイトル: 考えるプロが明かす「思考の生活習慣病」克服法
- 著者: 船川 淳志(著)
- 出版社: 講談社
- 出版日: 2004-02-23
(その後文庫化されています)
- タイトル: 思考力革命 – 「アタマの生活習慣病」に克つ7つの指針 (講談社+α文庫)
- 著者: 船川 淳志(著)
- 出版社: 講談社
- 出版日: 2006-08-19