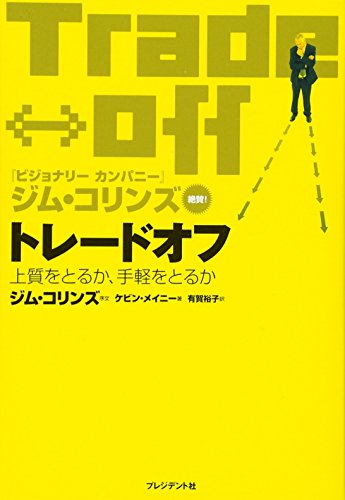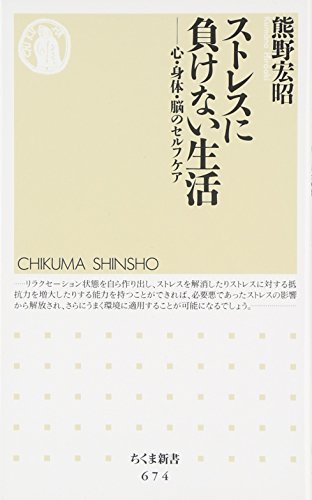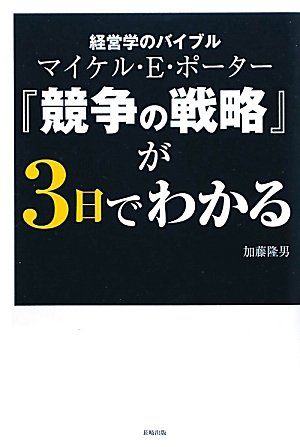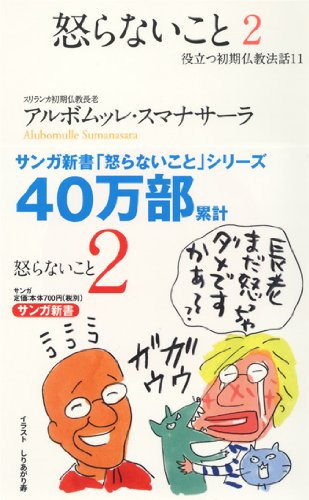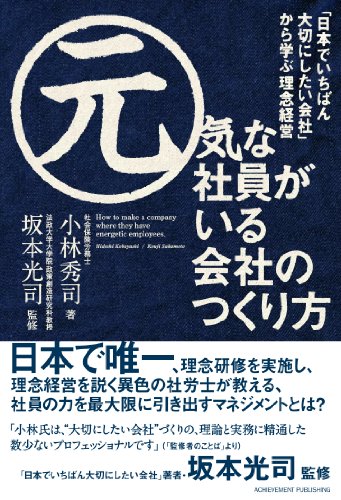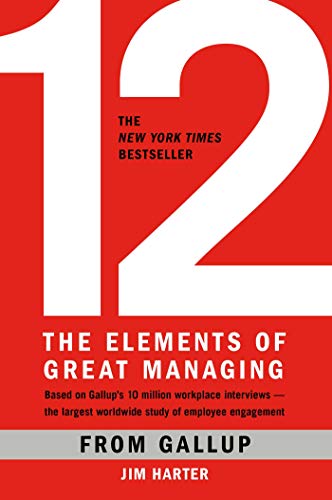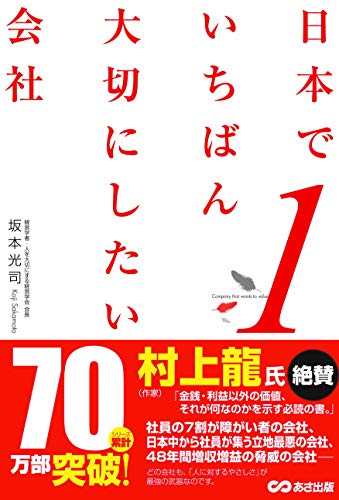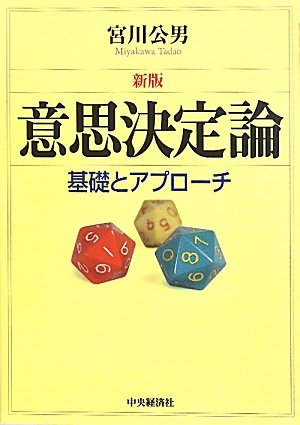まえがき
「私はこれまで、ビジネスの大失敗の数々を詳しく取材して記事にした。それらの事例に上質と手軽の天秤というコンセプトを当てはめてみると、五つの留意点が浮かび上がってくる。」
リスト
- テクノロジーの進歩を見落としてはいけない(上質かどうか、手軽かどうかの基準は、テクノロジーの進歩によって絶えず引き上げられていく)
- 商品やサービスの成否は、目新しいかどうか、時流に乗っているかどうかよりも、上質と手軽のさじ加減で決まる
- 上質と手軽のどちらをどれだけ重視するかは顧客層ごとに異なる
- 商品やサービスを小さく生むと、小回りが利くため、テクノロジーの進歩や競合他社の動きに対応しやすい
- 新しいテクノロジーは必ずといってよいほど不毛地帯(上質でも手軽でもない領域)で産声を上げる
あとがき
まえがきを含めて『トレードオフ ー 上質をとるか、手軽をとるか』より。カッコ内を補足として追加しています。
- タイトル: トレードオフ―上質をとるか、手軽をとるか
- 著者: ケビン・メイニー(著)(著)、ジム・コリンズ(序文)(著)、内田和成(解説)(著)、有賀裕子(翻訳)
- 出版社: プレジデント社
- 出版日: 2010-07-06