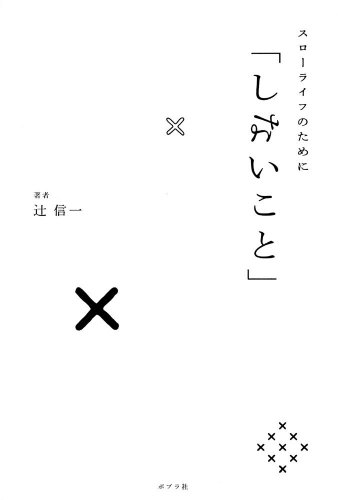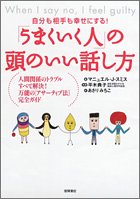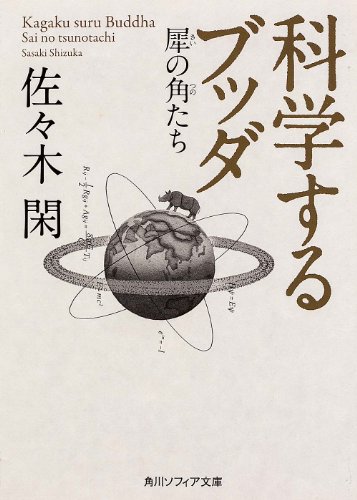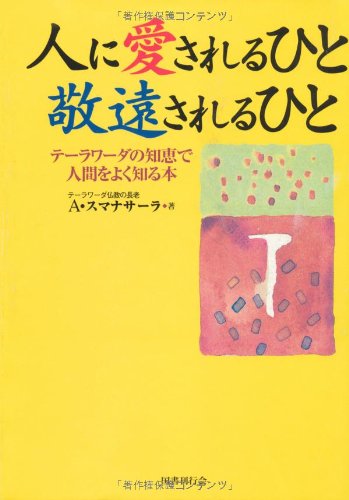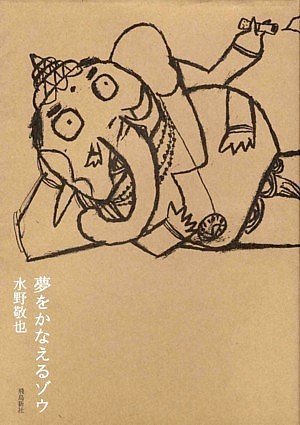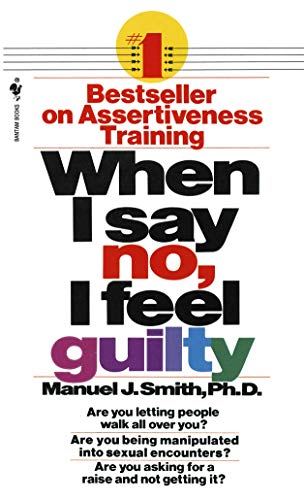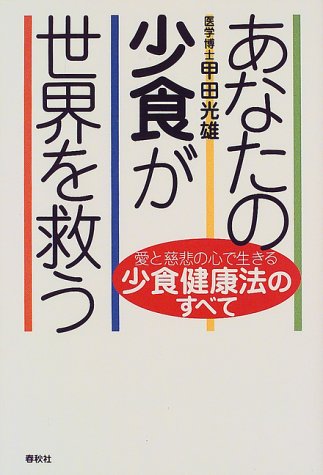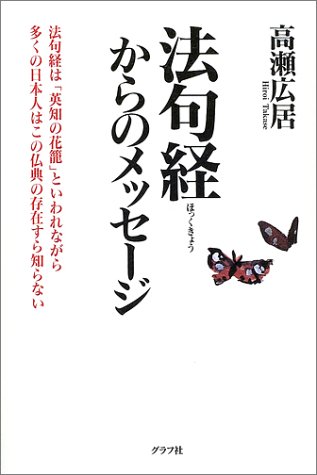まえがき
すべて人はやましさを感じることなくノーと言う権利を有する(You have the right to say no, without feeling guilty.)
リスト
- すべて人は自分の行動・思考・感情を自ら判断し、その開始と帰結に責任を持つ権利を有する。
- すべて人は自分の行動を正当化するための理由や言い訳を述べない権利を有する。
- すべて人は他人の問題解決に責任を負うべきかどうかを自分で判断する権利を有する。
- すべて人は気を変える権利を有する。
- すべて人は自分の責任において間違える権利を有する。
- すべて人は「知らない」と言う権利を有する。
- すべて人は他人の善意に付き合わない権利を有する。
- すべて人は非論理的に決断する権利を有する。
- すべて人は「わからない」と言う権利を有する。
- すべて人は「関心がない」と言う権利を有する。
あとがき
アサーション本の元祖[1]と言われる”When I Say No, I Feel Guilty”より。”A Bill of Assertive Rights”として載っています(文中では”The Bill of 〜”)。
Bill of Rights(権利章典 – Wikipedia)らしくなるよう訳してみました。いかめしくも面白い感じが出ているといいのですが。またまえがきは、巻末にあるこのリストの下に書かれていた文の和訳です。
この本には(『「うまくいく人」の頭のいい話し方』)という邦訳があるのですが、なぜかこの権利章典は載っていないんですよね。そこで原著から訳しました。
[1] “Assertiveness and Assertiveness Training” – BBC
参考までに、オリジナルのリストも引用します。
* You have the right to judge your own behavior, thoughts, and emotions, and to take the responsibility for their initiation and consequences upon yourself.
* You have the right to offer no reasons or excuses for justifying your behavior.
* You have the right to judge if you are responsible for finding solutions to other people’s problems.
* You have the right to change your mind.
* You have the right to make mistakes – and be responsible for them.
* You have the right to say, “I don’t know.”
* You have the right to be independent of the goodwill of others before coping with them.
* You have the right to be illogical in making decisions.
* You have the right to say, “I don’t understand.”
* You have the right to say, “I don’t care.”