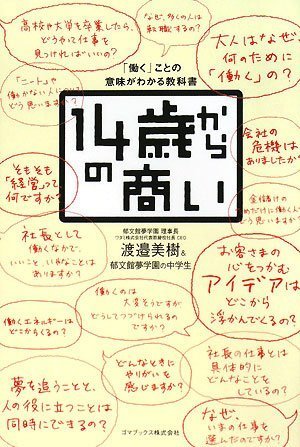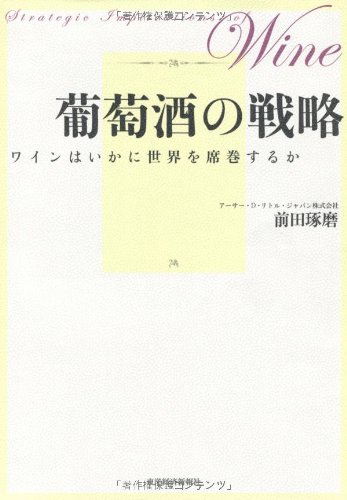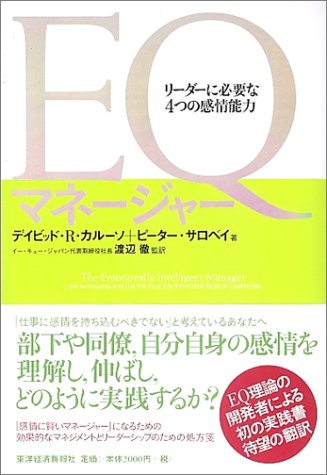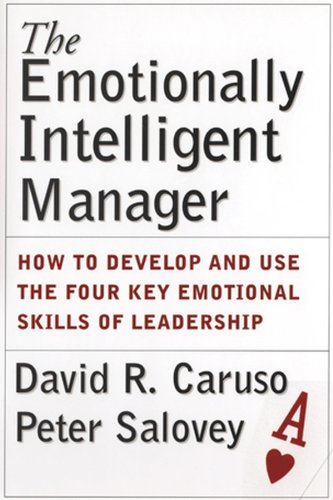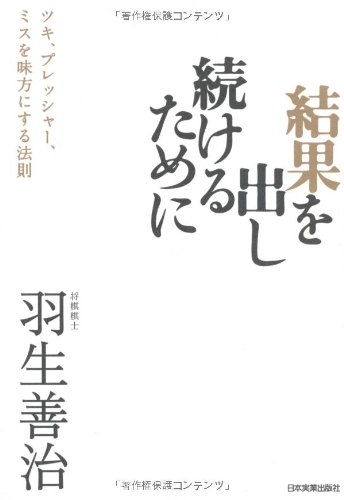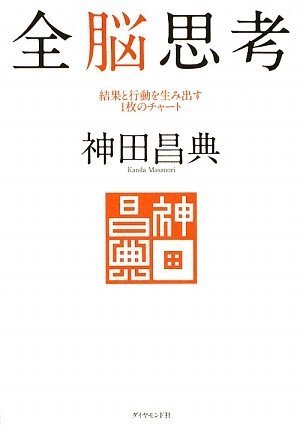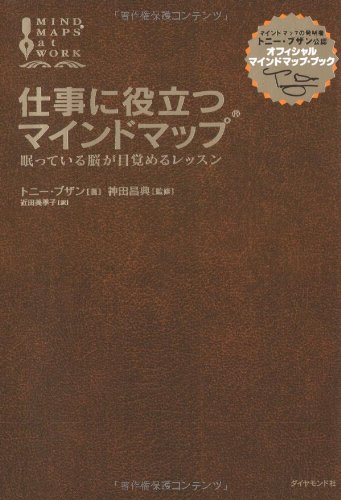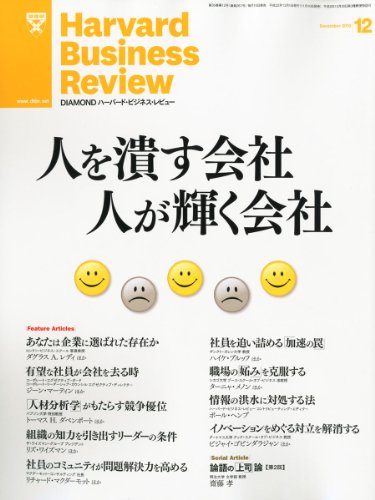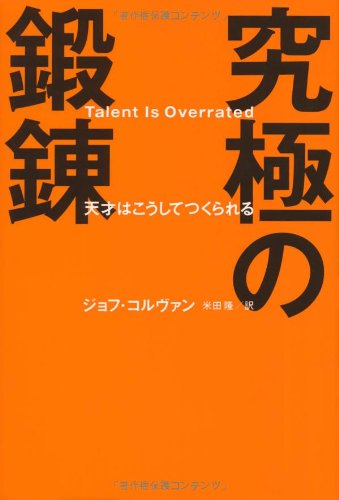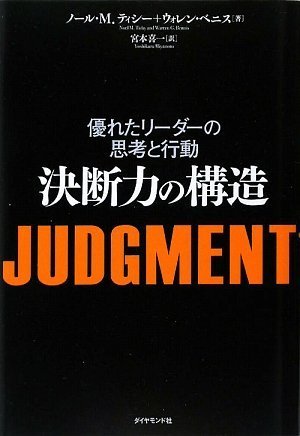まえがき
「キー・コンピテンシーとは、OECDが1999年〜2002にかけて行った「能力の定義と選択」(DeSeCo)プロジェクトの成果で、多数の加盟国が参加して国際的合意を得た新たな能力概念です。」
リスト
- 【カテゴリ1 状況に応じてツールを使う】
- 1-A 状況に応じて言語・シンボル・テキストを使う
- 1-B 状況に応じて知識・情報を使う
- 1-C 状況に応じてテクノロジーを使う
- 【カテゴリ2 異質な集団の中でやっていく】
- 2-A 他者とうまく関わる
- 2-B 協力し、チームの中で働く
- 2-C 対立を処理し、解決する
- 【カテゴリ3 自律的に活動する】
- 3-A 大きな展望を描いて行動する
- 3-B 人生計画や個人的なプロジェクトをつくり、実行する
- 3-C 自らの権利・利害・限界・ニーズを守る・主張する
あとがき
まえがきは「キー・コンピテンシーの生涯学習政策指標としての活用可能性に関する調査研究」(国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部)より。
リストは、”THE DEFINITION AND
SELECTION OF KEY COMPETENCIES Executive Summary“(OECD、PDFファイルへのリンク)から下記の文言を抽出し、他サイトの訳も参考にしながら独自に訳しました。これらのコンピテンシーの中心に「思慮深さ」(Reflectiveness)があると定義されています。
このキー・コンピテンシーがどのように定められたか、DeSeCoプロジェクトを紹介している「人格とキー・コンピテンシー」(名城大学 大学院大学・学校づくり研究科)という論文から引用します。
『 要するに、「キー・コンピテンシー」は、例えば、心理学のパーソナリティ理論のようなものから直接に導出されるものではなく、「今日の社会は、その市民に対して、どのような要請を掲げているのか」、あるいは「個人が眼前の社会の中で順調に機能を果たすためには何が必要か」(OECD 2005 p.6) という問いに導かれて決定されるのである。』
原文は下記の通りです。
Category 1: Using Tools Interactively
A. Use language, symbols and texts interactively
B. Use knowledge and information interactively
C. Use technology interactively
Category 2: Interacting in Heterogeneous Groups
A. Relate well to others
B. Co-operate, work in teams
C. Manage and resolve conflicts
Category 3: Acting Autonomously
A. Act within the big picture
B. Form and conduct life plans and personal projects
C. Defend and assert rights, interests, limits and needs
またプロジェクトの成果は和訳・出版されているようです。
- タイトル: キー・コンピテンシー
- 著者: ドミニク・S. ライチェン(著)、ローラ・H. サルガニク(著)、立田 慶裕(監訳)、今西 幸蔵(翻訳)、岩崎 久美子(翻訳)、猿田 祐嗣(翻訳)、名取 一好(翻訳)、野村 和(翻訳)、平沢 安政(翻訳)
- 出版社: 明石書店
- 出版日: 2006-06-02