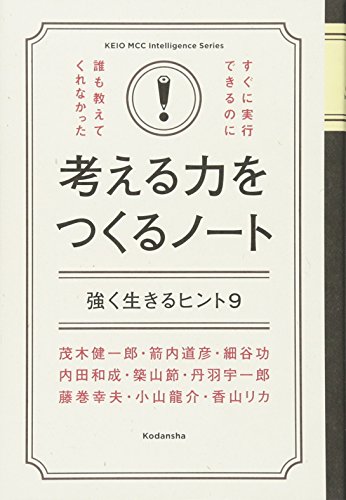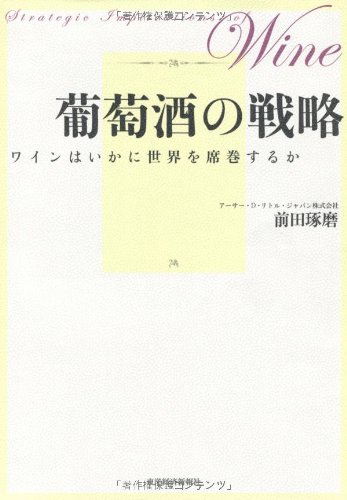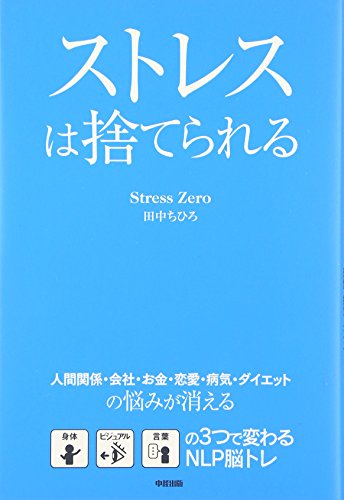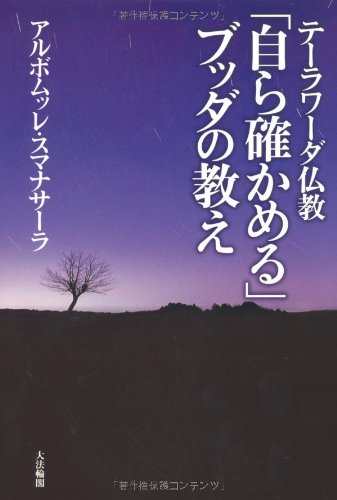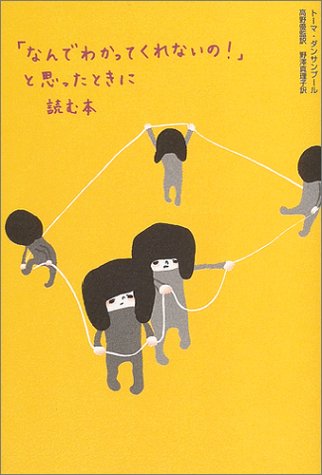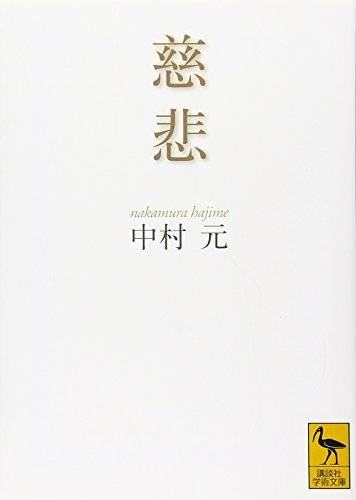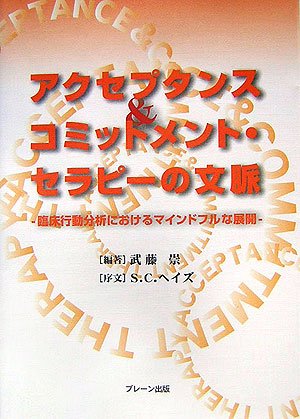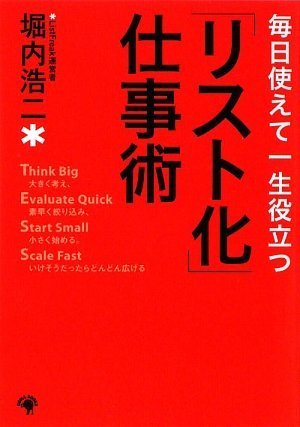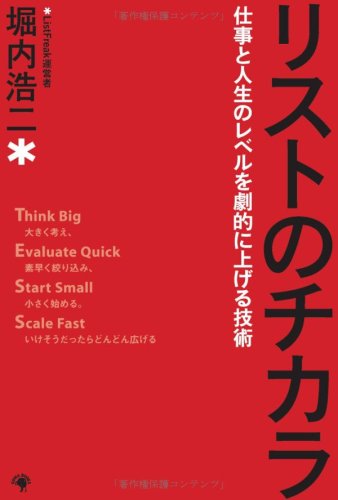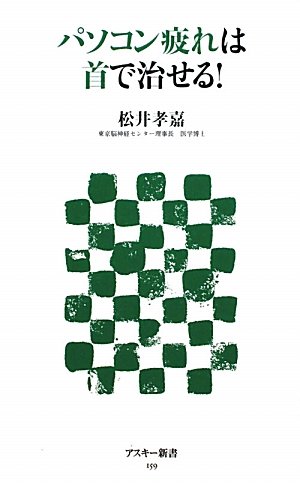まえがき
茂木健一郎氏の文章から。
リスト
- 「快楽主義者」になると決める!(目的意識を強くもち、脳の抑制をとりはずすため)
- 多様な体験をし、「記憶(データ)」のアーカイブを増やす(アイデアの源となるため)
- 「睡眠」をきちんととる(ひらめきの元データである記憶を整理してくれるため)
- 「自分の居場所」をつくる(愛着のもてる人や場所を拠り所に発想、行動できるため)
- 行動して、人に出会い、“新しい自分”を発見する(受け入れる心をもつため)
あとがき
まえがきを含めて
『考える力をつくるノート 〜 すぐに実行できるのに誰も教えてくれなかった』より。ビジネス書などで有名な著者が自説をコンパクトにまとめ直した感のある、お得なようなお得でないような?本でした。
章ごとにまとめリストがあります。もっとも完成度が高いと思われたリストを選んで引用しました。
- タイトル: すぐに実行できるのに誰も教えてくれなかった考える力をつくるノート (KEIO MCC Intelligence Series)
- 著者: 茂木 健一郎(著)、箭内 道彦(著)、細谷 功(著)、内田 和成(著)、築山 節(著)、丹羽 宇一郎(著)、藤巻 幸夫(著)、小山 龍介(著)、香山 リカ(著)
- 出版社: 講談社
- 出版日: 2010-06-25