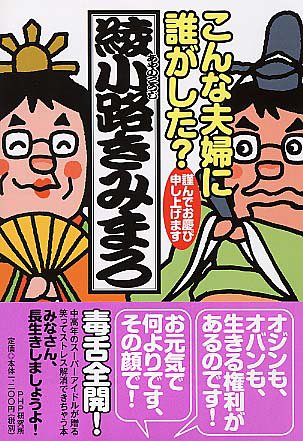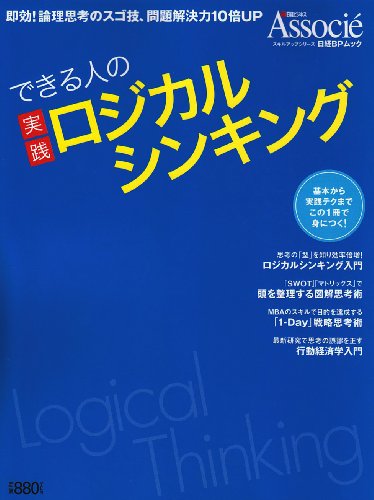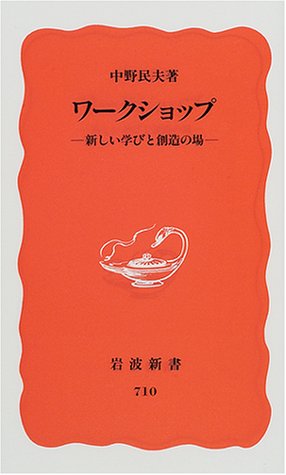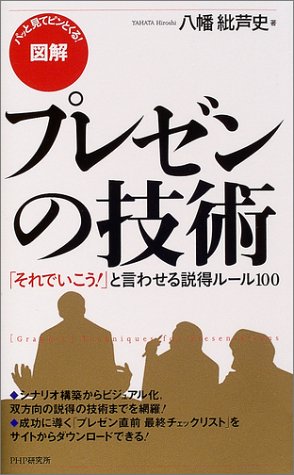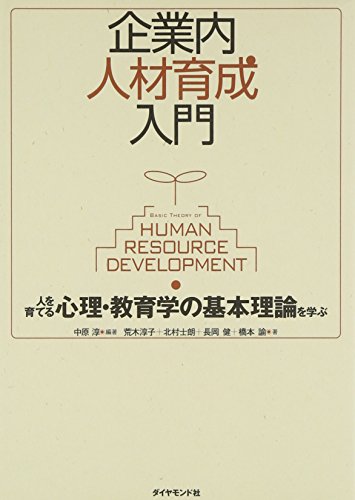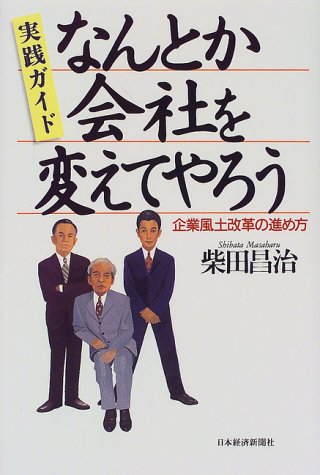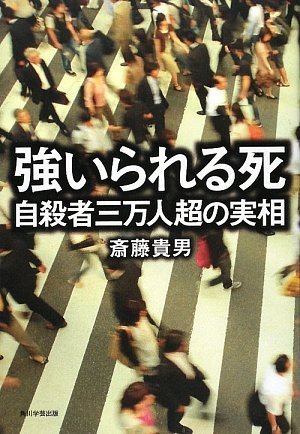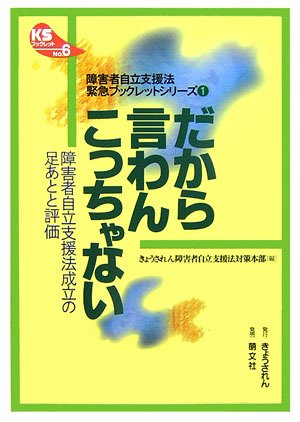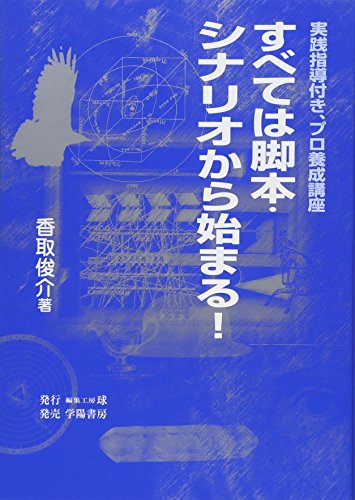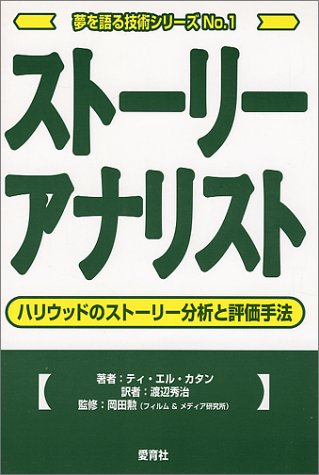まえがき
出典確認中。
リスト
- 【は】半分でいい
- 【ひ】人並みでいい
- 【ふ】普通でいい
- 【へ】平凡でいい
- 【ほ】ほどほどでいい
あとがき
「TVで観たよ」と教えてくれる人がありました。ブログエントリなどを総合すると、「検事・朝日奈耀子」(Wikipedia)というドラマ番組の1作で、2009年3月7日に放映された「生きたまま死後硬直!?医師の顔を持つ女検事vs“4回殺された男”時間逆流トリック!」(なんというタイトル……)という番組で出てきたらしいです。
さらにさかのぼると、綾小路きみまろさんが、2005年10月25日の「ぴったんこカン★カン」という番組でほぼ同じことを言っていたと書いているブログエントリを発見。
(2012/04/05 追記)
『人生の幸せ「はひふへほ」の出典 – NOTA』という記事を発見。そこでも綾小路 きみまろ氏の『こんな夫婦に誰がした? 謹んでお慶び申し上げます』が出典として挙げられています。
- タイトル: こんな夫婦に誰がした? 謹んでお慶び申し上げます
- 著者: 綾小路 きみまろ(著)
- 出版社: PHP研究所
- 出版日: 2005-12-01