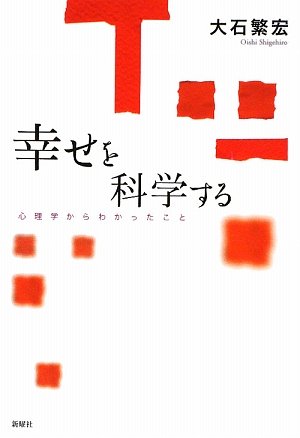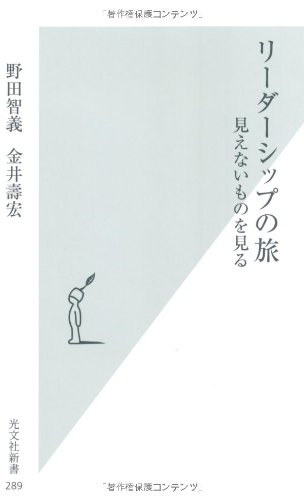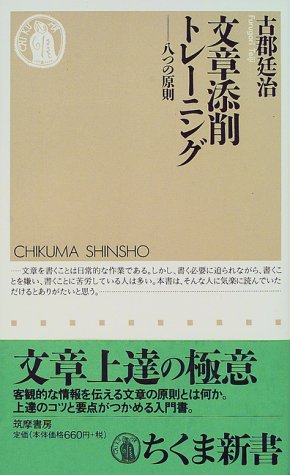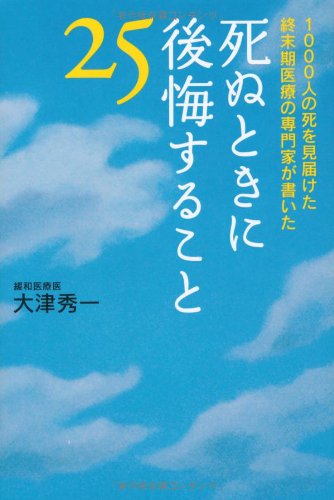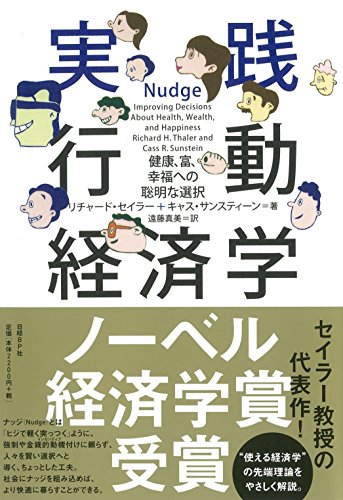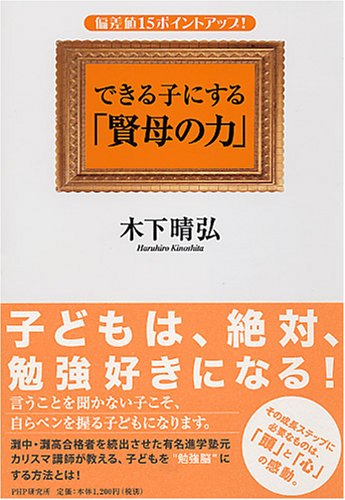まえがき
「最近では、(略)さまざまな性格特性はこの5つの因子(ファクター)に大きく分類できるという結果が出ている」
リスト
- Openness(新しいものの受け入れやすさ)
- Conscientiousness(まじめさ)
- Extraversion(外向性)
- Agreeableness(同調性)
- Neuroticism(ネガティブな感情の持ちやすさ)
あとがき
まえがきは『幸せを科学する―心理学からわかったこと』p120より。読んでへーと思ったので、検索してみたところ、”Big Five personality traits“(Wikipedia)がヒットしました。OCEANというアクロニムが定着しているわけではなさそうですが、こうしておけば覚えやすいですよね(ただし、Conscientiousnessは思い出せないだろうなあ……)。
日本語のWikipediaでも、「性格」の欄に「5因子モデル」として紹介されていました。「日本語訳が定まっていないものもある」とのことだったので、意訳をつけてみました。『幸せを科学する』では、それぞれ「オープンさ、善良さ、社交性、同調性、神経症傾向」となっています。
- タイトル: 幸せを科学する―心理学からわかったこと
- 著者: 大石 繁宏(著)
- 出版社: 新曜社
- 出版日: 2009-06-01
(追記 2010/06/22)
“Emotional Intelligence: New Ability or Eclectic Traits?“(PDF)という論文を読んでいたら、たまたまこれらの因子が紹介されていました。それぞれの因子が、対立する言葉の組み合わせとして定義されていて分かりやすかったのでメモ。
Openness–Closedness
Conscientiousness–Carelessness
Extraversion–Introversion
Agreeableness–Disagreeableness
Neuroticism–Stability