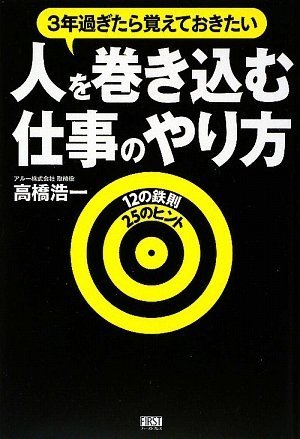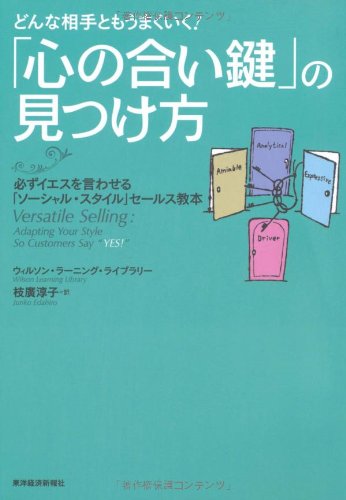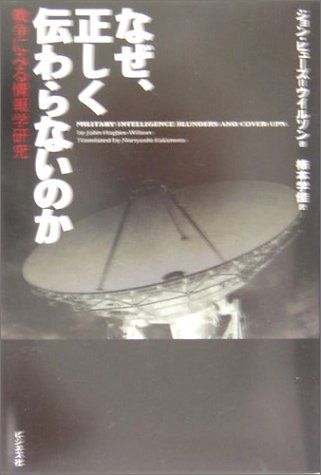まえがき
世界じゃんけんソサエティーの戦略ガイドより。基本戦略は2つ。相手に特定の手を出させないか、逆に特定の手を出させるようにしむけること。
リスト
- 初心者にはパーを出す
初心者はグーを出しやすい。 - 経験者にはチョキを出す
経験者は1を知っている。 - あいこが2回続いたら、次はそれに負ける手を出す
グーでのあいこが2回続けば、相手はチョキかパーに変えたくなる。それに負けない手はチョキ、つまりあいこだった手に負ける手。 - 宣言して出す
「グーを出すぞ」と言えば、相手はパーを出しづらくなる。そこでグーを出す。 - 前回の相手の手に負ける手を出す
相手がグーで負け、再戦するとする。相手は前回の結果を挽回する手(パー)を選びがち。だからチョキを出す。 - 出して欲しい手を示す
試合の前にチョキの形を相手に見せる。すると相手はチョキを出しがち。 - 困ったらパーを出す
統計的にはグーが一番多く出る。 - 複数回勝負に持ち込む
初回で勝てばそのまま。負けたらすぐさま「よし、3回勝負の2回目をやろう」と持ちかける。信用を失ってもいい、あるいはどうしても勝ちたいときに。
あとがき
“How to Beat Anyone at Rock Paper Scissors” (World RPS Society) より、やや意訳。説明も最小限に絞っていますので、なぜそう言えるのか不思議に思った方はリンク先を覗いてみてください。
「統計的手法で、ジャンケンで勝つ方法」(永井孝尚のMM21:ITmedia オルタナティブ・ブログ)というエントリを読んで興味を持ち、元ネタの内容により忠実と思えるように訳し直しました。
対人勝負というのは突き詰めていくと心理戦になりますね。じゃんけんもしかり。子どもで練習してみようかな。